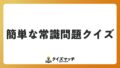野菜の色、成分、分類など、見慣れた食材の基本的な知識を問うクイズが10問用意されています。
野菜の成熟過程や栄養特性、植物学上の分類など、野菜の基礎知識を楽しみながら深めることができるでしょう。
見た目や食感から判断しがちな野菜ですが、意外な事実が隠されていることもあります。
クイズに挑戦し、普段の食生活に役立つ知識を得られる一助となれば幸いです。
Q1 : 未成熟の大豆を収穫した枝豆はどの植物分類上の科に属するでしょう?
大豆および枝豆はマメ科(Fabaceae)に属する一年草で、根に根粒菌が共生し空気中の窒素を固定する能力があるため、古くから重要な緑肥作物としても利用されてきました。マメ科共通の蝶形花や莢を持ち、タンパク質が豊富で畑の肉と呼ばれます。アブラナ科はキャベツやダイコン、ナス科はトマトやジャガイモ、ヒユ科はホウレンソウなどが所属し、花の形態や栄養生理が異なります。枝豆は若い莢を食用にするため甘味と旨味が強いのが特徴です。
Q2 : 中華料理などで使われる「ニンニクの芽」は実際にはニンニクのどの部位を収穫したものでしょう?
市販される「ニンニクの芽」は、正確には鱗茎から伸びてくる花茎(スコープ)を若いうちに摘み取ったものです。この部分は伸びると先端に紫色の花序を形成しますが、栄養が分散すると球が太らないため、食用兼栽培管理として摘み取られます。葉身部分はもっと扁平で薄く、根は髭状の部分、鱗茎は普段食べる球のことなので、名称と実際の部位が一致しにくい点を確認しておくと調理や栽培知識が深まります。
Q3 : 沖縄でゴーヤーと呼ばれるウリ科の野菜の正式な和名はどれでしょう?
ゴーヤーは沖縄方言で、植物学的な標準和名はツルレイシ(蔓茘枝)です。ニガウリという通称も広く用いられますが、学術書や種苗名簿ではツルレイシが正式表記となっています。学名Momordica charantiaのウリ科一年草で、強い苦味成分モモルデシンを含み、夏場のビタミンC補給やグリーンカーテンとしても重宝されます。キワノは別種のツノニガウリ、ヘチマは同じウリ科でも属が異なり、スポンジ状の果皮をたわしに利用する点で用途が異なります。
Q4 : トマトの赤い色の主な色素として正しいものはどれでしょう?
完熟トマトの鮮やかな赤色はカロテノイドの一種リコピンによるものです。成熟過程でクロロフィルが減少し、リコピン合成酵素が活発になることで色が赤く変わります。リコピンは活性酸素種を消去する抗酸化力が高く、油脂や加熱処理で細胞壁が崩れると体内吸収率が向上します。クロロフィルは葉緑素、アントシアニンは紫色系色素、カプサイシンは辛味成分でトマトの色づきには寄与しません。
Q5 : ブロッコリーとカリフラワーはもともとどの野菜を品種改良して作られた仲間でしょう?
ブロッコリーとカリフラワーはいずれも地中海沿岸原産の野生キャベツ(Brassica oleracea)を祖先とするアブラナ科の変種です。キャベツは葉を球状に結球する方向に改良されましたが、ブロッコリーは花蕾を肥大させ、カリフラワーは花蕾を白化させながら緻密に発達させるよう選抜されました。同種由来のため栄養組成も近く、スルフォラファンなどのイソチオシアネート系成分を含みます。ハクサイやレタスは別属で、ケールは原種に近い葉キャベツに相当しますがブロッコリーとは異なる栽培形態です。
Q6 : ほうれん草を大量に生で食べたときに尿路結石の原因になりやすいとされる成分はどれでしょう?
ほうれん草には水溶性のシュウ酸が比較的多く含まれ、体内でカルシウムと結合して難溶性のシュウ酸カルシウムとなると、腎臓や尿路で結晶化しやすくなります。茹でこぼして水にさらすとシュウ酸の大部分が流出し、さらにカルシウム豊富な小魚やチーズと一緒に摂ることで結合して排出されやすくなります。クエン酸は逆に結石を防ぐ有機酸、リノール酸は脂質、グルタミン酸はうま味成分で、結石形成に直接関与しません。
Q7 : ジャガイモの芽や皮が緑化した部分に多く含まれる有毒成分はどれでしょう?
ジャガイモが光に当たるとクロロフィルの合成と同時にステロイドアルカロイドのソラニンやチャコニンが増加します。これらは加熱では分解しにくく、少量でも嘔吐・腹痛・めまいなどを引き起こすことがあります。特に発芽部や青緑色に変色した皮には高濃度で蓄積するため、家庭では芽を深くえぐり取り、皮の青い部分を厚くむいて廃棄することが推奨されます。他の選択肢はジャガイモにはほとんど含まれない別種の成分です。
Q8 : タマネギを刻むと涙が出る主な原因物質はどれでしょう?
タマネギの細胞を切断するとアリイナーゼという酵素が働き、含硫化合物が分解されて揮発性の硫化アリル(正確にはプロパンチアール-S-オキシド)が生成されます。この気体が目の粘膜を刺激し、保護反応として涙腺から涙が分泌されます。リコピンはトマトの赤色素、β-カロテンはニンジンの色素、イソフラボンは大豆成分で、いずれも催涙作用を持ちません。包丁を冷やす、水にさらすなどで酵素活性を下げると涙は軽減できます。
Q9 : ニンジンが属する植物の科はどれでしょう?
ニンジンはパセリやセロリと同じセリ科に分類され、傘状に広がる散形花序や、中空の茎などの特徴を共有しています。根がオレンジ色なのはβカロテンを大量に蓄積するためで、16世紀のオランダで現在の橙色品種が育成されました。ユリ科はタマネギ、ナス科はトマト、マメ科はエダマメなどで、花の形や胚珠の付き方が異なり、分類学的に明確に区別されます。
Q10 : 緑色のピーマンが完熟すると一般的に何色になるでしょう?
ピーマンは未熟果の緑色の状態で出荷されることが多いだけで、果実自体はパプリカと同系統のトウガラシ属なので、熟すとクロロフィルが分解されカロテノイドが増加し赤色に変わります。色の変化とともに糖度やうま味が増し、ビタミンC・βカロテンの含有量も高くなるため、赤ピーマンは緑の状態より甘く栄養価も優れています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は簡単な野菜クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は簡単な野菜クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。