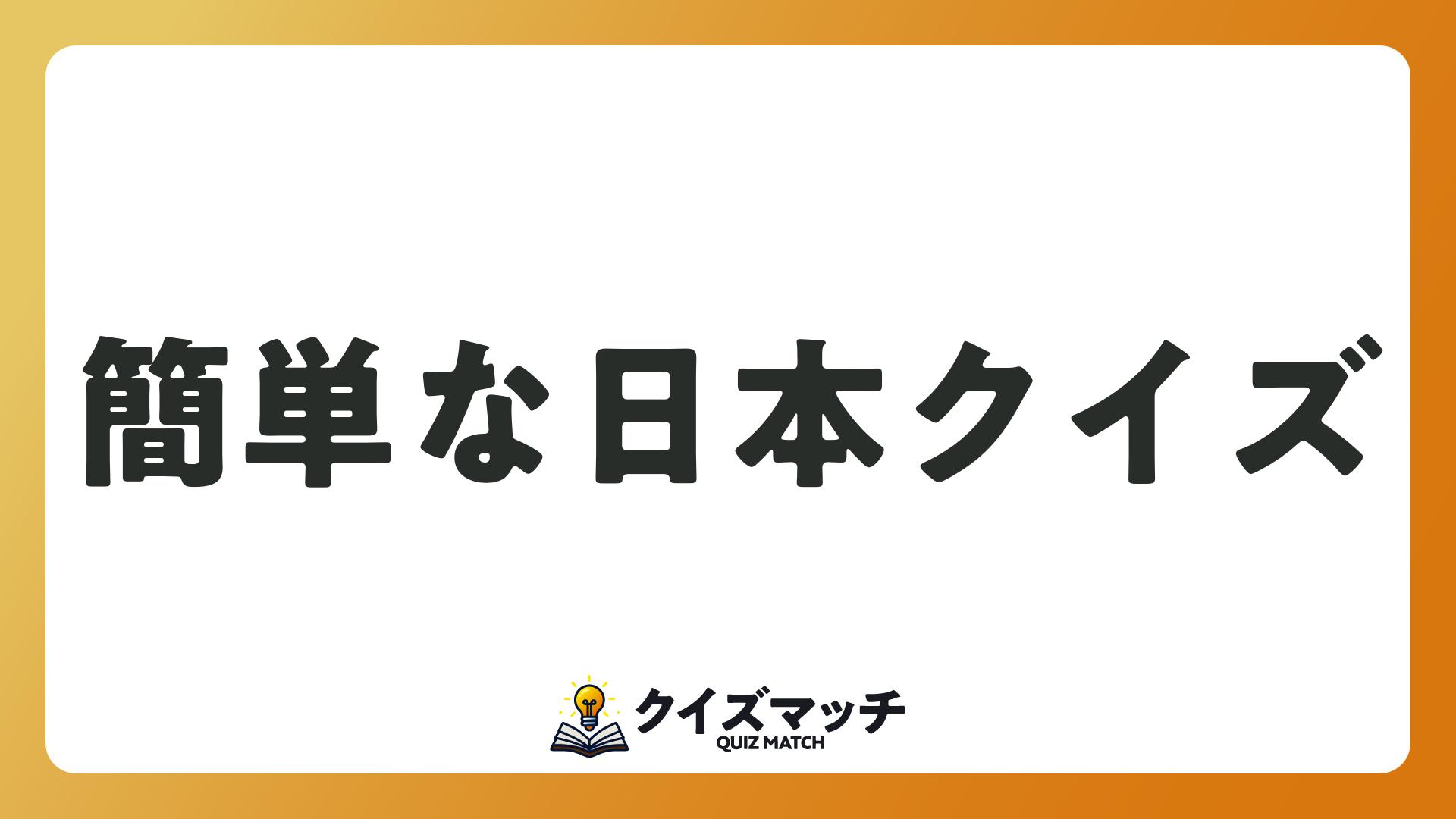日本の伝統文化や歴史に関する豊かな遺産を探究するため、簡単な日本クイズに挑戦してみましょう。国鳥や名所、文学作品、古典など、様々な角度から日本の魅力に迫る10問が用意されています。日本人なら誰でも知っているような定番の話題から、意外な事実まで網羅しています。ご自身の知識を確認したり、新たな発見をするきっかけになれば幸いです。気軽に楽しみながら、日本の深い歴史と多様な文化について理解を深めていただければ幸いです。
Q1 : 日本最高峰・富士山の標高はおよそ何メートル?
富士山は山梨県と静岡県に跨る成層火山で、日本最高峰の標高3776.24メートル(国土地理院測定)を誇ります。古来信仰の対象として崇められ、数多くの浮世絵や詩歌に描かれてきました。2013年には『富士山―信仰の対象と芸術の源泉』として世界文化遺産に登録され、その景観価値と宗教的意義が高く評価されています。気象観測や地質研究の重要拠点でもあり、近年は登山者増加に伴う混雑や環境負荷への対策が進められています。
Q2 : 合掌造り集落で有名な『白川郷』がある都道府県は?
白川郷は岐阜県大野郡白川村に位置し、急峻な山岳地帯の豪雪に適応した合掌造り家屋が数多く残る集落です。1995年には富山県の五箇山とともに『白川郷・五箇山の合掌造り集落』としてユネスコの世界文化遺産に登録されました。切妻の茅葺き屋根を持つ建物は、屋根裏で養蚕が行える機能性を備え、地域共同体による結の精神で維持されてきました。観光地化が進む一方、伝統的景観保全と住民生活の両立が課題となっています。
Q3 : 江戸幕府の第8代将軍は誰?
徳川吉宗は1716年に江戸幕府第8代将軍に就任し、『享保の改革』を断行して財政再建と社会秩序の立て直しを図りました。倹約令の発布、上米の制の導入、公事方御定書による裁判基準の整備、将軍自ら庶民の訴えを聞く目安箱の設置など、実務重視の政策で知られます。また西洋医学を取り入れるための『蘭学』奨励や甘藷栽培の普及など、文化・自然科学の発展にも寄与しました。その実績から『米将軍』とも称され、人気の高い将軍です。
Q4 : 元号『令和』の典拠となった日本の古典は?
2019年5月1日に施行された元号『令和』は、『万葉集』巻五に収められた梅花の宴の序文『初春の令月にして、気淑く風和ぎ…』から採られました。万葉集は8世紀に編纂された最古の歌集で、天皇から農民まで階層を超えた歌が収められています。新元号制定にあたり、日本の古典を初めて典拠としたことで注目を集め、国書由来の元号としては確認できる最初の事例とも言われます。出典の選定には有識者会議の審議を経て閣議決定が行われました。
Q5 : 世界遺産・法隆寺が建つ都道府県は?
法隆寺は奈良県生駒郡斑鳩町に所在し、607年に聖徳太子と推古天皇によって創建されたと伝えられます。現存する世界最古級の木造建築群として1993年に日本初のユネスコ世界文化遺産に登録されました。五重塔や金堂の壁画、玉虫厨子など飛鳥文化を代表する貴重な遺産を有し、日本仏教史や建築史の研究に欠かせない寺院です。奈良県には東大寺や薬師寺など歴史的寺院が集中し、『古都奈良の文化財』として広く知られています。
Q6 : 東海道五十三次の起点となった場所はどこ?
東海道五十三次は江戸日本橋から京都三条大橋まで続いた約492㎞の主要街道で、江戸幕府が整備しました。起点の日本橋は全国の道路元標とされ、物流と文化交流の中心地として繁栄しました。歌川広重の浮世絵『東海道五十三次』は宿場ごとの風景を描き、庶民の旅行熱をかき立てました。現在も橋の中央には道路元標が設置され、国道1号・4号など複数路線の起点を示しており、観光名所として多くの人が訪れています。
Q7 : 次のうち『日本三名園』に含まれない庭園は?
日本三名園とは、江戸時代を通じて諸国を巡った儒学者・林鵞峰らにより選ばれた兼六園(石川県金沢市)、後楽園(岡山市)、偕楽園(水戸市)の3つを指します。いずれも大名庭園の特徴である回遊式で、四季折々の景観が楽しめる名勝です。対して六義園は江戸幕府五代将軍徳川綱吉の側用人・柳沢吉保が築いた庭園で、東京都文京区に位置します。格式は高いものの三名園には含まれないため、誤答としてよく用いられます。
Q8 : 小説『坊っちゃん』の作者は誰?
『坊っちゃん』は1906年に朝日新聞で連載された夏目漱石の代表作です。松山中学に赴任した若い教師が正義感ゆえに騒動を起こす痛快な物語で、漱石自身の松山での教師経験が色濃く反映されています。漱石は『吾輩は猫である』『こころ』などでも知られ、明治期の近代日本語文学を確立した作家として評価が高い人物です。現在も千円紙幣の肖像に採用されるなど、国民的文豪として親しまれています。
Q9 : 日本で最も長い川はどれ?
信濃川は長野県の甲武信ヶ岳付近を源に千曲川として流れ、新潟県に入ると信濃川と名を変え、日本海へ注ぎます。全長367㎞で日本一長い川です。流域では稲作が盛んで、越後平野の肥沃な土壌を形成するほか、歴史的には川舟による物流が発達し、北前船と結びついた米どころ文化が栄えました。近年は治水と環境保全の両立を図る取り組みが進められ、カヌーやラフティングなど観光資源としても注目されています。
Q10 : 日本の国鳥に指定されている鳥は?
キジは日本神話や昔話にもしばしば登場し、鮮やかな羽色と高い警戒心を持つことから『国難を知らせる鳥』として古くから親しまれてきました。1964年に公益財団法人日本鳥類保護連盟が国民投票を行い、最も票を集めたキジが国鳥に選定され、同年政府も承認しました。狩猟対象でもありますが、現在は保護が進められ、里山の象徴的存在となっています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は簡単な日本クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は簡単な日本クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。