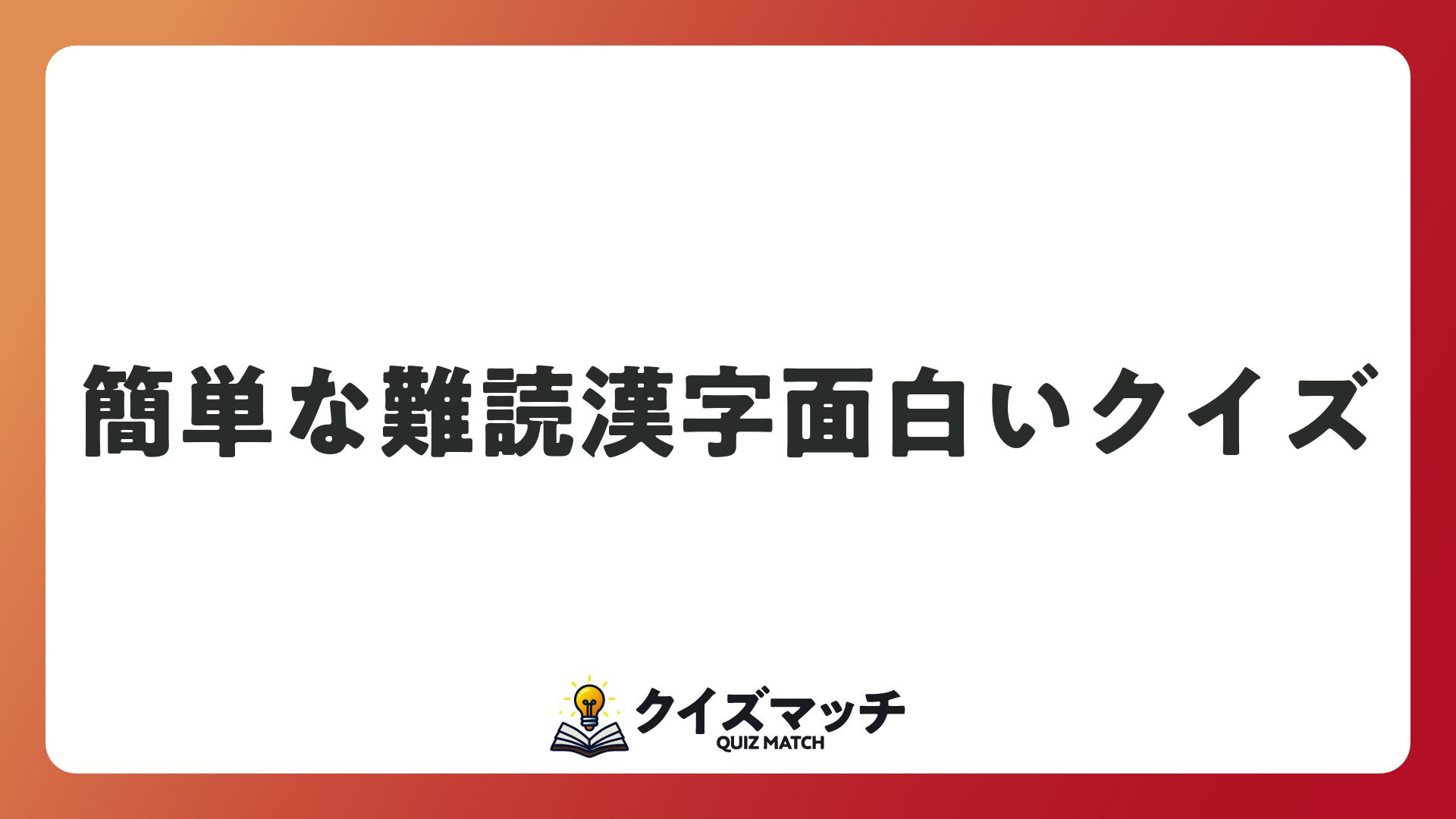「漢字クイズ 思わずつまずく難読漢字から学ぶ面白い日本語」
漢字表記は時と場合によって変化し、同じ字でも複数の読み方がある。そのため、慣れ親しんだ言葉でも誤読してしまうことがある。本記事では、そうした「思わずつまずく」難読漢字のクイズを10問ご紹介。語源や背景知識を踏まえて正解を探求することで、日本語表現の奥深さに迫りたい。専門用語からビジネス文書、日常会話まで、幅広い場面で役立つ知識が満載。漢字の不思議を解き明かし、語彙力と表現力の向上につなげていただければと思う。
Q1 : 応援や肩入れを意味する「贔屓」の読みは?
「贔屓」は特定の人物や店を特別に好み力を貸す行為を指し、読みは「ひいき」が正しい。古くは歌舞伎の常連客が役者を経済的に支援した風習に由来するとされる。漢字の『贔』には“強く支える”、“屓”には“背負う”という意味があり、合わせて“力を入れて持ち上げる”イメージが形成される。スポーツ観戦で好きなチームを応援する際や、ビジネスで特定の取引先を優遇する状況を説明する際にも用いられるため、読みとニュアンスを知っておくと表現が豊かになる。
Q2 : 副詞「悉く」の読みは?
「悉く」は“残らずすべて”という意味を担う副詞で、読みは訓読みの「ことごとく」である。「悉」は“細部に至るまで”を示す漢字で、送り仮名の有無によって意味と読みが変化する点が特徴だ。『悉に』と書く場合は“つぶさに”と読み、“くわしく”という意味に転じるため注意が必要である。文章語に多用され口語ではあまり聞かれないが、論説文や契約書など厳密な場面で使われるため、読みとニュアンスを知っておくと理解力が向上し語彙の幅も広がる。
Q3 : 思いやりを示す動詞「労る」の読みは?
「労る」は相手の身体的負担や心の痛みに寄り添い大切に扱うことを表し、読みは「いたわる」が一般的である。同じ部首を持つ「労う」は「ねぎらう」と読み、功績を褒め称える意味になるため混同は禁物だ。手紙やメールで「ご自愛ください」と同じ文脈で使われることが多く、正しい使用は丁寧さや温かみを伝える上で効果的である。語源を理解していれば、ビジネスでもプライベートでも自然に使い分けができ、相手への配慮がより的確に伝わる。
Q4 : 建設業で使われる「竣工」の読みは?
「竣工」は建築物や大型設備の工事が完了して使用可能になることを示し、正式な読みは「しゅんこう」である。「竣」は“おわる”、“工”は“工事”を表すため、熟語としての意味は直感しやすいものの、音が聞き取りにくく「しゅうこう」と誤読されがちである。建設業界では竣工図、竣工検査など関連語が多く、式典や報道資料でも頻繁に登場する。読みを間違えると取引先に専門性を疑われる恐れもあるので、業界外でも正確に発音できるようにしておくと信頼感が高まる。
Q5 : ビジネス文書によく出る「齟齬」の読みは?
「齟齬」は二者間の意見や計画がかみ合わずに生じる食い違いを表す熟語で、読みは濁音入りの「そご」が正解である。字形が複雑なので手書きでは略字が使われることも多いが、公文書では正字体が望ましい。語源は獣の上下の歯がずれて当たらない様子を示す「齟」と「齬」が対になり、並置することでズレがより強調される構造になっている。会議や契約書で用いると専門的で端的な印象を与えられるため、読みと意味を確実に押さえておくとビジネスコミュニケーションが円滑になる。
Q6 : 「恣意」という言葉の読みは?
「恣意」は自分勝手な考えや気ままな振る舞いを指し、哲学や法学では客観的根拠のない判断を批判する際に使われる。字を分けると「恣」は“ほしいまま”、“意”は“こころ”を意味し、合わせて“勝手な思い”を端的に示す熟語となる。発音は一拍で「しい」と短く、口頭では聞き取りにくいうえ、送り仮名を伴う動詞形が存在しないため誤用が多い。文章で見かけた際にはネガティブ評価の語であることを理解し、文脈から主体が誰かを見極めると内容把握が容易になる。
Q7 : 文章で見かける副詞「徐に」の読みは?
「徐に」は動作をゆっくりと始めるさまを表す副詞で、現代語では「おもむろに立ち上がる」のように用いられる。漢字の「徐」は“ゆるやか”を意味し、送り仮名を付けずに副詞化することで静かながら確かな行動開始を示すニュアンスが生まれる。単に速度が遅いだけでなく、慎重さや控えめな意思表示が含まれる点がポイントである。文学作品では緊張感を高める演出として頻出するため、読みを把握しておくと場面の機微をより正確につかめる。
Q8 : 医療用語「浮腫」の読みは?
「浮腫」は体内に余分な水分がたまり、手足や顔が膨らむ症状を示す医学用語で、正式な音読みは「ふしゅ」である。日常会話では訓読みの「むくみ」が圧倒的に多いが、カルテや検査結果の所見では「浮腫」を略して“F”と書き「ふしゅ」と読ませる慣習がある。漢字は水が浮かんで腫れる様子を直感的に表し、意味理解は難しくないが読みは覚えていないと聞き取れない。医療系のニュースやドラマをより深く理解するために知っておきたい語である。
Q9 : 「貼付」の読みとして正しいものは?
「貼付」は書類に切手や写真などを貼り付ける行為を指し、官公庁や医療現場では音読みの「ちょうふ」が正式とされる。一方コンピュータ用語で「ファイルを添付する」と言う場合は「てんぷ」が慣用となり、同じ漢字でも読み分けが必要になる。意味は想像しやすいが読みを取り違えると専門職では重大な誤解を招くことがあるため注意したい。語源は「貼る」と「付ける」の組み合わせで、動作そのものを的確に表現している点が興味深い。
Q10 : 「五月蠅い」の正しい読みはどれ?
「五月蠅い」は五月頃に大量発生して人を悩ませるハエを指す語が語源で、そこから人や音が騒々しく煩わしい様子を示す意味へ派生した。新聞や公文書では仮名書きが通例だが、小説や漫画では場面の空気を強調するために漢字表記が用いられることも多い。読み方は訓読みの「うるさい」以外にほぼ存在せず、覚えてしまえば対応できるが、書く場面を誤ると固い印象になりやすい点に注意が必要である。文脈に応じて平仮名と漢字を使い分けることが表現力向上の鍵となる。
まとめ
いかがでしたか? 今回は簡単な難読漢字面白いクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は簡単な難読漢字面白いクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。