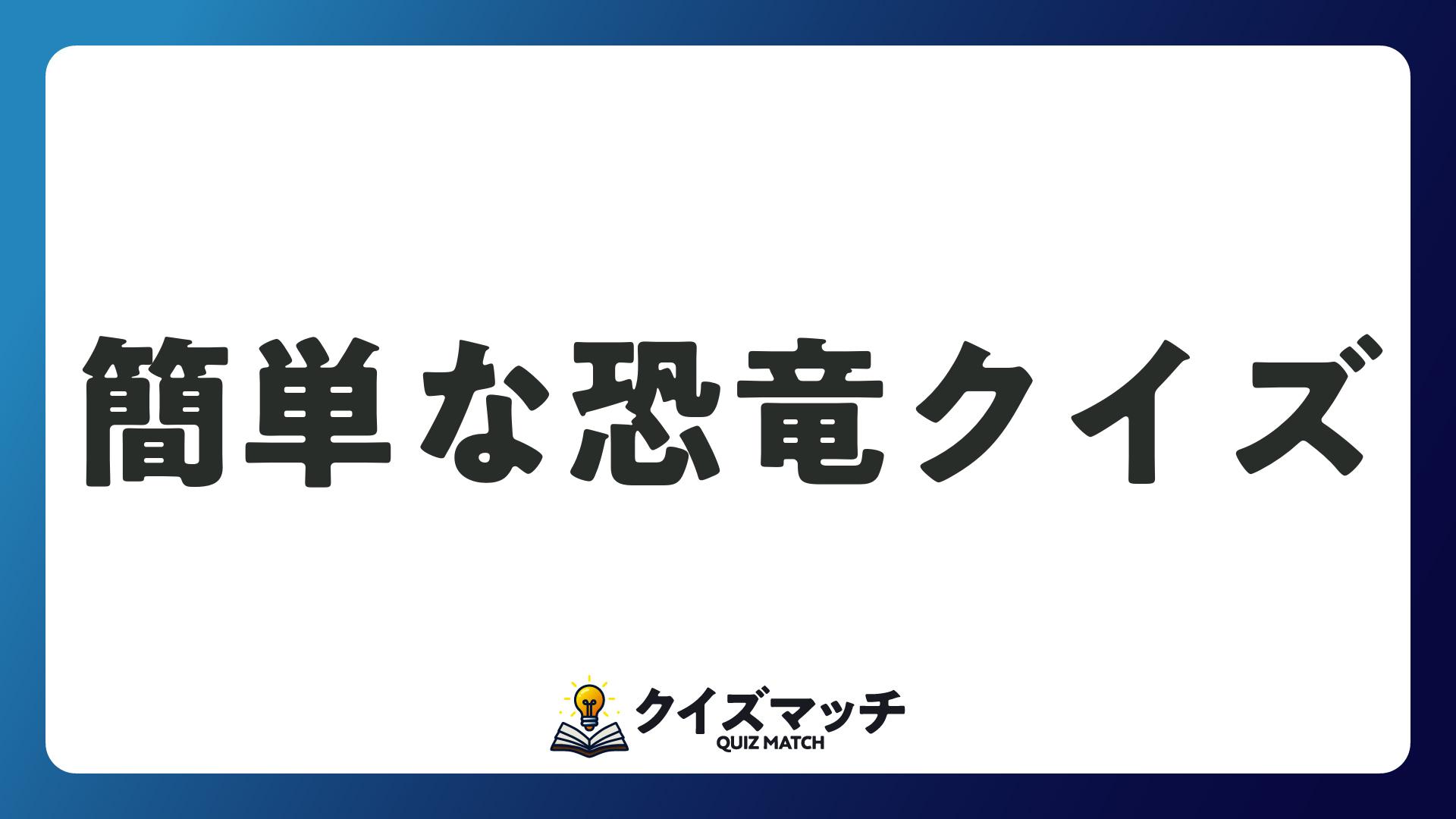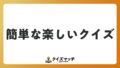恐竜好きのみなさん、こんにちは。恐竜はとても魅力的な生物ですね。今回は、恐竜をテーマにした簡単なクイズをお楽しみいただきます。全10問の内容は、ティラノサウルスの生息時代やトリケラトプスの角の本数、ヴェロキラプトルの体表構造など、恐竜に関する基本的な知識をチェックするものです。答えを確認しながら、恐竜の不思議な世界をさらに探求してみてください。一緒に楽しみましょう!
Q1 : デイノニクスという学名が示す意味は何?
デイノニクスの名称はギリシア語のdeinos(恐ろしい)とonyx(爪)から作られ、特に第2趾にある大型の鎌形爪にちなんでいる。この爪は獲物に跳びかかって深く突き刺し、出血させる武器だったと考えられる。1960年代にジョン・オストロムが発表した詳細研究は、恐竜が敏捷で温血的だったことや鳥類との進化的近縁性を示し、恐竜研究のルネサンスを引き起こした。
Q2 : アンキロサウルスの最も顕著な防御装置はどれ?
アンキロサウルスは全身を覆う装甲板に加え、尾の先端に骨の塊が癒合したハンマー状クラブを持つ。脊椎が硬く連結され筋肉が強化されているため、クラブを左右に振り回して捕食者の骨を砕くことができたと力学解析で示されている。クチバシは大半の鳥盤類に共通し、中空骨や翼膜は本種にはないため、最大の防御要素として突出しているのは尾のハンマーである。
Q3 : 白亜紀末に大量絶滅を引き起こしたとされる最も有力な要因は?
メキシコ・ユカタン半島のチクシュルーブ・クレーターは直径約180kmの衝突痕で、形成時期が恐竜絶滅境界と一致する。世界中の同年代地層にはイリジウムや衝撃石英が濃集した薄い層があり、これは巨大隕石が蒸発させた地殻物質が降り積もった証拠とされる。衝突による粉塵は太陽光を遮断し、生態系の基盤となる光合成を阻害して食物連鎖を崩壊させたと考えられ、学界で最も広く支持されている。
Q4 : パラサウロロフスが頭骨に持つ長い突起は一般に何と呼ばれる?
パラサウロロフスの後頭部から後方に伸びる管状突起はクレストと呼ばれ、内部は複雑な空洞構造で鼻腔と連結している。空洞はホルンのように共鳴し、低周波の音を発して群れ内コミュニケーションや性的ディスプレイに使用されたと推測される。実際にCT解析と音響シミュレーションでそうした鳴声が再現され、形状の違いが雌雄や年齢差を示すとの説もある。
Q5 : イグアノドンの模式標本が最初に発見された国はどこ?
イグアノドンは1825年、イギリスの医師ギデオン・マンテルがサセックス州で採取した大きな歯を研究し、イグアナに似た歯という意味で命名した。これは学名が付与された史上2番目の恐竜であり、19世紀にロンドン水晶宮で展示された復元像は大衆に恐竜の姿を広めた。北米やアジアにも類似するハドロサウルス類が存在するが、最初の正式発見地はイギリスである。
Q6 : 次のうち恐竜に分類されない生物はどれ?
プテラノドンは翼竜に属する飛翔性爬虫類で、恐竜の定義である直立歩行の後肢骨格を持たない。恐竜は鳥類を含む陸生主竜類の一系統だが、翼竜はそれと姉妹群の非恐竜型主竜類に属するため分類学上は別グループとなる。ステゴサウルス、ブラキオサウルス、アパトサウルスはいずれも鳥盤目または竜脚形類の真正恐竜であり、恐竜に含まれないのはプテラノドンだけである。
Q7 : ディプロドクスの主な食性はどれ?
ディプロドクスは細長い首と尾を持つ竜脚類で、前方に並んだ杭状の歯は葉やシダを枝からしごき取るのに適している。顎の可動域や歯の磨耗パターン、胃石の存在など多角的な証拠が草食性を裏付け、鋭い歯や捕食に必要な咬合力は備えていない。これらの形態学的、機能的特徴から植物食恐竜であることは確実視されている。
Q8 : ヴェロキラプトルに関して現在の学説で正しいものは?
ヴェロキラプトルの近縁であるミクロラプトルなどの完全な羽毛痕が保存された化石が中国で多数発見されており、ヴェロキラプトル自身の前腕骨にも羽軸を支えるクイルノブと呼ばれる突起が確認されている。この形態学的証拠により、現代の古生物学では本属にも羽毛が密生していたと結論づけられている。うろこだけの裸の姿という旧来の復元は否定されつつある。
Q9 : トリケラトプスが持つ角の本数として正しいものは?
トリケラトプスの頭骨には鼻の上に1本、眉の上に2本の計3本の角があり、さらに後頭部を覆う大きなフリルで首を守っていた。角は防御や種内ディスプレイに使われたと考えられ、複数個体の化石には角の損傷や再生の痕跡が見られるため、捕食者のティラノサウルスと戦った形跡やオス同士の争いに利用された可能性が高い。したがって正しい角の本数は3本である。
Q10 : ティラノサウルスが生息していた時代はどれ?
ティラノサウルス・レックスは約6800万〜6600万年前の白亜紀末期(マーストリヒチアン階)に生息していたことが化石記録から明らかで、ジュラ紀や三畳紀の地層からは見つかっていない。大きな頭骨や強力な咬合力を備えた大型のティラノサウルス科恐竜が繁栄したのは白亜紀後期であり、同時期の北米の地層で多数の化石が産出していることから、この時代に限定して生息していたと考えられている。
まとめ
いかがでしたか? 今回は簡単な恐竜クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は簡単な恐竜クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。