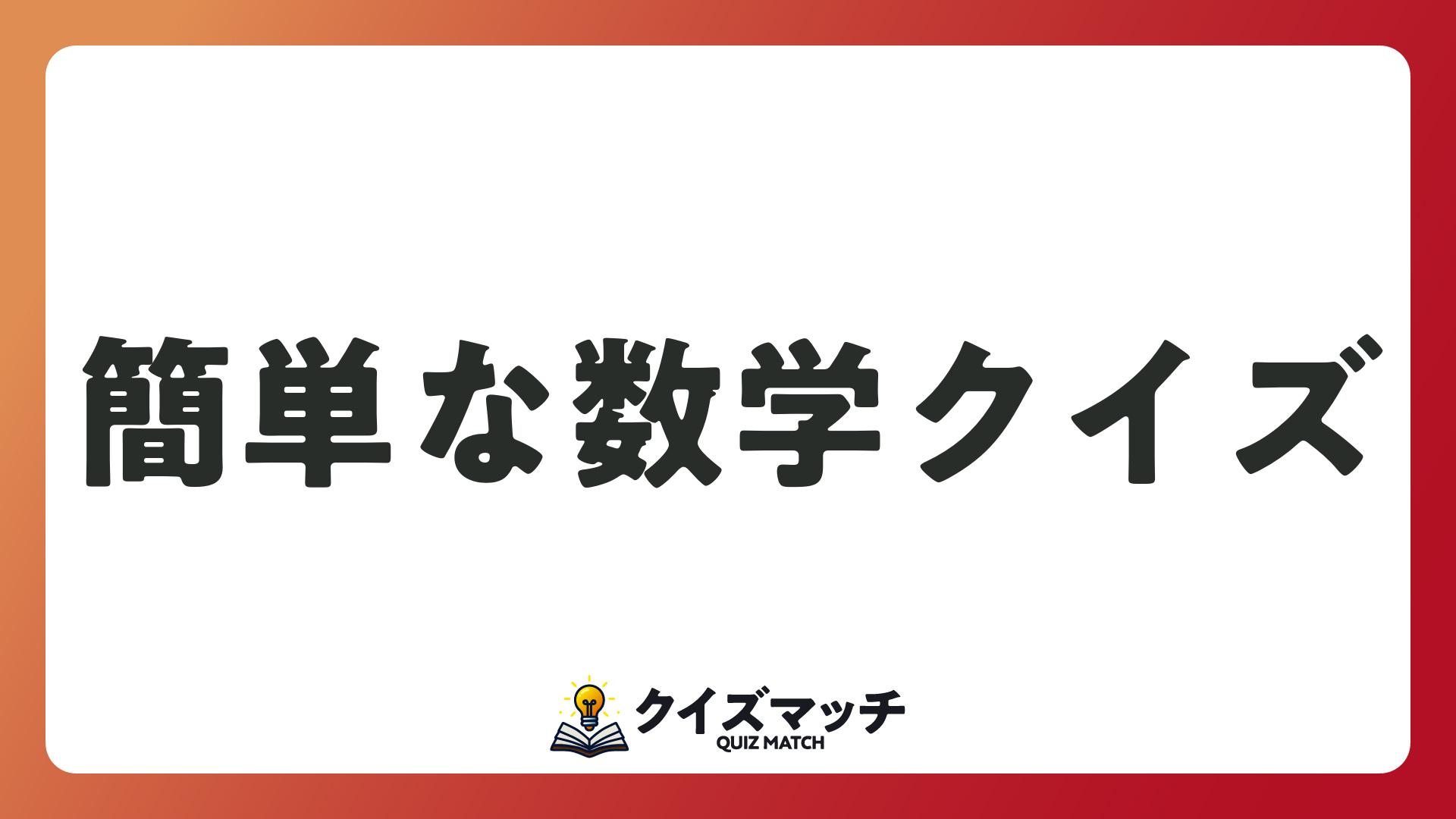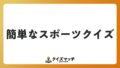数学の基本をマスターしよう!簡単な数学クイズでスキルアップ
数学は生活に密着した重要な科目ですが、時に複雑に感じることもありますね。そこで今回は、基本的な数学の概念を楽しく復習できるクイズを10問ご用意しました。二次方程式や行列、微分など、さまざまなトピックを網羅。計算力や理解力を確かめながら、数学の基礎を強化していきましょう。クイズを解いて、数学の世界をさらに深く探検しましょう!
Q1 : 複素数(2+3i)(1−2i)を計算したときの実部はいくつ?
(2+3i)(1−2i)を展開すると、まず実部同士2×1=2、交叉項−4i+3i=−i、虚部同士−6i^2=+6が実部に加算されるため、結果は8−i。よって実部は8。複素数の掛け算は分配法則で行い、i^2=−1を最後に置き換えると符号ミスが減る。選択肢5,6,7は実部の計算で最後の+6を落としたり掛け違えたりして生じる典型的エラー。手順を4項すべて書き出すことで正確さが確保できる。
Q2 : Σ_{k=1}^{5}(2k−1) の値は?
Σ_{k=1}^{5}(2k−1)は1+3+5+7+9と同義。奇数の連続和で、個数が5だから平均は中央の5、したがって総和は5×5=25と暗算も可能。直接足し算しても同じ値。数列を視覚的に把握すると計算が早く、また奇数のn個和がn^2になる一般性も見抜ける。選択肢15は偶数個と勘違い、30や35は末項を10や11と誤読したときに出る値で、途中式を明記すると誤答を防げる。
Q3 : 関数f(x)=x^3−3x^2+2の導関数f'(x)をx=2において評価した値は?
f(x)=x^3−3x^2+2の導関数はf'(x)=3x^2−6x。x=2を代入すると3×4−6×2=12−12=0。導関数が0になる点は接線が水平、つまり極大・極小候補点であることも重要な情報。定数項2は微分で消える点や、微分したのちの代入順序を逆にして混乱するミスが多いので、計算手順を一行ずつ書くと安全。また、係数が多項式の形であれば項別微分し加えるだけというルールを理解しておくと計算量が激減する。
Q4 : |2x−3|<5 を満たすxの範囲の長さは?
|2x−3|<5を外すと−5<2x−3<5。両辺に+3で−2<2x<8、次に両項を2で割り−1<x<4。区間の長さは4−(−1)=5。絶対値不等式は中心からの距離が上限未満という意味で、グラフ的に見ても左右に2.5広がった長さ5の開区間になる。境界を含まない点にも注意。区間長の計算では符号を落として|右端−左端|を取ると早い。不等式を連立形で書き直す練習をすると応用力が高まる。
Q5 : 2個の標準的なサイコロを同時に振ったとき、出た目の和が9になる確率は?
2個のサイコロの和が9になる組は(3,6)(4,5)(5,4)(6,3)の4通り。サイコロはそれぞれ6面で独立なので全事象は6×6=36。したがって確率は4/36=1/9。互いに区別しないと2通りと短絡的に減らす誤りに注意。サイコロ問題では「順序を区別するか」を必ず確認する習慣が有効。なお、和が10なら3通り、和が11なら2通り、和が12なら1通りと段階的に減るので図を描いて整理すると理解が深まる。
Q6 : 行列[[2,1],[5,3]]の行列式の値は?
2×2行列[[2,1],[5,3]]の行列式はad−bcの形で求める。具体的には2×3−1×5=6−5=1。値が1ということはこの行列は可逆で、逆行列の要素も整数になる利点がある。なお、掛ける順を誤り2×5−1×3=7や3と答えるミスが頻発するので、行列式の公式は左上×右下−右上×左下と位置で覚えると安定する。行列式が0でない限り逆行列が存在する点も合わせて復習しておきたい。
Q7 : 初項7、公差4の等差数列の第10項はいくつ?
等差数列の一般項はa_n=a_1+(n−1)dである。初項が7、公差が4、n=10を代入するとa_10=7+9×4=7+36=43。公式さえ覚えていれば暗算で済むレベルだが、途中でnとn−1を取り違えると初項との差が1つずれ、39や47などの誤値が出やすい。計算途中で式を逐一書き出すと安全。さらに和を問われる場合はn/2(2a_1+(n−1)d)を使うと良い。
Q8 : 6冊の異なる本から3冊を選び、順番に並べる方法は何通り?
順列は「並べる」問題であることが鍵。6冊から3冊を選び順序も考えるのでnPrを使う。6P3=6×5×4=120通り。組合せ6C3=20と混同しやすいが、並べるかどうかで公式が変わる。選択肢60は6×5÷など掛け算を1回減らした典型的なケアレスミス。順列公式はn!/(n−r)!と覚えておくと汎用的に使える。また、6×5×4×3=360のように「3冊を並べる」の意味を取り違え4冊並べてしまうと360が出る。手順を日本語で確認してから式を立てれば正確さが増す。
Q9 : 半径3cm、高さ5cmの円柱の体積は?
円柱の体積は底面積×高さで求める。底面は半径3の円だから面積はπ×3^2=9π。高さ5を掛けると45π。単位が立方センチメートルなら45πcm^3となる。他の選択肢は計算途中で半径と直径を取り違えたり、高さをかけ忘れた場合に出やすい値。定義通りに公式を当てはめれば迷わない。また、もし半径3を直径と誤読して半径1.5で計算すると底面積2.25πとなり、15πという誤りに至る。問題文の数値を写し間違えずに確認することが正解への近道である。
Q10 : 2次方程式 3x^2 - 12x + 9 = 0 の解のうち小さい方は?
方程式3x^2−12x+9=0を3で割るとx^2−4x+3=0。因数分解すると(x−1)(x−3)=0だから解はx=1,3。小さいほうは1である。数式を整理してから標準形にすることで因数分解の負担が減り、解とその大小関係が瞬時にわかる。なお解の公式を使っても同じ結果が得られるが、この程度の係数なら因数分解のほうが計算量が少なくミスも起こりにくい。加えて、二次方程式の解と係数の関係より、解の和は4、解の積は3となり、どちらも正なので小さい解が正の1であることも裏付けられる。
まとめ
いかがでしたか? 今回は簡単な数学クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は簡単な数学クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。