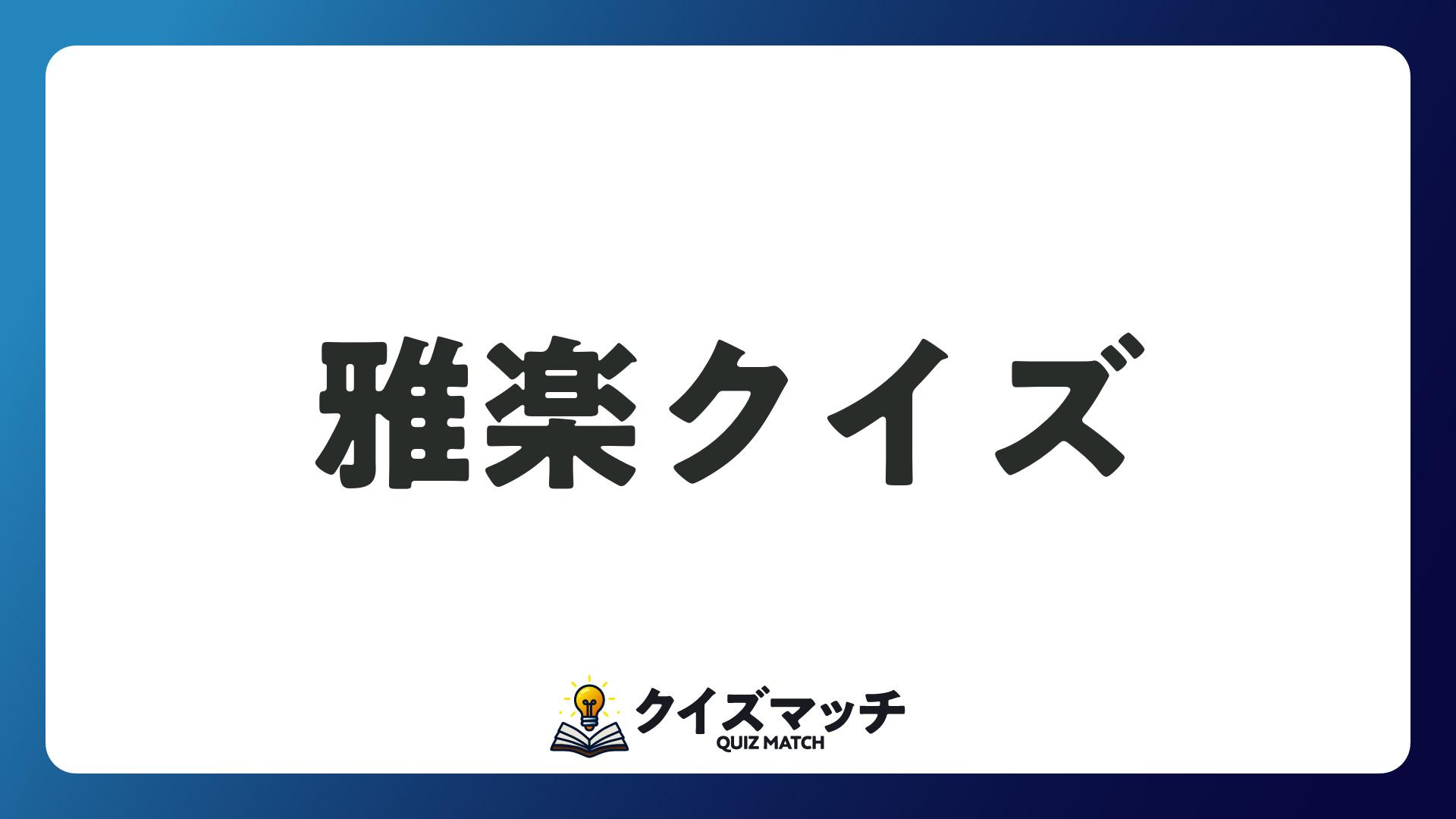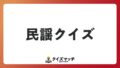雅楽は、日本古来の音楽と外来の音楽が融合して発展した伝統芸能です。平安時代に宮廷を中心に体系化された雅楽には、管楽器、弦楽器、打楽器といった様々な楽器が使われ、厳かで神秘的な響きを奏でます。本クイズでは、雅楽の楽器、舞踊、歴史的な背景など、雅楽の魅力に迫ります。雅楽という伝統芸能の奥深さを探るべく、10問のクイズにチャレンジしてみてください。
Q1 : 雅楽の歌物(声楽曲)で、和歌・漢詩を日本語や漢文で歌うものを何というか?
雅楽には器楽曲だけでなく、歌も含まれています。『朗詠(ろうえい)』は、和歌や漢詩を日本語あるいは漢文朗読で旋律化したものです。平安時代以降、貴族の間で詠まれ、華やかで雅な雰囲気を持った歌物です。催馬楽も歌物ですが、民謡を取り入れた伴奏曲です。
Q2 : 雅楽の成立や発展に最も深く関わった、現在も雅楽を伝承する宮内庁の部署は?
宮内庁の『宮中楽部(くないちょう がくぶ)』は、日本の雅楽の伝承と公式な演奏を担う専門部署です。長年にわたり、皇室行事や国事に雅楽を演奏してきた伝統ある組織です。現在も最古のオーケストラともされる伝統を維持しています。
Q3 : 雅楽の楽器で、和音を奏でることができる特徴的な楽器は?
笙(しょう)は金属製の簧(リード)を持ち、17本の竹管を同時に鳴らすことができるため、和音を奏でる独特の響きを持っています。これは世界的にも珍しい楽器であり、雅楽に独特の浮遊感や荘厳な雰囲気を与えます。
Q4 : 雅楽の曲名『越天楽(えてんらく)』は主にどの行事で演奏されることが多いか?
『越天楽』は、雅楽の代表的な器楽曲で、最も親しまれている曲のひとつです。特に新年や即位など慶事、祝賀の際に演奏されることが多いです。伝統的な宮中行事はもちろん、神社の祭りなどでも流されることがよくあります。
Q5 : 三管のうち、合奏の音頭を取るリーダー的役割を持つ楽器はどれ?
三管(笙・龍笛・篳篥)のうち、篳篥は旋律の核を担い、合奏の音頭をとる重要な役割があります。篳篥は音量が大きく、旋律を導くため、他の管楽器や楽器はこれに合わせて演奏するため、リーダーとなります。
Q6 : 雅楽における「舞楽」の分類で、左方の舞はどこの文化の影響を強く受けているか?
舞楽は『左方』と『右方』に大別されますが、『左方』の舞楽は中国・唐(とう)から伝わった舞を中心に構成されています。実際にはベトナムやインド、朝鮮由来の曲も含みますが、左方は赤、右方は朝鮮(高麗)に由来し青が用いられるのが特徴です。
Q7 : 雅楽が国家的に体系化された時代として正しいのはどれ?
雅楽は中国や朝鮮半島から伝来した音楽や舞楽が日本の文化に取り入れられ発展しました。特に平安時代に朝廷によって体系的に整えられ、宮中行事や祭礼に不可欠なものとなりました。現在伝わる多くの楽曲・制度もこの時代の整理に由来します。
Q8 : 雅楽の演奏構成で“三管”と呼ばれる楽器群はどれですか?
雅楽のオーケストレーションにおいて、主に旋律を担当する三大吹奏楽器が「三管(さんかん)」と呼ばれます。これは笙、龍笛、篳篥の3つで構成されています。それぞれ異なる音域と音色を持ち、雅楽合奏に不可欠な役割を担います。
Q9 : 雅楽で使用される楽器のうち、吹奏楽器に該当しないものは次のうちどれ?
雅楽の楽器には、吹奏楽器(管楽器)、弦楽器、打楽器があります。篳篥、笙、龍笛はいずれも息を吹いて音を出す吹奏楽器ですが、琵琶は弦をはじいて演奏する弦楽器です。琵琶は伴奏や旋律を担当し、管楽器とは異なる役割を持っています。
Q10 : 雅楽において日本固有の舞楽はどれですか?
雅楽には外来の音楽や舞楽が多いですが、日本固有のものも存在します。倭舞(やまとまい)は日本古来の舞とされ、他の選択肢である左方の舞や右方の舞、唐楽舞は中国や朝鮮半島由来の舞楽を取り入れたものです。倭舞は『大嘗祭』などの宮中行事でも演じられ、日本的な要素が強いのが特徴です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は雅楽クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は雅楽クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。