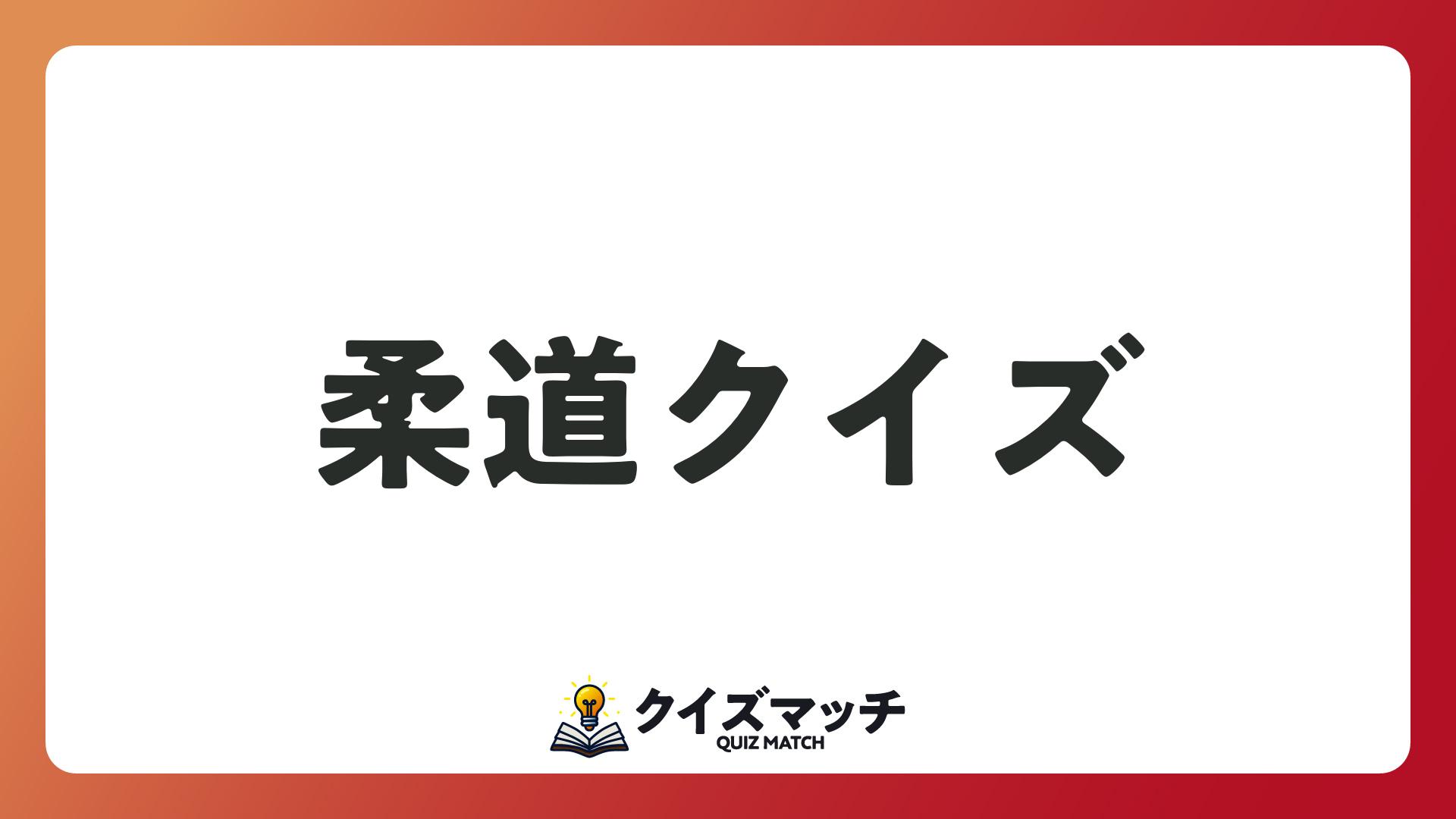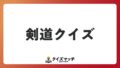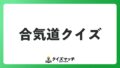柔道の知識を問うクイズにチャレンジしてみましょう。柔道は1882年に嘉納治五郎によって創始された伝統的な日本武道で、現在ではオリンピック競技としても知られています。この10問のクイズでは、柔道の起源やルール、特徴的な技など、柔道に関する基本的な知識を問います。柔道に詳しい方も、そうでない方も、ぜひこのクイズに挑戦してみてください。答えを見つけながら、柔道の魅力をさらに深く理解していきましょう。
Q1 : 世界で最初に柔道が五輪正式種目となった年は?
柔道が初めてオリンピックの正式種目に採用されたのは、1964年の東京オリンピックです。この大会で柔道は正式競技として加えられ、その後1972年のミュンヘン五輪以降は毎大会採用されています。1988年には女子の柔道が公開競技として追加されました。
Q2 : 柔道の「寝技」に含まれないものはどれ?
柔道の「寝技」とは、床に倒れた状態で行う技術で、抑え込み技、関節技、絞め技などが含まれます。一方、足払いは立ち技(投げ技)の一種で、寝技に含まれません。したがって「足払い」は寝技に該当しません。
Q3 : 柔道の帯の色で、最も高い段位を示す色はどれか?
柔道の段位制度において、最も高い段位(主に6段以上)は、紅白帯または赤帯が使用されます。黒帯は主に初段以上から五段までです。それ以下は白、黄、緑、青、紫などの色帯が使われます。紅白帯や赤帯は特別な高段者のみが締めることを許されています。
Q4 : 国際柔道連盟(IJF)の本部があるのはどこでしょう?
国際柔道連盟(IJF:International Judo Federation)の本部はスイスのローザンヌにあります。ローザンヌは、多くの国際スポーツ連盟が集まる都市として有名です。柔道は日本発祥の競技ですが、世界的な運営は国際連盟が担っています。
Q5 : 柔道において、畳の端に出るとどうなりますか?
柔道では、選手が試合範囲外に出ると「場外」となり、審判が「待て」を宣告して試合を一時中断します。場外に出ただけで自動的に負けにはなりませんが、意図的に場外へ出る行為は反則とみなされ「指導」が与えられることがあります。
Q6 : 柔道着(道着)の正式な色は何色でしょう?(国際大会の主な色)
柔道の国際大会では、主に白色と青色の柔道着(道着)が使用されます。これにより選手の区別がしやすくなり、判定や観戦の際の混乱を防ぎます。かつては白のみでしたが、2000年のシドニー五輪から青も採用されました。赤と黒、緑と黄、白と黒は柔道着の公式な色ではありません。
Q7 : 「袖釣込腰」はどの分類の技に含まれるでしょう?
「袖釣込腰(そでつりこみごし)」は、柔道の投げ技に分類されます。「投げ技」は、相手を畳に投げ倒すことで得点を狙う技の総称です。袖釣込腰は、相手の袖を引きつけ、腰を使って投げる技のひとつです。抑え込み技、関節技、絞め技は分類が異なります。
Q8 : 柔道の試合場は一般的にどのような形状でしょう?
柔道の試合場は一般的に正方形です。国際大会では、試合場の寸法は8メートル四方(国際規格は8メートル×8メートルから10メートル×10メートルの間)で、その外側に安全地帯が設けられています。正方形なのは試合の公正性や選手の安全性を確保するためです。
Q9 : 柔道において「一本」が与えられる主な条件はどれか?
「一本」とは、柔道における最高得点です。主に、投げ技が正しく決まって相手の背中を畳にしっかりつけて倒したときや、抑え込み25秒、相手の関節や絞め技によるギブアップなどの場合に与えられ、試合はその時点で終了します。他の選択肢はいずれも一本の条件にはなりません。
Q10 : 柔道の創始者は誰でしょう?
柔道の創始者は嘉納治五郎(かなう じごろう)です。1860年に生まれた嘉納治五郎は、柔術諸流派の技法を整理・改良し、1882年に「講道館柔道」を設立しました。以降、柔道は国内外に広まり、現在ではオリンピック競技にもなっています。武田惣角は大東流合気柔術、植芝盛平は合気道、千葉周作は剣術で知られています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は柔道クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は柔道クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。