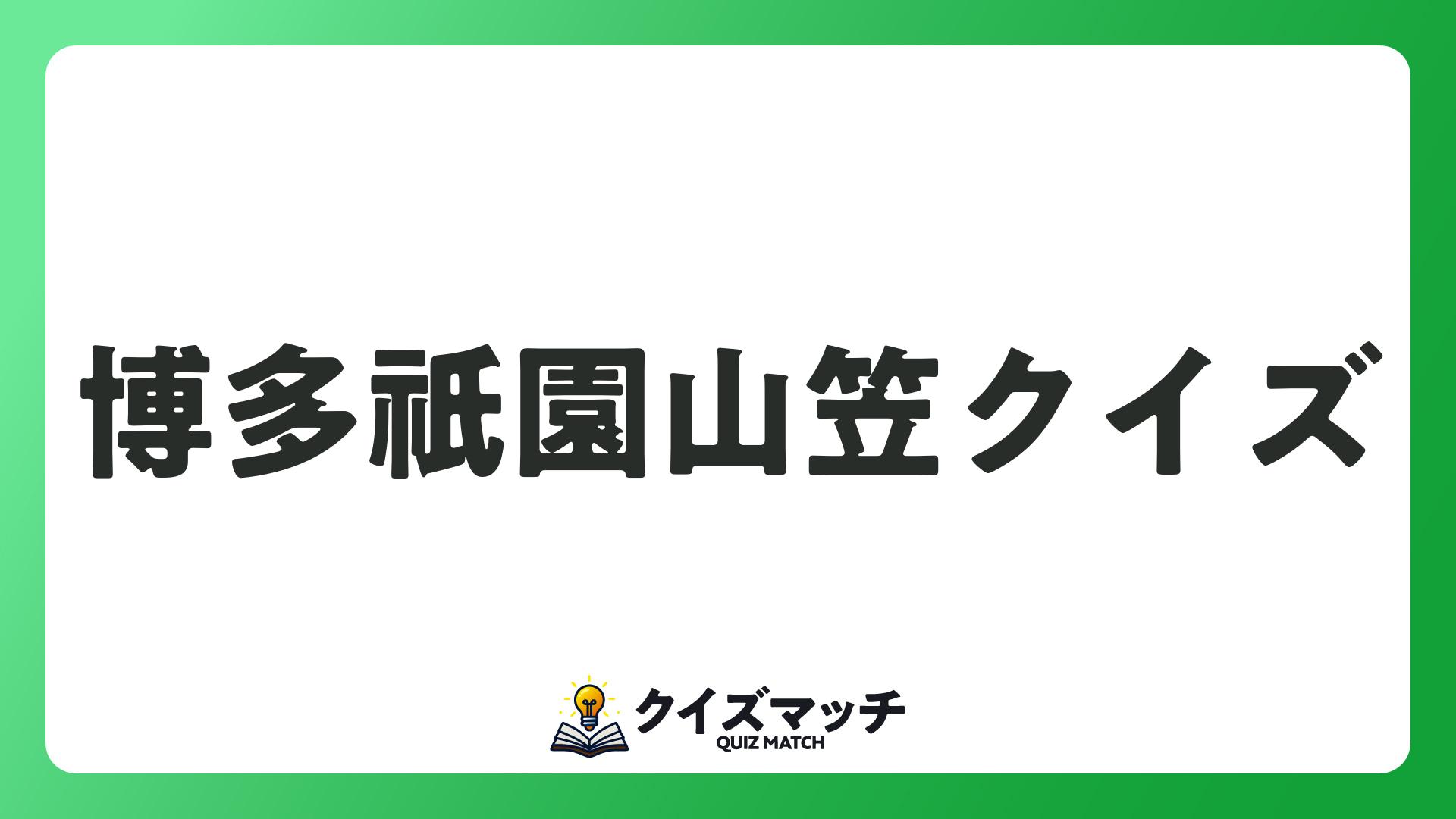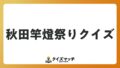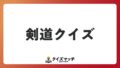博多祇園山笠は、福岡市博多区を中心とした夏の風物詩です。7月1日から15日まで開催され、クライマックスの「追い山笠」は7月15日の早朝に行われます。この祭りには長い歴史があり、鎌倉時代に始まったと言われています。山笠を担ぐ白装束の担ぎ手たちの姿は、祭りの代名詞とも言えるでしょう。この記事では、博多祇園山笠についての10の基本的な問題を紹介します。祭りの歴史や特徴、そして山笠にまつわる伝統について理解を深めていただければと思います。
Q1 : 博多祇園山笠の担ぎ手が履く独特な履き物の名前は何でしょう?
担ぎ手が履くのは「足袋草履」と呼ばれる、足袋と草履が一体化した履物です。滑りにくく、祭りの際に激しく走ったり曲がったりする際にも足元を守る役割があります。祭りの衣装に欠かせない伝統的な履き物です。
Q2 : 博多祇園山笠が2016年に登録されたユネスコの無形文化遺産はどのカテゴリーでしょう?
博多祇園山笠は2016年に「山・鉾・屋台行事」としてユネスコ無形文化遺産に登録されました。これは日本全国の同様の祭りとともに登録されたもので、地域固有の伝統と祭礼の重要性が認められた結果です。
Q3 : 山笠の掛け声として有名なものはどれでしょう?
山笠の掛け声として最も有名なのが「オイサ」です。担ぎ手たちは「オイサ!オイサ!」と声を揃えながら町を駆け抜けます。この掛け声は団結の象徴であり、一体感を生み出す重要な要素です。
Q4 : 現在の博多祇園山笠で「飾り山笠」と区別される、実際に担いで走る山笠の名前は何でしょう?
「舁き山笠」は実際に担いで走るための山笠で、内装や人形の高さなども制限されています。それに対して「飾り山笠」は観賞用で、華麗な人形飾りや高さ10m以上にもなる装飾が特徴ですが、担がれて走ることはありません。
Q5 : 博多祇園山笠で町ごとに組織される担ぎ手の集団を何と呼ぶでしょう?
博多祇園山笠では博多区のいくつかの地区ごとに「流(ながれ)」と呼ばれる集団に分かれます。流ごとに山笠を持ち、祭りに参加します。それぞれの流には歴史や伝統が根付いており、流の競い合いも見どころの一つです。
Q6 : 博多祇園山笠の最大の見どころでもある「追い山」は、どの神社の前からスタートしますか?
「追い山」は博多祇園山笠のフィナーレを飾る行事で、櫛田神社の前からスタートします。櫛田神社は山笠の総鎮守として祭りの中心となる神社であり、「櫛田入り」や「祝いめでた」とともに多くの人々が熱狂する瞬間です。
Q7 : 山笠の担ぎ手の衣装として有名な白い腰帯は何と呼ばれるでしょう?
山笠の担ぎ手が身に着ける白い帯は「サラシ」と呼ばれます。サラシは丈夫な布で、身体を保護しながら動きやすさも確保する役割があります。祭りの際はこのサラシ姿で町を疾走する姿が博多の夏の風物詩となっています。
Q8 : 博多祇園山笠の起源はどの時代と言われているでしょうか?
博多祇園山笠の起源は鎌倉時代(1241年)までさかのぼるとされています。博多に疫病が流行した際、承天寺の開祖・聖一国師が施餓鬼棚に乗って町を廻り、疫病除けの祈祷を行ったことが始まりと伝えられています。鎌倉時代から続く歴史ある祭りです。
Q9 : 「追い山笠」で使われる山笠の重さはおよそ何トンでしょうか?
追い山笠で使われる舁き山笠は、装飾や構造にもよりますが、約1トンから2トン程度になると言われています。多くの男性たちが力を合わせて担ぎ、街中を駆け抜ける様子は非常に迫力があります。2トンもの山笠を担ぐのは伝統と団結の象徴です。
Q10 : 博多祇園山笠の開催期間は毎年何月に行われるでしょうか?
博多祇園山笠は毎年7月1日から7月15日まで福岡市博多区を中心として開催される伝統的な祭りです。クライマックスとなる「追い山笠」は毎年7月15日の早朝に行われ、多くの見物客が訪れます。「7月」は、この祭りの全行程を通じて重要な月です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は博多祇園山笠クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は博多祇園山笠クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。