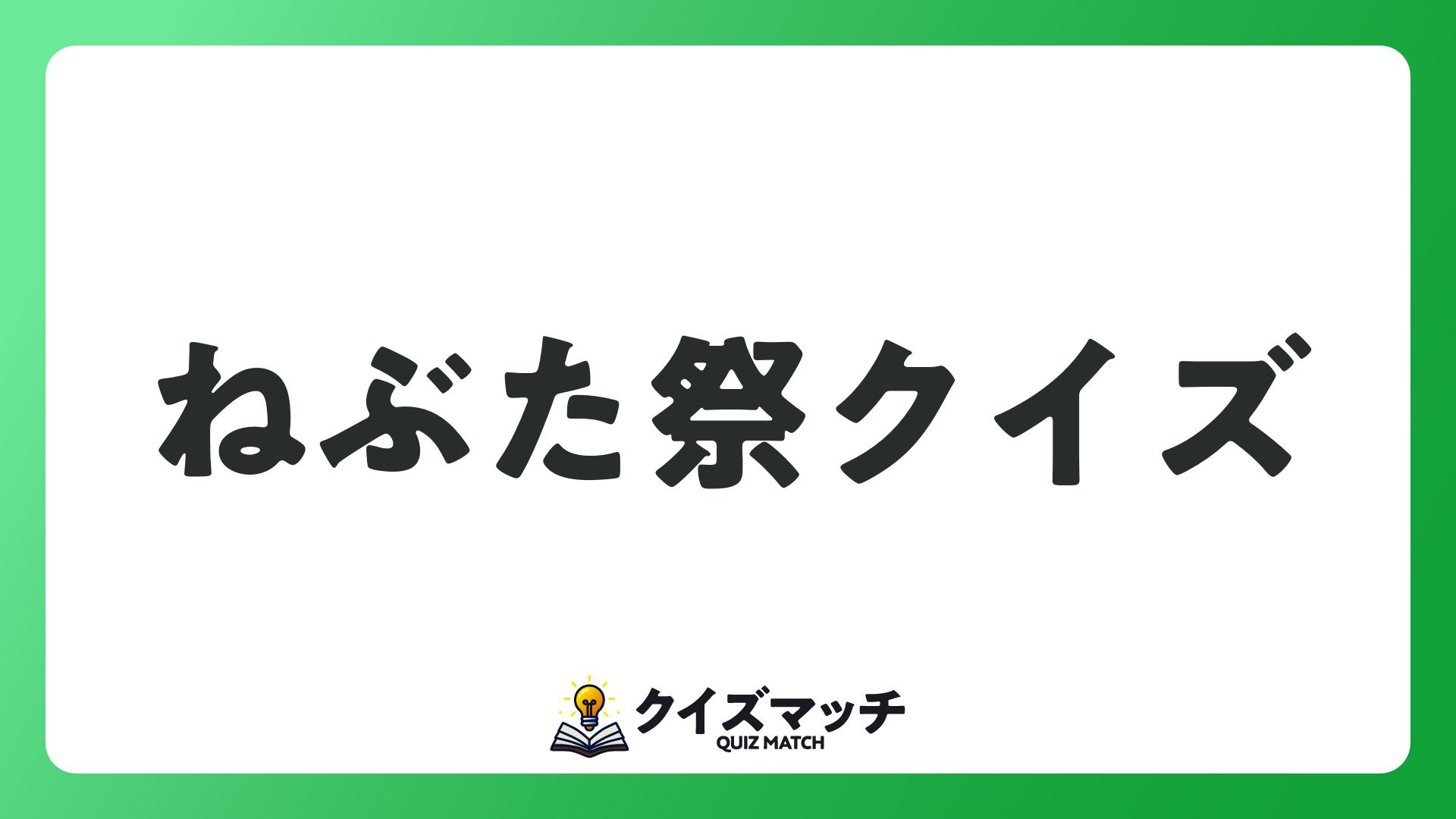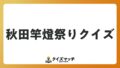夏の青森を彩る伝統行事「ねぶた祭」。毎年8月上旬に開催され、巨大な灯籠「ねぶた」が練り歩く様子は圧巻です。ねぶた祭の歴史や文化、特徴について知る機会としてこのクイズを楽しんでいただければ幸いです。
Q1 : ねぶた祭の主催団体はどれですか?
ねぶた祭の主催は「青森ねぶた祭実行委員会」となっています。実行委員会は地域の自治体や経済団体、企業、ボランティアなどが協力して組織しており、毎年安全かつ円滑な運営ができるよう取り組みが行われています。他の選択肢は祭りには関わりますが主催ではありません。
Q2 : ねぶた祭の巨大ねぶたの製作期間として一般的なのはどれですか?
ねぶたの制作は、通常3~4カ月かかります。設計、骨組み作り、絵付けや紙貼り、電気配線など多くの工程が必要で、大型なねぶたになると数十人のチームで分担して作り上げます。短期間で完成するものではありません。この長い準備の積み重ねが祭り当日の美しさへとつながります。
Q3 : ねぶた祭はユネスコの無形文化遺産に登録されていますか?
2024年現在、青森ねぶた祭そのものはユネスコの無形文化遺産には登録されていません。ただし、2016年には「山・鉾・屋台行事」として日本各地の祭礼がまとめて登録されていますが、青森ねぶた祭はこれに含まれていません。将来的な登録が期待されています。
Q4 : ねぶた祭の中で演奏される楽器に含まれるものはどれですか?
ねぶた祭の囃子では「太鼓」が重要な役割を持ちます。迫力ある太鼓のリズムが会場全体を盛り上げます。他にも笛や手振り鉦(かね)なども使われますが、三味線やギター、ピアノなどは伝統的なねぶた囃子には使用されません。
Q5 : ねぶた祭の起源とされる風習はどれですか?
ねぶた祭の起源のひとつとされるのは「精霊送り」(眠り流し)です。お盆を控え、眠気や邪気を川や海に流し去ることで清めるという意味があります。その名残が巨大な灯籠になったとされています。人形流しや盆踊りも地域によっては似た行事ですが、ねぶたの直接の由来は精霊送りとされます。
Q6 : ねぶた祭の開催時期として正しいのはどれですか?
ねぶた祭の開催は毎年8月2日~7日です。夏休み真っ盛りの時期で、青森市内は全国各地からの観光客で賑わいます。7月中旬や9月下旬ではなく、8月上旬に行われるのが正解です。この時期ならではの活気と熱気が魅力です。
Q7 : ねぶた祭りの踊り手を何と呼びますか?
ねぶたの周りを跳ねて踊る参加者は「ハネト」と呼ばれます。ハネトは「ラッセラー、ラッセラー」という掛け声とともに勇壮に飛び跳ね、音と熱気で祭りを盛り上げます。特定の衣装や規則を守れば、誰でも当日参加できるのも特徴です。ねぶた師はねぶたを作る職人の名称です。
Q8 : ねぶた祭の最終日に行われる伝統的なイベントはどれですか?
ねぶた祭の最終日には「ねぶたの海上運行」が行われます。海上運行では大型ねぶたが船に積まれ、青森港を巡り幻想的な光景を演出します。同時に花火大会も開催され、祭りのフィナーレを華やかに飾ります。他の選択肢は実際のねぶた祭には存在しないイベントです。
Q9 : ねぶた祭で曳かれる「ねぶた」とはどのようなものですか?
ねぶた祭で曳かれる「ねぶた」は、主に竹や針金の骨組みに和紙を貼り、色鮮やかな絵付けと内部の電飾で彩られた大型の人形灯籠です。歴史上の人物や神話、歌舞伎の名場面をモチーフとすることが多く、その美しさと迫力は祭りの大きな魅力になっています。他の選択肢に挙げられているものは別な祭りの特徴です。
Q10 : ねぶた祭が毎年開催される都市はどこですか?
ねぶた祭は青森県青森市で毎年開催されます。青森市の夏の風物詩で、全国的にも有名な祭りです。巨大な灯籠「ねぶた」が市内を練り歩く様子は圧巻で、多くの観光客が訪れます。秋田市では竿燈まつり、弘前市と盛岡市も別の祭りが有名ですが、ねぶた祭は青森市のみで正式に開催されています。
まとめ
いかがでしたか? 今回はねぶた祭クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はねぶた祭クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。