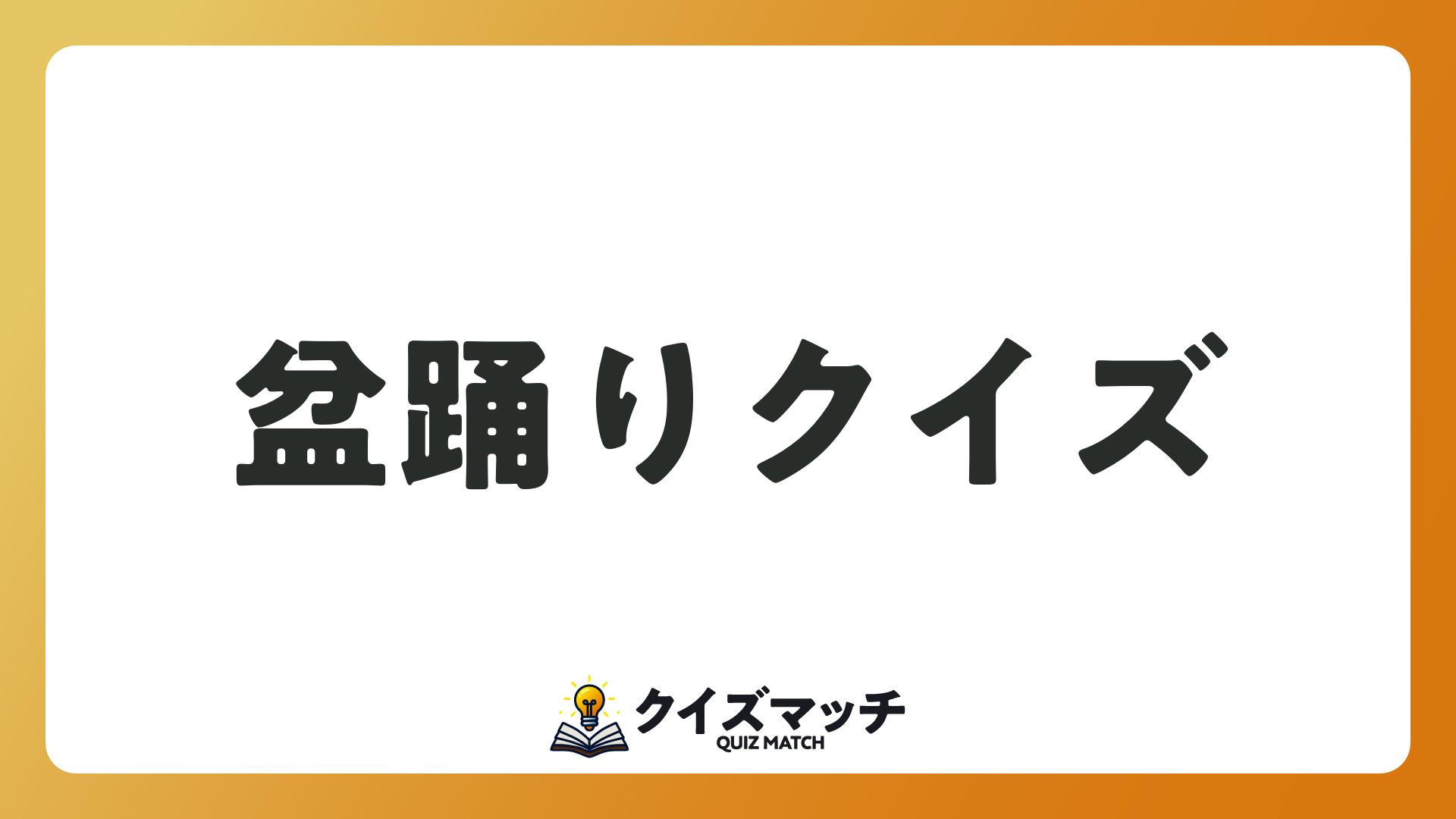日本の夏の風物詩といえば盆踊り。その歴史や特徴、地域性について、10問のクイズを用意しました。「江州音頭」の発祥地は?盆踊りの基本動作は?「東京音頭」に登場する夏の風物詩は?北海道の盆踊りと深い関係にある産業は?など、盆踊りに関する様々な知識を問います。伝統的な日本の夏の風物詩である盆踊りの魅力を再発見できる内容になっています。
Q1 : 盆踊りの起源について正しい説明はどれですか?
盆踊りの起源は仏教行事の盂蘭盆会です。死者の供養として始まり、仏教が日本に伝来した後、各地で民俗的色彩と結びついて現在の形になりました。明治以降の学校教育や欧米文化の影響ではありません。神道行事とも異なります。
Q2 : 岩手県で有名な踊りで、太鼓を打ちながら踊る盆踊りを何と呼ぶか?
岩手県の『さんさ踊り』は、太鼓を打ちながら歌と踊りを合わせて進行します。女性が華やかな衣装で太鼓を打つ姿が印象的で、日本三大盆踊りや日本三大民謡踊りのひとつにも数えられています。
Q3 : 江戸時代の盆踊りが盛んだった理由に関して正しいものはどれか?
江戸時代、盆踊りは農民や町人たちにとって年に一度の大きな娯楽と交流の機会でした。仏教的な祖霊供養の意味も強く、さらに社会的な交流や結婚の出会いの場としても親しまれていました。
Q4 : 阿波踊りで有名な徳島県で、踊り手が着用している特徴的な被り物は?
阿波踊りの女性踊り手が被る笠(すげがさ)は、円錐形の独特な形状で装飾もされています。男性は鉢巻きが多いですが、阿波踊りの象徴といえばこのすげがさです。涼しさと美しさを兼ね備えています。
Q5 : 盆踊りの行事が日本全国で多く行われる時期はいつですか?
盆踊りは日本の伝統的な仏教行事であるお盆に合わせて開催されるため、一般的に7月または8月が中心です。地域によって異なりますが、ご先祖様の霊を迎え供養する盆の季節に全国で開催されます。
Q6 : 盆踊りの際、中央に設置される櫓(やぐら)の目的として最も当てはまるものは?
盆踊りの中央に立てられるやぐらは、太鼓や音頭取りが上がって演奏や歌をリードする役割があります。踊り手がその周囲を回るように踊ることで一体感を生み、音の中心として機能します。観覧席や供物台として用いる例は通常ありません。
Q7 : 北海道の代表的な盆踊りである『北海盆唄』に関係が深い産業は?
『北海盆唄』は北海道で有名な盆踊りの歌で、もともとはニシン漁の労働歌『ソーラン節』が原型となっています。北海道の漁業が大きく関わっているため、盆踊りの振り付けにも網を引く動作が取り入れられています。
Q8 : 『東京音頭』の歌詞に含まれる夏の風物詩は何でしょう?
『東京音頭』は1920年代に作られた曲で、盆踊り用として非常に有名です。歌詞には“花火”が登場し、夏の風物詩として情景を彩っています。金魚や風鈴も夏を代表しますが、オリジナルの歌詞には“花火”がはっきりと描かれています。
Q9 : 盆踊りの踊り方で、よく見られる典型的な動きとして正しいものはどれでしょう?
多くの盆踊りの踊り方では、手を左右に振ったり、円を描きながら歩いたりする基本動作が多いです。ジャンプや頭上で叩く動作は一部地域のアレンジですが、最も一般的な型は手を上下や左右に軽く振るパターンです。これは老若男女誰でも踊れるよう工夫されています。
Q10 : 日本の伝統的な盆踊りで有名な『江州音頭』の発祥地はどこでしょう?
『江州音頭』は滋賀県が発祥の地とされており、江戸時代から伝わる盆踊りの歌と踊りです。江州とは現在の滋賀県の旧国名で、多くの盆踊りが地域色豊かに発展しました。関西地域のみならず、全国へ広まることで今では多くの場所で親しまれています。大阪府とも縁が深いですが、元は滋賀県発祥とされています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は盆踊りクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は盆踊りクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。