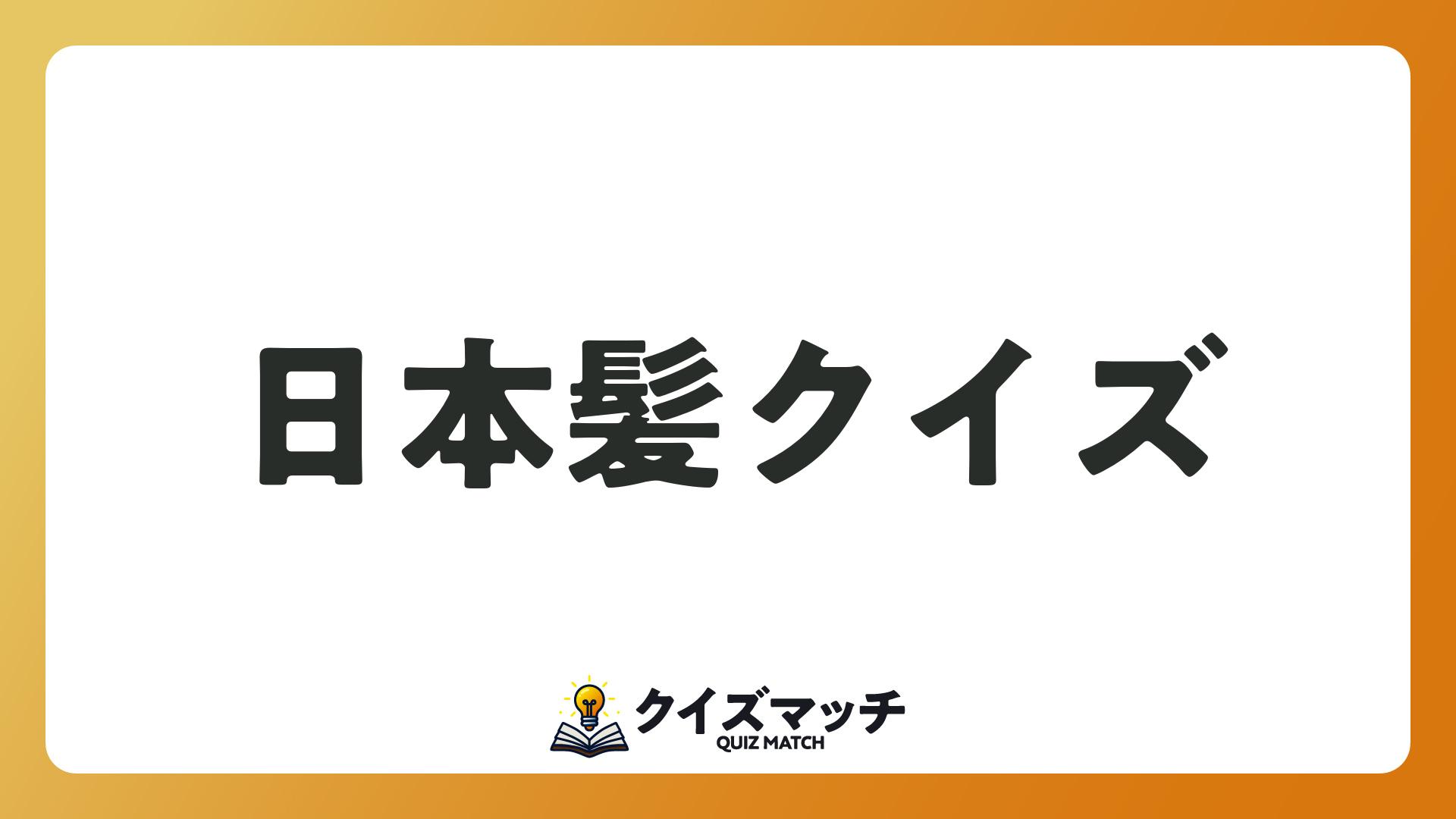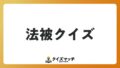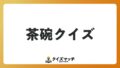日本の伝統文化の粋である日本髪には、江戸時代から受け継がれてきた多様な髪型が存在します。今回のクイズでは、町娘の人気スタイルから公家の格式ある髪型まで、日本髪の代表的な髪形について紹介します。髪の飾りや由来など、日本の歴史や習慣に深く関わる日本髪の知識を楽しく学べる内容となっています。日本の美意識が息づく日本髪の世界をぜひ探検してみてください。
Q1 : 結婚式で着る和装時に花嫁が髪型に挿す大きな白い飾りは何と呼ばれる?
角隠しは、和装の花嫁が頭にかぶる大きな布状の飾りで、髪型を隠すようにセットします。魔除けや謙遜の意味も込められ、文金高島田などの日本髪とともに使われます。
Q2 : 江戸時代の日本髪で、前髪を下ろして顔を丸く見せるためのスタイルは何と呼ばれる?
お鬢下しは、前髪を下ろし、両側の鬢(もみあげ部分)も顔に沿って下ろすことで顔の輪郭を丸く柔らかく見せる伝統的な髪型のテクニックです。
Q3 : 元々、島田髷という髪型が生まれたとされる地名はどこ?
島田髷は静岡県島田市が発祥と伝えられています。江戸時代初期に「島田の宿」の遊女が工夫した髪型が広まり、全国の女性に広く親しまれるようになりました。
Q4 : おすべらかしという髪型は、どのような人々が主に結っていた髪型ですか?
おすべらかしは主に宮中や公家の女性が結っていた格調高い日本髪です。後頭部に大きな線を作る独特のスタイルで、現代では皇室の儀式などでも用いられます。
Q5 : 芸者や舞妓が主に結う「割れしのぶ」はどの年代の女性の髪型?
割れしのぶは主に舞妓や若い未婚女性が結う日本髪で、真ん中が割れてしのぶ草がかたどられているのが特徴です。舞妓さんの代表的な髪型として知られています。
Q6 : 日本髪で髪留めや飾りとして使われる”かんざし”は英語で何と呼ばれる?
かんざしは英語で”Ornamental hairpin”と呼ばれます。棒状や櫛状で装飾が施されたものも多く、日本髪の装いを華やかにする伝統的な髪飾りです。
Q7 : 江戸時代に浮世絵などで人気となった、既婚女性が結った日本髪の髪型は?
丸髷は日本髪の中でも主に既婚女性が結う髪型で、江戸時代の浮世絵などにもよく登場します。既婚のしるしとして親しまれ、現代でも一部の儀式や行事で見ることができます。
Q8 : 文金高島田は日本髪の一種ですが、どのような場で特によく使用されていますか?
文金高島田は日本の伝統的な花嫁髪型であり、現代でも結婚式の和装でよく使用されます。華やかな髪飾りとともに、着物に映える格式ある髪型として親しまれています。
Q9 : 日本髪を結う際、髪をまとめるために多く使われる伝統的な油は何?
日本髪を結うときに伝統的に使われる油は椿油です。椿油は保湿性が高く、髪につやを与え、まとまりやすくしてくれるため、昔から使われてきました。特有のしっとりとした質感は日本髪の美しさを引き立てます。
Q10 : 江戸時代の町娘によく結われていた日本髪の代表的な髪型はどれ?
島田髷は江戸時代の町娘や若い女性の間で特に人気があった日本髪の一種です。年頃の若い女性が結う髪型として多く描かれ、のちに花嫁髪型の文金高島田へと発展しました。丸髷は既婚女性、銀杏返しは芸者や舞妓に多い髪型です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は日本髪クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は日本髪クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。