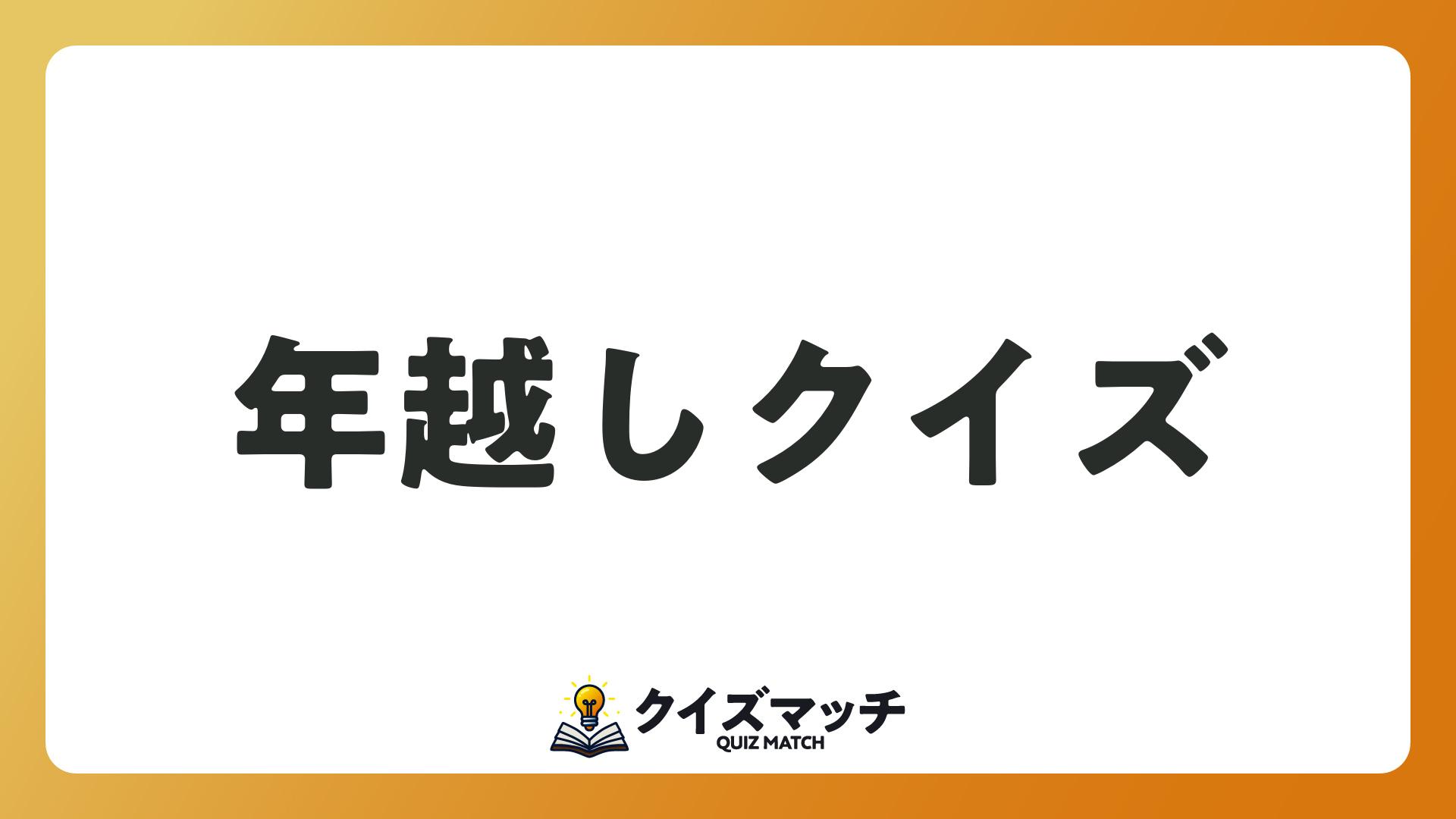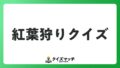新年を祝う年越しの風習には、さまざまな由来や意味が込められています。この記事では、NHKの人気番組や正月料理、初夢など、正月ならではのクイズを10問ご用意しました。年末年始のお楽しみを存分に味わえる内容となっています。日本の伝統的な習慣や文化の背景にある意味を知り、新年を心から祝福することができるでしょう。どうぞお楽しみください。
Q1 : お年玉を渡す際によく使用される小さな袋の名前は?
お年玉をわたす際の小さな封筒は「ポチ袋」と呼びます。「ポチ」とは関西弁で「少し」という意味があり、心をこめて贈る気持ちが込められています。彩り豊かでかわいいデザインのものが毎年出回り、子どもたちにとって正月の楽しみのひとつです。
Q2 : おみくじで最も運勢が良いとされるのは?
おみくじで最も運勢が良いのは「大吉」です。「吉」「中吉」「小吉」などと種類がありますが、神社や寺によっては「大大吉」など特別なものも存在します。一般的には「大吉」は何事も順調に運び、願いが叶うとされるため、新年に引けると一年の良いスタートがきれると喜ばれています。
Q3 : 日本の大晦日に縁起が悪いとされる行動は?
大晦日にお金を借りることは「一年中お金に困る」という縁起の悪い行動と考えられています。掃除やそば、初詣は吉とされていますが、大晦日や正月前後は「借金」や「貸し借り」などを避ける風習が日本各地に今も残っています。
Q4 : 関西地方で大晦日の夜に食べる習慣がある、にしんが入ったそばの名称は?
関西地方、特に京都で大晦日に食べる伝統的なそばが「にしんそば」です。甘辛く煮た身欠きにしんをそばの上にのせて提供します。江戸時代末期に京都で生まれた料理といわれ、縁起物として年越しの定番メニューになっています。
Q5 : 新年最初の夢「初夢」に見ると縁起が良いとされるものの最初は?
「一富士、二鷹、三なすび」という言い回しがある通り、初夢で最も縁起が良いとされるのは「富士山」です。由来には諸説ありますが、最も高い山=目標の高さ・運気上昇を意味し、ほかにも「鷹=強いもの」「なすび=成す(成し遂げる)」となぞらえられています。
Q6 : おせち料理の中で「数の子」が象徴するものは?
おせち料理の「数の子」は、その卵の数が多いことから子孫繁栄を象徴しています。ニシンの卵であり、家庭が代々繁栄し、子孫がたくさん増えることを願って正月に食べられます。他にも、栗きんとんは金運、黒豆は健康を象徴しています。
Q7 : 正月飾りのひとつ「門松」は、一般的に何の植物で作られる?
門松は主に松と竹で作ります。松は「不老長寿」「永遠」を、竹は「成長」「繁栄」などの願いを込めており、神様の依り代として家の門口に飾り、新年の福を呼び込むとされています。地域によって多少の違いはあるものの、門松の基本は松と竹です。
Q8 : 除夜の鐘は通常何回撞かれる?
除夜の鐘は、一年の煩悩の数とされる「108回」撞かれるのが習わしです。この‘108’には仏教での煩悩の数という意味があり、108の煩悩を払い清めて新しい年を迎えるという願いが込められています。除夜の鐘は全国の寺院で聞くことができます。
Q9 : 大晦日に放送されるNHKの人気音楽番組は次のうちどれ?
NHK紅白歌合戦は、1945年に始まった国民的人気音楽番組で、毎年大晦日に生放送され、紅(女性または女性グループ)・白(男性または男性グループ)の2チームが歌自慢を競います。家族で年越しを迎える定番の行事として定着し、多くの視聴率を毎年記録しています。
Q10 : 日本で年越しそばを食べる風習の由来とされることはどれ?
年越しそばは、細く長く伸びるそばの形から「長寿」を願う意味が込められています。また、切れやすいことから、「今年一年の厄災を断ち切り、新しい年を迎える」という意味ももたせていますが、最も代表的なのは「長寿祈願」です。年末の風物詩として広く定着しており、そのルーツは江戸時代にさかのぼります。
まとめ
いかがでしたか? 今回は年越しクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は年越しクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。