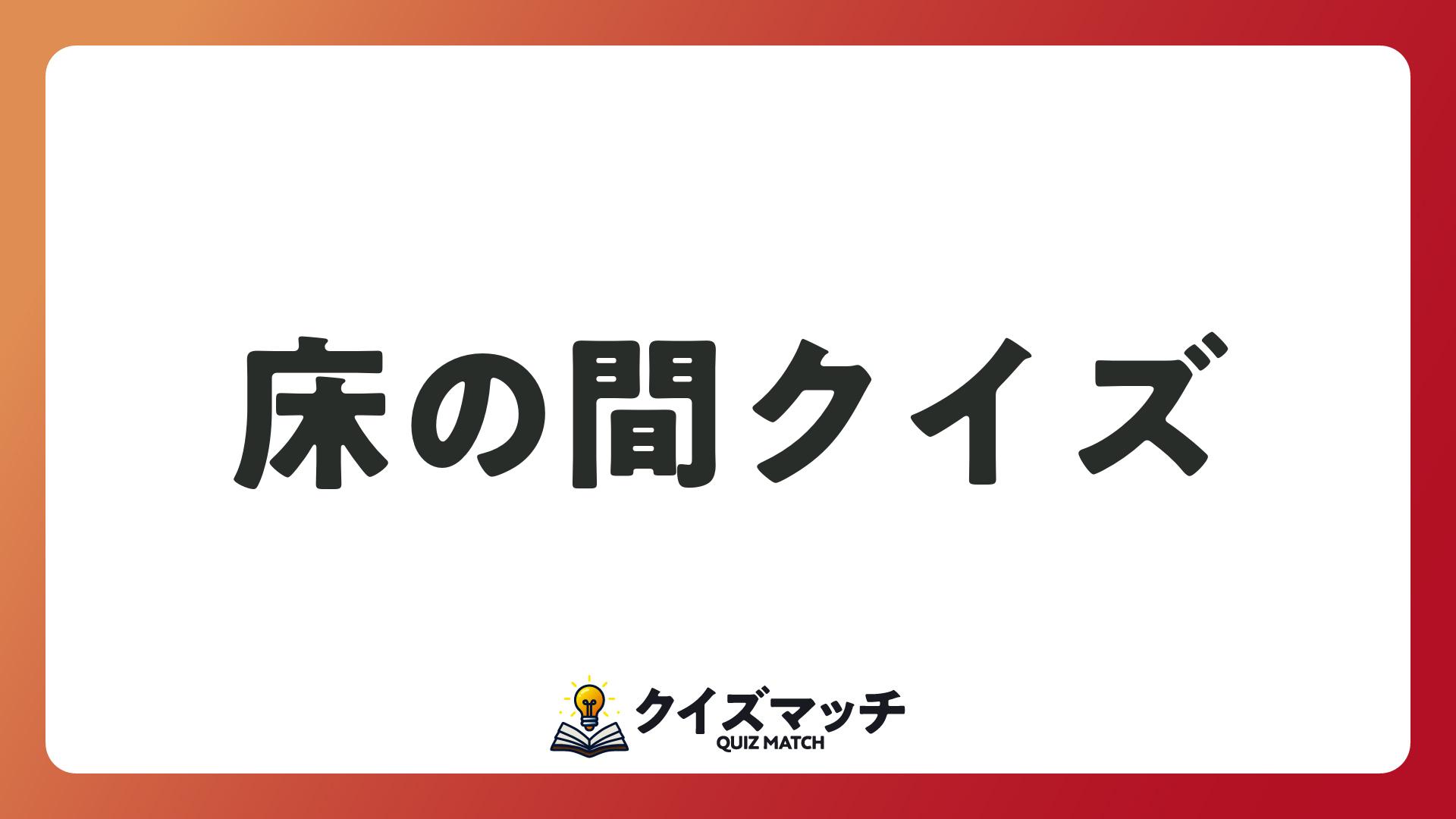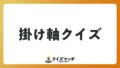日本の伝統的な和室には、必ずといっていいほど「床の間」が設けられています。この床の間は、様々な装飾を飾り付けることで、季節感や主の趣味を表現し、来客を意識した格式ある空間となります。今回のクイズでは、そんな床の間の歴史や意匠、正しい使い方などについて、10問にわたって深く掘り下げていきます。床の間の知識を深めて、日本の伝統美を堪能してみてはいかがでしょうか。
Q1 : 現代住宅の床の間利用として最も一般的なものはどれでしょう?
現代では伝統的な床の間を活かしたまま、飾り棚や収納として再利用する事例が増えています。和室が少なくなった住宅事情もあり、床の間本来の装飾空間としてではなく実用的な使い方にアレンジされることが多く、寝具やキッチン、洗面用にはあまり使われません。
Q2 : 床の間の天井の意匠で、最も格式が高いとされるものは何と呼ばれますか?
床の間の天井意匠には複数の種類がありますが、中でも格式が高いのが「折上げ天井」です。天井面が中央部で一段上がり、精巧な木組みや装飾が使われます。書院造や武家屋敷、寺社建築など、重厚で高級な空間によく見られる技法です。
Q3 : 床の間に仏壇や神棚を置くのは一般的に正しいですか?
床の間に仏壇や神棚を置くことは、一般的には行われません。床の間は装飾やもてなしの空間です。仏壇は仏間、神棚は神棚専用の位置に設けるのが伝統的な作法です。両者を一緒にするのは宗教的な意味合いからも避けられています。
Q4 : 床の間に飾る掛軸や花の置き方として正しいのはどれですか?
日本の美意識において、床の間の設えは非対称を基本としています。「間」を意識した空間の美しさが重視され、花や置物、掛軸は左右対称にはせず、適度な余白とバランスを楽しみます。西洋のように中央や隅に揃えるのは一般的ではありません。
Q5 : 床の間のある和室は、どの時代に広く普及しましたか?
床の間は室町時代に成立した書院造が起源で、その後武家や公家の住宅に普及し、格式ある和室に不可欠な空間となりました。奈良時代はまだ存在せず、江戸時代以降に町屋など庶民にも広まりましたが、起源と普及の契機は室町時代です。
Q6 : 床の間に生ける花として伝統的に向かないものはどれ?
床の間には自然の花や枝もの、生け花を飾るのが礼儀です。造花は人工的なものであり、日本の伝統や床の間の“生”を尊ぶ精神にふさわしくありません。季節感や自然の美しさを大切にすることが和室の設えの基本とされています。
Q7 : 床の間の「上座」は、通常どこに位置していますか?
床の間の間近は部屋の「上座」とされ、来客への最上級の礼儀と尊敬を示す場所です。正式な訪問時には、主客が床の間の前に案内されるのが通例です。入口近くや部屋の中央、仏壇の隣など他の場所は伝統的な上座の考え方にはあたりません。
Q8 : 床の間の床を特に指す「床板(とこいた)」として、一般にどんな材が使われることが多いでしょう?
床の間の床板(とこいた)は、和室の中でも特に格の高い場所とされ、美しい木目や香りが特徴の檜(ヒノキ)がよく使われます。杉や松も日本の建材として知られていますが、床の間の格式を考えると檜が最も適した材料とされています。
Q9 : 床の間に掛けるものとして最も一般的なのはどれでしょう?
床の間には仏画や書、山水画などが描かれた掛軸を飾るのが通例です。これに他の季節の設えとして一輪挿しや置物などを添えます。障子や屏風などは部屋を仕切るためのもの、畳は床材として使われるもので、床の間特有の装飾としては掛軸が最も一般的です。
Q10 : 床の間は日本の伝統的な部屋において、主に何のために設けられた空間でしょうか?
床の間は日本の伝統的な和室に設けられる、客をもてなす装飾的な空間です。絵画(掛軸)や花(生け花)、置物などを飾り、季節感や主の趣味を表現します。床の間は格式の象徴的存在であり、正式な場でも重視され、部屋の最も上座に位置します。寝床や食事場所、物置とは本来の用途が異なります。
まとめ
いかがでしたか? 今回は床の間クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は床の間クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。