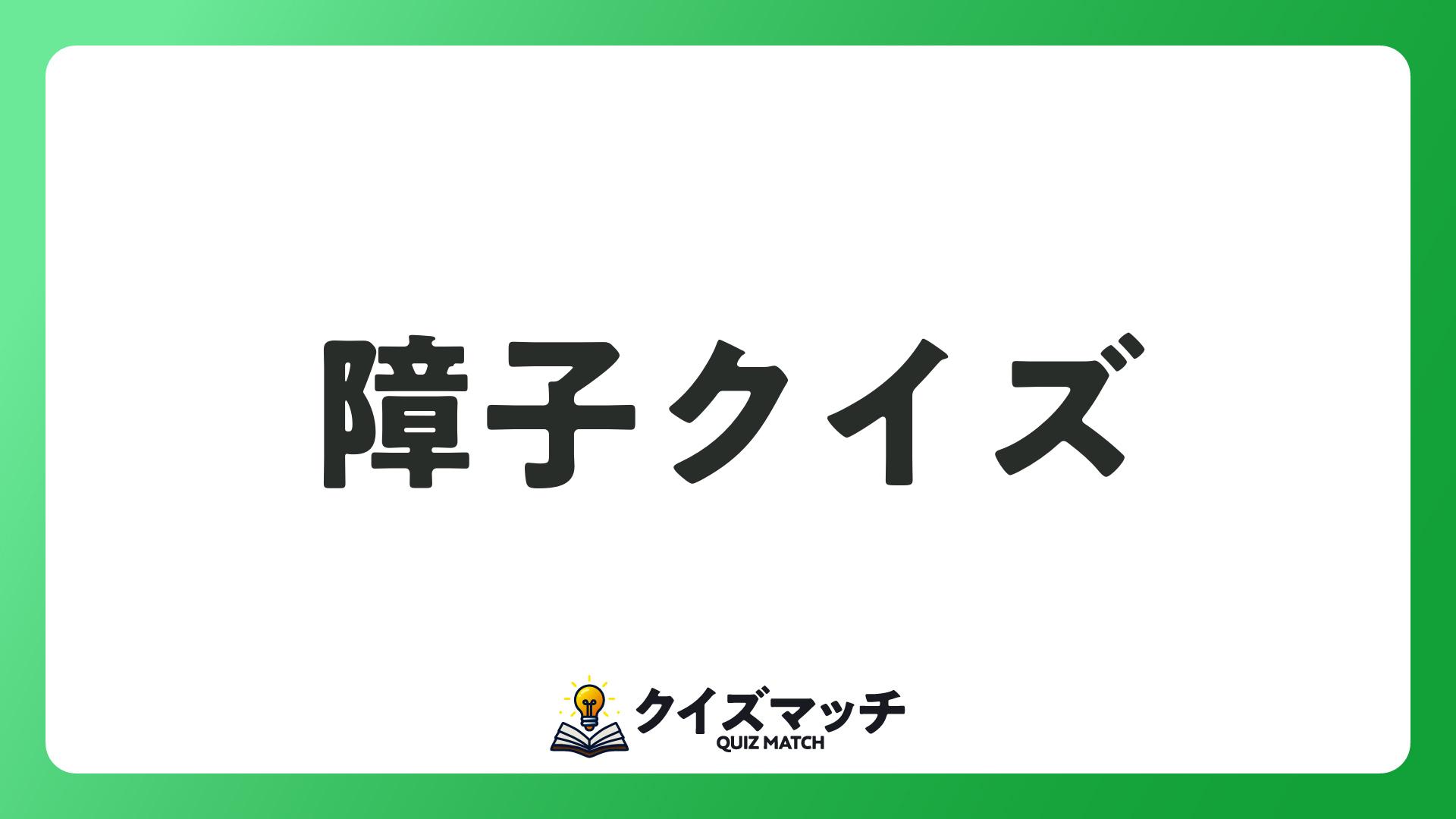障子は日本の伝統的な建具の代表格で、和室の雰囲気を象徴するアイテムです。主に和紙を用いて作られ、柔らかな光を取り入れつつ外からの視線を遮る効果があります。今回は、そんな障子についての豆知識を10問クイズにしてお届けします。障子に関する歴史や素材、補修方法など、意外と知らないことも多いかもしれません。障子への理解を深めていただければ幸いです。
Q1 : 現代で障子に使われることがある“プラスチック障子紙”の利点は?
現代では従来の和紙の代わりに、破れにくいプラスチック製障子紙も人気です。小さな子どもやペットのいる家庭でも安心して使える利点があります。一方、光を全く通さない、色が鮮やかすぎる、熱を通しやすいといった特徴は一般的ではありません。
Q2 : 障子の標準的な高さはおよそどれくらい?
障子の標準的な高さは約180cm前後が一般的です。もちろん住宅や部屋によって差がありますが、日本の伝統的な引き戸や障子の多くはこのサイズを基準に作られています。90cmは小さすぎ、210cmや250cmは大きな空間向けです。
Q3 : 障子の和紙の破れを即席で補修する方法として一般的なのは?
障子の和紙が破れた際、応急処置として補修用の障子テープを使うのが一般的です。白色の細いテープが市販されており、目立ちにくく手軽に補修できます。新聞紙や絵の具、接着剤で固めるのはあまり実用的ではなく、見た目も損なわれます。
Q4 : 障子が和室の環境にもたらす効果で正しいものは?
障子に使われる和紙には調湿作用があり、室内の湿度を一定に保ったり、結露を防いだりする働きがあります。室内の快適性向上にも寄与します。全く効果がない、冬に部屋を冷やすということはありません。
Q5 : 障子の歴史について、誤っているものはどれ?
障子は中国から直接伝来したものではなく、日本で独自に発展しました。古くは板戸が使われていましたが、平安時代に現在のような障子の原型が生まれ、明治以降も和室のある家庭を中心に利用され続けています。
Q6 : 障子の桟(さん)とは何を指す?
障子の桟(さん)は、和紙を貼るための格子状の骨組み部分を指します。桟があることで和紙がしっかり張られ、障子自体の強度も保たれます。和紙の種類、取っ手や戸車は桟とは異なります。格子状のデザインは日本の伝統的な意匠の一つでもあります。
Q7 : 障子の補修のとき、和紙を貼る前に木枠についた古いのりや和紙を落とす方法は?
障子の張替え時には、水を含ませて古い和紙やのりを柔らかくし、そっとはがします。無理にカッターやヤスリで削ると木枠を傷める危険があるため避けるべきです。また、乾いた布ではのりは落ちません。水分で和紙やのりをやわらかくしてから作業します。
Q8 : 障子の主な役割として正しくないものはどれ?
障子は、和室を仕切ったり、外光を室内にやわらかく取り入れるための建具です。視線を遮る効果もあります。しかし遮音性はあまりなく、外の騒音を遮る効果は低いです。構造上、障子自体は音を通しやすい素材であるため、主な役割とは言えません。
Q9 : 障子の和紙を木枠に貼る際によく使う接着剤は?
障子の張替えに使われる伝統的な接着剤はでんぷんのりです。でんぷんのりは水溶性で、和紙を傷めにくく、乾いた後もはがしやすいのが特徴です。ボンドやテープ、グルーガンも現代の補修では使われることがありますが、従来は主にでんぷんのりが用いられています。
Q10 : 障子に使用される代表的な素材はどれ?
障子は日本の伝統的な建具であり、主に和紙を木枠にはめ込んで作られています。和紙は光を柔らかく取り入れながらも、外からの視線を遮る効果があります。ガラスや布、プラスチックも現代では一部使用例がありますが、伝統的な障子の基本素材は和紙です。和紙独特の質感と、調湿性、断熱性も障子の魅力の一つです。
まとめ
いかがでしたか? 今回は障子クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は障子クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。