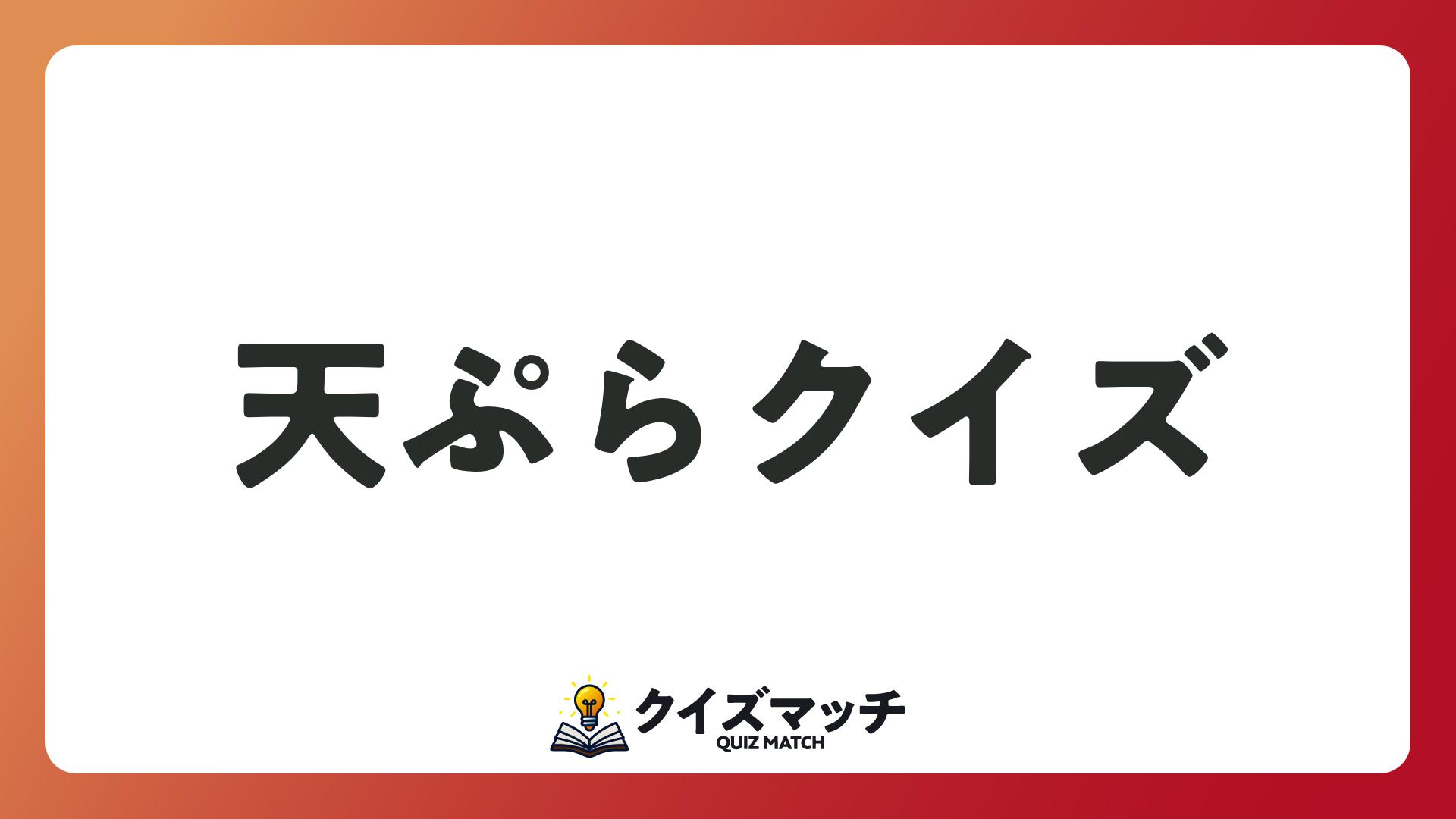天ぷらはまさに日本の代表的な料理の一つです。その歴史や調理法、食べ方には興味深い背景がたくさんあります。本クイズでは、天ぷらの発祥やタレの作り方、人気の食材や揚げ方のコツなど、天ぷらに関する様々な知識を問います。クイズを通して、読者のみなさんにもっと天ぷらの魅力を知っていただければと思います。どうぞお楽しみください。
Q1 : 天ぷら専門店のカウンターでよく使われる器はどれ?
天ぷら専門店では、揚げたての天ぷらを油切り用の天紙(てんがみ)を敷いた木の板や金網の上に置いて提供されることが一般的です。余分な油を吸い、揚げたての食感が長持ちします。陶器やガラス、竹ざるが使われることは少ないです。
Q2 : 天ぷらを揚げる最適な温度帯はどれ?
天ぷらを美味しく揚げるための油温は、おおよそ160〜180℃が適しています。これより低いと衣がべちゃつき、高すぎると焦げやすくなります。家庭用の温度計を使って計ることもおすすめです。
Q3 : 天ぷら油に最も一般的に使われる植物油はどれ?
天ぷらには菜種油が最も一般的に使われてきました。風味やコスト、からっと揚がるなどの理由からです。ごま油は香りづけで一部加えることもありますが、主役は菜種油。オリーブ油やひまわり油は伝統的ではありません。
Q4 : 天ぷらで人気の野菜「ししとう」。ししとうの正しい特徴は?
ししとうは唐辛子(ピーマンやパプリカも含む)の仲間ですが、基本的に辛みはほぼなく、野菜天ぷらの定番です。ただしごく稀に辛いものに当たることがありますが、全てが辛いわけではありません。ナスの仲間や根菜でもありません。
Q5 : 天ぷらの語源「tempura」の由来とされるポルトガル語の意味は?
「天ぷら」は「tempora」というラテン語(ポルトガル語経由)で「四季のうち、肉食を断つ時期」を意味する言葉に由来します。キリスト教の行事期間に食べられる魚や野菜の揚げ物から派生したとされます。
Q6 : 天ぷらに最も多く使われる魚介類はどれ?
天ぷらで最もポピュラーな魚介と言えばエビです。プリッとした食感と甘みが衣とよく合い、歴史的にも庶民から高級料理店まで幅広く提供されています。カニやイカ、タコも使われますが、エビには及びません。
Q7 : 伝統的な天ぷらのタレ(天つゆ)を作る際、使われないものはどれ?
伝統的な天つゆは、だし・醤油・みりんで作られます。これにおろし大根を入れて食べるスタイルが一般的です。砂糖も入れることがありますが、味噌は通常使われません。「味噌天つゆ」というものもほぼ存在しません。
Q8 : 天ぷらの衣を作るとき、カリッとした食感を出すために重要なのはどれ?
天ぷらの衣は、小麦粉を冷水でサッと混ぜるのがカリッと仕上げるポイントです。冷水を使うことでグルテンの発生を抑え、サクサク軽い衣になります。よく混ぜすぎると重くなり、小麦粉を二度ふるっても大差はありません。油を混ぜることもありません。
Q9 : 江戸時代、天ぷらが主に食べられていた場所はどこ?
江戸時代の天ぷらは、主に屋台で食べられていました。庶民のファストフードとして、通り沿いや川沿いで手軽に食べる料理でした。当時は家庭や寺院で食べることは少なく、現在のように料亭や専門店で食べられるようになったのはもっと後のことです。
Q10 : 天ぷらの発祥に深く関係している外国はどこ?
天ぷらは16世紀に日本に伝わった料理で、その発祥にはポルトガルが大きく関係しています。ポルトガルの宣教師や商人たちが長崎に伝えたフリッター(揚げ物)が日本で独自の進化を遂げ、現在の天ぷらとなりました。中国やオランダも日本料理に影響を与えたことはありますが、天ぷらへの大きな影響はポルトガルだけです。
まとめ
いかがでしたか? 今回は天ぷらクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は天ぷらクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。