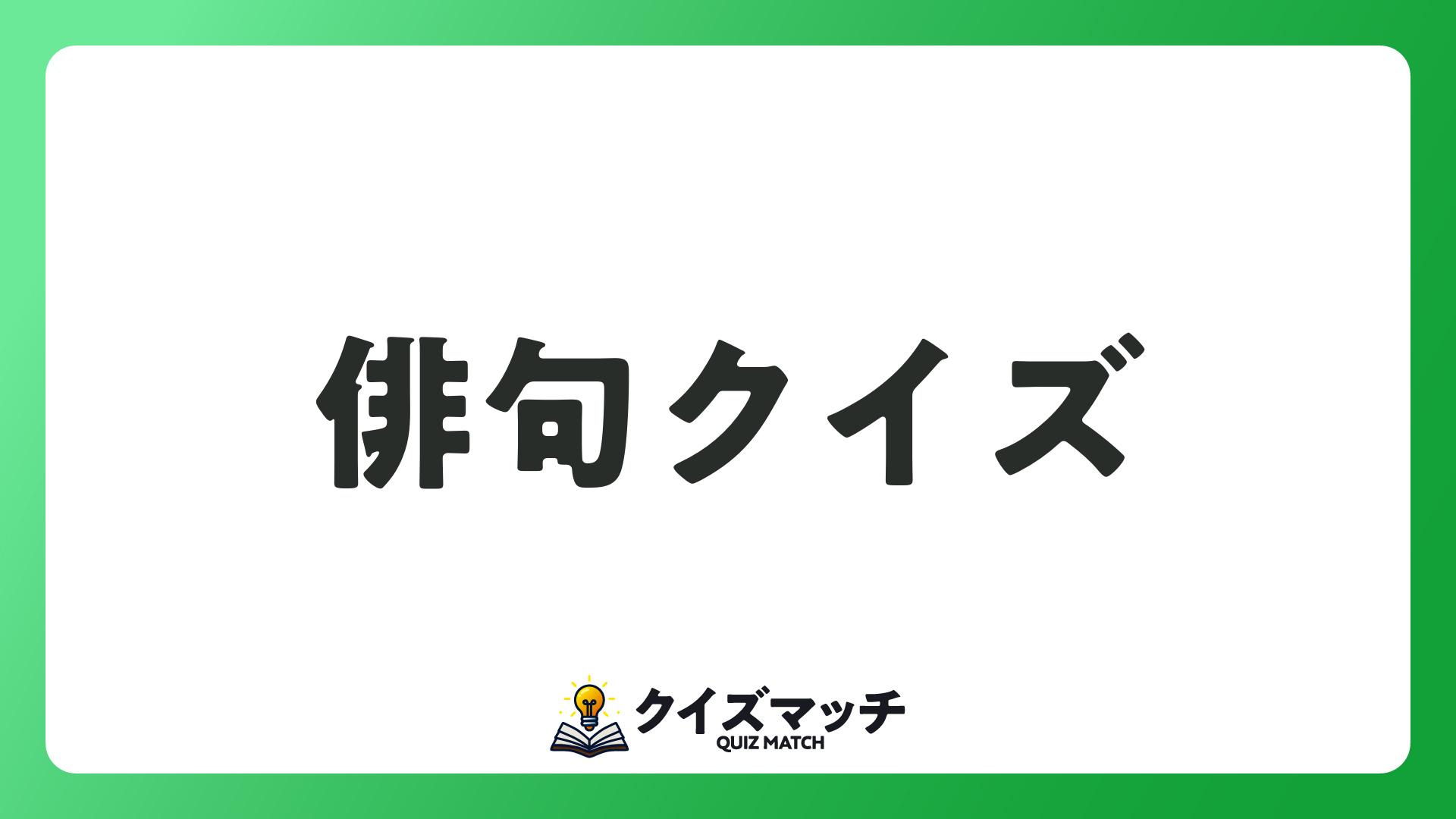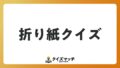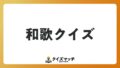俳句は五・七・五の言葉の響きが魅力的な日本の伝統的な短詩形です。季節感を象徴する言葉や、一瞬の情景を巧みに捉えた名句が数多く残されています。この記事では、俳句ファンやこれから学びたい人のために、10問の俳句クイズをお届けします。作者や季語、定型といった基本知識から、近代俳句の革新まで、幅広い分野をカバーしています。俳句の奥深さや楽しさを感じていただければ幸いです。
Q1 : 「春の海 ひねもすのたり のたりかな」という句の作者は誰?
この句は与謝蕪村の代表作です。春の穏やかな海の様子が「のたりのたり」とゆったり描かれ、俳句の中でも特に人気の高い一句です。与謝蕪村は江戸時代中期の俳人・画家としても知られています。
Q2 : 現代俳句で反定型(自由律俳句)を主導した俳人は誰でしょう?
種田山頭火は従来の定型(5・7・5)や季語にとらわれない自由律俳句の代表的作家です。山頭火は日常や内面世界を自分の言葉で素直に表現しました。
Q3 : 次のうち、俳句雑誌『ホトトギス』の創刊に最も関わった人物は誰でしょう?
俳句雑誌『ホトトギス』は高浜虚子が中心となって発展させました。正岡子規の勧めを受けて編集を引き継ぎ、俳句革新運動の中で大きな役割を担いました。
Q4 : 一茶の句『やせ蛙 まけるな一茶 これにあり』はどの季節の俳句でしょう?
この句に登場する「蛙」は夏の季語です。俳句では動物や植物などが季節を象徴する語になることがよくあり、「蛙」は基本的に夏のものとされます。
Q5 : 俳句において、季語がない句を何と呼ぶでしょう?
俳句では、季語が使われていない句を「無季俳句」といいます。無季俳句は従来の俳句の習慣に反し、20世紀以降に増えましたが、現在も季語を重んじる伝統が主流です。
Q6 : 『柿食へば 鐘が鳴るなり 法隆寺』の作者を選んでください。
この句の作者は正岡子規です。明治時代の俳人であり、古典的な俳句の枠を残しつつ新しい表現に挑戦しました。法隆寺の鐘と柿の風味という秋の情景を結びつけた名句です。
Q7 : 江戸時代に活躍した「三大俳人」に数えられない人物は次のうち誰でしょう?
「三大俳人」とは、松尾芭蕉、与謝蕪村、小林一茶の三人を指します。正岡子規は明治時代の俳人であり、俳句の革新に大きく貢献しましたが、江戸時代の「三大俳人」には含まれません。
Q8 : 『古池や 蛙飛びこむ 水の音』の作者は誰でしょう?
この有名な俳句の作者は松尾芭蕉です。芭蕉は江戸時代の俳諧師で、数多くの傑作を残しました。この句はその代表作であり、自然の静けさや人間存在の一瞬を表現したものとして高く評価されています。
Q9 : 次のうち、俳句に必須とされている要素はどれでしょう?
俳句においては「季語」が必須とされています。季語とは季節を表す言葉であり、自然や季節感を詠み込むことが俳句の大きな特徴です。他の選択肢は和歌や詩全般に見られますが、俳句の約束としては必須ではありません。
Q10 : 俳句の定型として広く知られる音数はどれでしょう?
俳句は、五・七・五の合計17音からなる伝統的な日本の定型詩です。五・七・五という音数が定型としてもっとも重視されており、他の音数のパターンは俳句としては認められません。変則的な形も稀に見られますが、基本形は5・7・5です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は俳句クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は俳句クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。