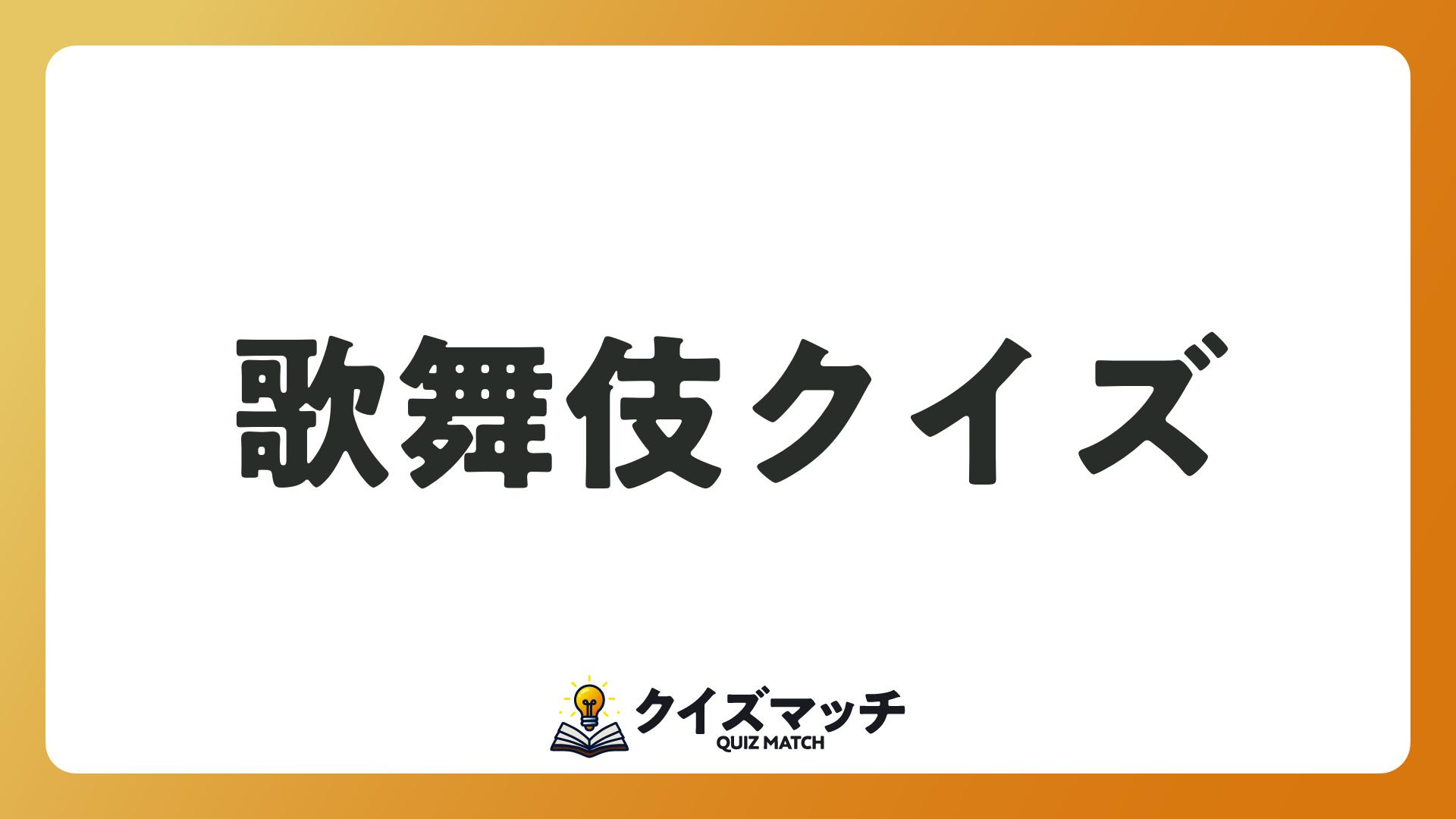200年以上の歴史を誇る歌舞伎。その華麗な世界を10問のクイズでご紹介します。出雲阿国から始まった歌舞伎の起源、伝統的な演技様式、有名な演目、そして役者の文化まで、歌舞伎ならではの魅力を探ってみましょう。歌舞伎初心者から通人まで、この機会に新しい発見をしていただければ幸いです。
Q1 : 歌舞伎独特の『大向こう』とは何ですか?
歌舞伎における『大向こう(おおむこう)』は、観客席の後方から役者や場面に対して声をかける伝統的な応援や称賛の掛け声です。主に役者の屋号を叫ぶなどして舞台と客席の一体感を生み出す役割を果たし、歌舞伎特有の観劇文化の一つです。修練を積んだ常連ファンが行うのが一般的です。
Q2 : 歌舞伎の伴奏楽器で主に使われる和楽器はどれですか?
歌舞伎の音楽では主に三味線が使われ、浄瑠璃や長唄などの歌や語りとともに演奏されます。場面の雰囲気や登場人物の感情を表現し、舞台を盛り上げる大切な役割を担っています。その他にも笛や太鼓などの和楽器も使用されますが、三味線が特に欠かせません。
Q3 : 女性の役を男性が演じる歌舞伎の役者を何と呼びますか?
歌舞伎では、女性役は必ず男性が演じ、その役者を「女形(おんながた)」と呼びます。女形は所作・声・表情を工夫し、女性らしさを追求する特殊な演技が要求されます。江戸幕府の政策で女性の出舞台が禁じられたことから発達し、独自の美学と高度な技術が養われてきました。
Q4 : 歌舞伎の舞台で回り舞台が導入された時代はいつですか?
歌舞伎の舞台では「回り舞台(まわりぶたい)」が江戸時代中期の文化・文政年間(19世紀前半)に考案されました。これにより短時間で場面転換が可能になり、演出の幅が広がりました。現代の舞台装置の先駆けとも言える仕掛けとして、歌舞伎の舞台構成を大きく発展させました。
Q5 : 歌舞伎十八番とは何ですか?
歌舞伎十八番(かぶきじゅうはちばん)は、市川団十郎家が得意とした18の演目をまとめたものです。初代市川団十郎や成田屋の流儀を示す象徴で、勧進帳、暫(しばらく)などが含まれます。成田屋市川家の芸の粋を世に伝えるために整理された選り抜きの演目です。
Q6 : 歌舞伎の演技様式で、見得(みえ)はどのような時に使われますか?
見得(みえ)は、歌舞伎特有の演技法で役者が印象的なポーズをとり、しばらく静止して感情の盛り上がりや重要な場面を強調するときに使われます。このポーズは観客に役者の心理を伝えるためのもので、見得を切ることで劇的な効果や喝采を生み出します。
Q7 : 歌舞伎で家ごとに受け継がれる称号を何と言いますか?
歌舞伎では役者ごとに「屋号(やごう)」と呼ばれる家名があり、例えば「成田屋」「市川家」などが有名です。屋号は舞台上や劇場で役者への掛け声(大向こう)の際などにも使われ、役者ごとの伝統や家柄を重視する歌舞伎の特徴のひとつになっています。
Q8 : 歌舞伎の有名な演目の一つ『勧進帳』で主役の武将は誰ですか?
『勧進帳』は源義経を主役とした歌舞伎の代表的な演目です。兄・源頼朝から追われる義経とその一行が、弁慶の機転によって安宅の関を突破する物語が描かれています。この演目は歌舞伎十八番にも数えられ、日本の歴史や武士道精神を象徴する作品です。
Q9 : 歌舞伎で使われる隈取(くまどり)とは何を指しますか?
歌舞伎における隈取(くまどり)は俳優の顔に施される独特な化粧法のことで、役柄や心情を色や線によって表現します。代表的なものは赤色(力強さ・正義)、青色(悪役・怨念)、茶色(妖怪や超自然的存在)などがあります。隈取は観客に役柄の特徴を視覚的に伝える重要な演出です。
Q10 : 歌舞伎の起源とされる人物は誰ですか?
歌舞伎の始まりは、17世紀初頭に京都の四条河原で「かぶき踊り」を始めた出雲阿国(いずものおくに)とされています。出雲阿国は女性で、斬新な踊りや奇抜な装いで評判となり、多くの人々を集めました。その後、庶民の娯楽として広がり、歌舞伎の基礎を築いた人物です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は歌舞伎クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は歌舞伎クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。