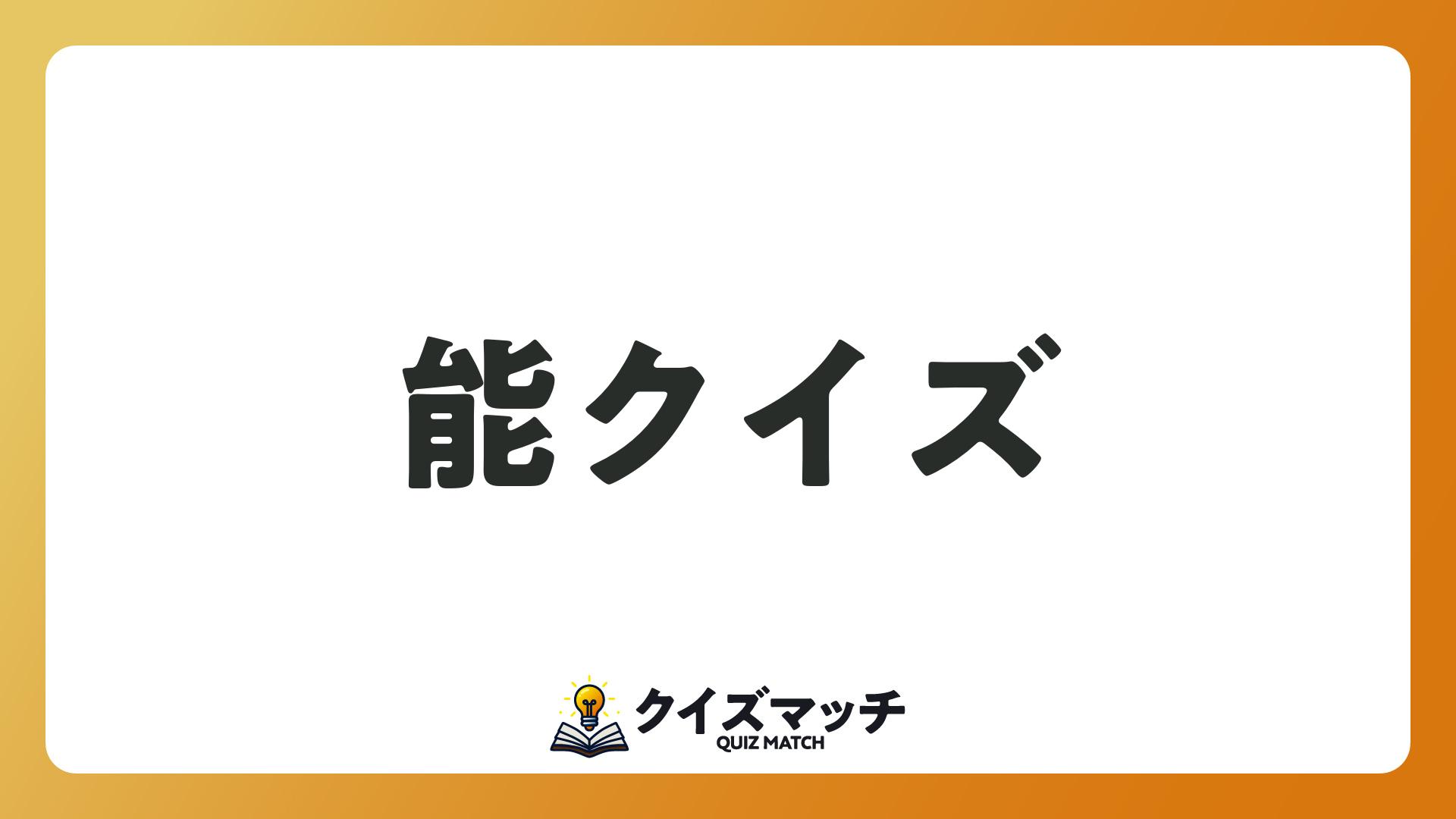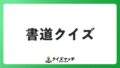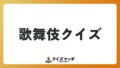能楽の主要な形式である「能」と共によく演じられる日本の古典芸能は、世俗的な人物と日常をテーマとする「狂言」です。能と狂言は、室町時代より伝わる伝統のある「能楽」と総称される古典芸能で、荘重な世界観と滑稽な対比が観客に変化と楽しみを与えています。本クイズでは、能楽の歴史、様式、演目といった多彩な特徴について、10問でご紹介します。
Q1 : 能において「老女物」「鬼物」などのカテゴリーのことを何と呼ぶ?
能には「老女物」「鬼物」「雑能物」「修羅物」など、内容や登場人物によって分類する独特の区分方法があり、これを「能物」と呼びます。たとえば老女物は老女が主役、鬼物は鬼が主役といったように、カテゴリーごとに主役やテーマが異なります。
Q2 : 能楽が発展した主要な時代はどれ?
能楽は14世紀の室町時代に大きく発展しました。その中心には観阿弥・世阿弥親子がいます。新たな脚本や演出、洗練された美学により、武士階級を中心に支持を集め、日本を代表する芸術となりました。江戸時代には幕府の保護を受けて地方にも広まりました。
Q3 : 能で上演される演目の主な構成要素に含まれないものはどれ?
能の演目は「舞」「地謡」「囃子」などから構成されていますが、日常会話のような「セリフ回し」はほとんどありません。能のセリフは詩的・叙情的で節回しや独特の声の出し方で表現され、写実性を追求した現代劇のセリフとは異なります。
Q4 : 能の曲目で、平家の武将の亡霊を主人公とする代表作はどれ?
「敦盛」は平家の武将・平敦盛の霊が主人公となる能の名作です。源氏の武将・熊谷直実と敦盛の交流を描き、無常観と仏教的な救済が大きなテーマです。戦死した敦盛の魂が舞台上で語ることで、死者の思いを観客に訴えることができます。
Q5 : 能の演目「葵上」でシテが演じる役はどれ?
「葵上」は源氏物語を題材にした能の代表的な演目です。シテは六条御息所の怨霊を演じ、葵上を苦しめる場面が描かれます。生霊として登場する六条御息所の激しい嫉妬や激情、そして成仏への過程が、大きな見どころとなっています。
Q6 : 能の代表的な楽器で、鼓の一種でリズムを刻むものはどれ?
能楽に用いられる主要な楽器として、小鼓、大鼓、太鼓、笛があります。このうち「大鼓」は、両手で打つ鼓の一種で、非常に高い緊張感のある音を出し、曲のリズムや雰囲気を決定する要素です。大鼓奏者(大鼓方)は高い技術を持ち、演者や他の楽器と息を合わせて演奏します。
Q7 : 能の舞台で、主役を演じる役者の呼称はどれ?
能の舞台において、主役を演じる役者は「シテ」と呼ばれます。シテは、物語の主軸となる存在を演じ、面をつけて演技や舞を披露します。対して、シテと対になる重要な脇役が「ワキ」、シテの供をする者が「ツレ」、劇中の詩吟や音楽を支える合唱が「地謡」です。
Q8 : 能の発展に大きく貢献し、“能の大成者”と呼ばれる人物は誰?
世阿弥(ぜあみ)は室町時代の能役者・脚本家で、父・観阿弥と共に能を大成させました。著書『風姿花伝』では能の美学や演技論を説き、今も古典芸能研究の基本文献です。洗練された脚本や独自の演出法を通じ、能を高度な芸術へと押し上げた功績から“能の大成者”と呼ばれています。
Q9 : 「能」に使用される伝統的な仮面の名称として正しいものはどれ?
能に用いられる仮面は「能面」と呼ばれます。能面は、鬼や老人、青年、女性などさまざまな人物や霊的存在を表現するもので、50種類以上の型が存在します。演者は能面をつけることで顔の表情を抑え、微妙な角度や動きによって感情や性格を表現します。その繊細さが能の大きな魅力の一つです。
Q10 : 能楽の主要な形式である「能」と共によく演じられる日本の古典芸能はどれ?
能と共によく演じられる「狂言」は、滑稽なセリフ劇を主とする日本の伝統芸能で、能の演目の間や後に上演されます。能が荘重で神秘的な世界観を持つのに対し、狂言は世俗的な人物と日常をテーマにしており、その対比が観客に変化と楽しみを与えています。ともに「能楽」と総称され、室町時代より伝わる伝統があります。
まとめ
いかがでしたか? 今回は能クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は能クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。