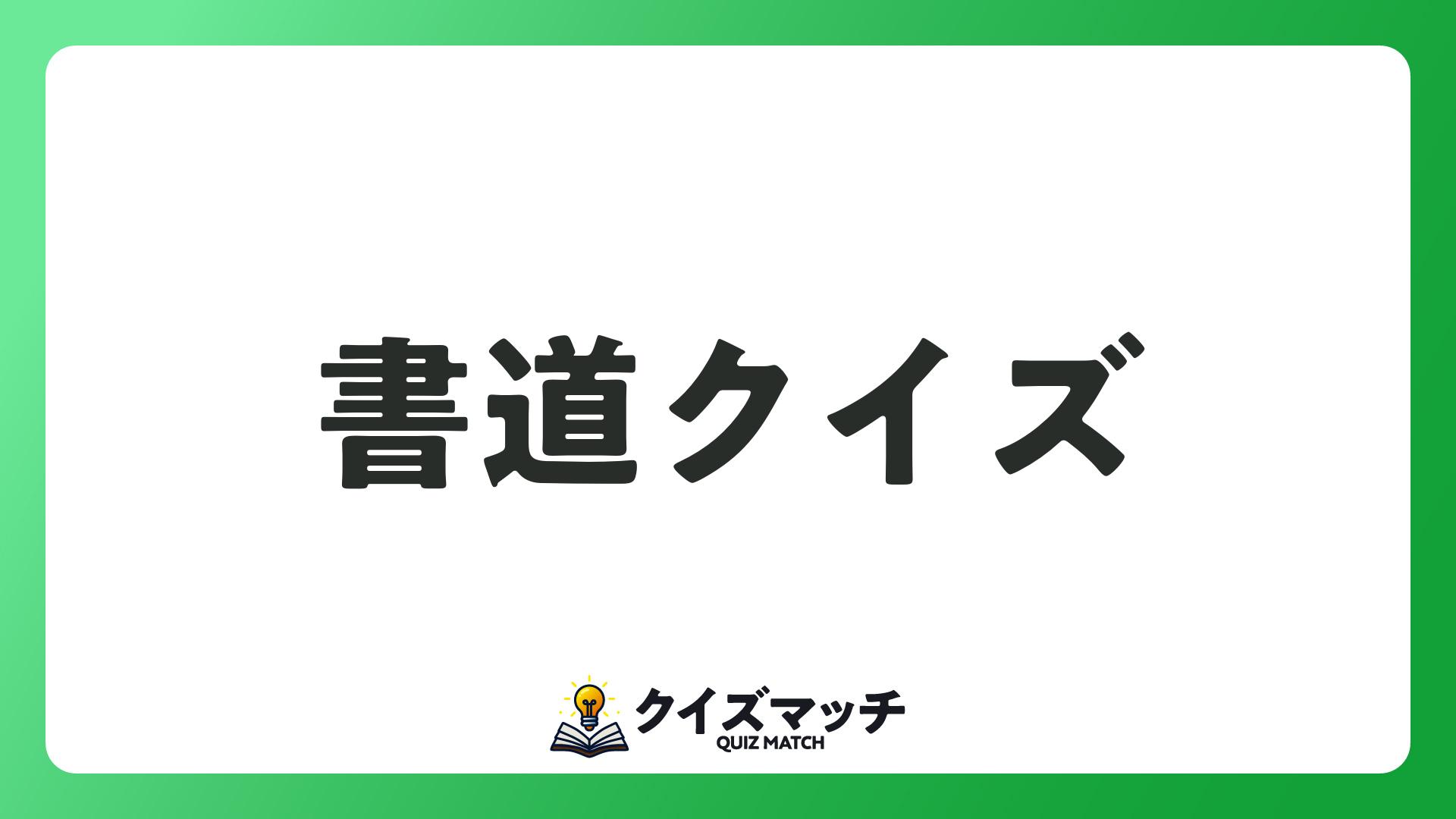書道は日本の伝統文化の中でも大切な位置を占めています。今回は、書道に関する10問のクイズをお届けします。書の三大字体や古典の名品、必要な道具など、書道を学ぶ上で知っておきたい基本知識が盛りだくさんです。書道に興味がある方はもちろん、それ以外の方も楽しめる内容になっています。書道の魅力を感じていただけたら幸いです。
Q1 : 「文房四宝」のうち、最も日本独自の発展を遂げたとされる道具はどれですか?
「文房四宝」の中で「筆」は日本独自の発展が最も顕著です。日本ではヤギや馬、イタチの毛など動物の種類や混合技術の工夫が進み、用途や表現に応じて多様な筆が誕生しました。他の墨、硯、紙も日本特有の工夫がありますが、筆の発展と多様性は特に際立っています。
Q2 : 書道の臨書とは、どのような意味でしょうか?
臨書(りんしょ)は、歴史的価値ある古典や名筆の書をお手本にして、できるだけ忠実に模写し練習することを言います。これによって基礎技術や作風、精神などを学ぶことが目標です。近現代でも書道の上達に臨書が重要視され、学習の出発点となっています。
Q3 : 日本で広く使われている、「かな」文字が成立した時代はどれですか?
日本の「かな」文字(ひらがな・カタカナ)は、主に平安時代に成立したとされています。万葉仮名から発展し、ひらがなは主に女性に用いられ、漢詩文の男性社会に対する女性の文学的台頭を象徴しています。やがて仮名書道として発展し、日本文化に不可欠な書体となりました。
Q4 : 草書が生まれた目的として最も適切なものはどれでしょう?
草書は、中国で漢字を速く書くために生み出された「速記体」です。画数の多い漢字を大幅に省略・簡略化することで、流れるような連続性が特徴となりました。日常の筆記や書簡に適し、芸術作品でもリズム感や個性を伝えるのに用いられています。
Q5 : 作品中で字の配列や余白の取り方に特に注意する、書道の重要な要素は何と呼ばれますか?
書道では、文字のレイアウトや余白の取り方を「結構」と呼びます。結構が良くないと優れた線質や筆遣いも輝きません。特に作品や条幅、額装作品等では位置関係・配列が重視されます。書道技術の集大成が結構に現れるとも言われるほど重要なポイントです。
Q6 : 書道作品の落款で用いられる、名前などを彫った印章のことを何といいますか?
落款(らっかん)では、名前や雅号を彫った「印」を使います。「印」は「篆刻」とも呼ばれ、多くは石で作られ朱色の印泥で押します。他の選択肢である判子や花押、印泥はそれぞれ別の意味があります。印のデザインも芸術性が求められ、書道の作品には欠かせないものです。
Q7 : 中国・王羲之が書いたとされる、書道の古典的傑作として知られる書物は?
王羲之(おうぎし)は中国東晋時代の書家で、その代表作「蘭亭序」は書道史上屈指の名筆として名高い作品です。「蘭亭序」は宴会の詩文集を序文として認めた作品で、流麗な行書が高く評価されています。「赤壁賦」は蘇軾、「資治通鑑」は司馬光、「史記」は司馬遷による歴史書です。
Q8 : 書道の「四宝」とよばれる道具のうち、含まれないものはどれですか?
書道を行ううえで欠かせない「文房四宝」は、筆・墨・硯・紙の四つです。「墨汁」は現代では広く使われていますが、本来は石炭から作る固形の「墨」を硯で擦って使っていました。手間がかかる伝統の技法の部分を支える四宝は、書道文化の根幹をなします。
Q9 : 日本の書道史で有名な平安時代の三筆とは、小野道風、藤原佐理ともう一人は?
平安時代の「三筆」とは、小野道風(おののとうふう)、藤原佐理(ふじわらのすけまさ)、橘逸勢(たちばなのはやなり)の三人を指します。彼らは官僚としての活躍とともに書の名手としても知られ、日本書道の発展に大きく貢献しました。三筆は現在でも優れた能書家の代名詞的存在です。
Q10 : 書道における「三体」とは、楷書・行書ともう一つは何でしょう?
「三体」とは、楷書・行書・草書の三つの字体を指します。楷書は基本的で最も格式が高く、行書はそれを崩した読みやすい字体、草書はさらに速書きの省略された字体です。隷書や篆書も中国の伝統的な字形ですが、三体には含まれません。現在も競書や作品制作など多くの場面で三体が意識されています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は書道クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は書道クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。