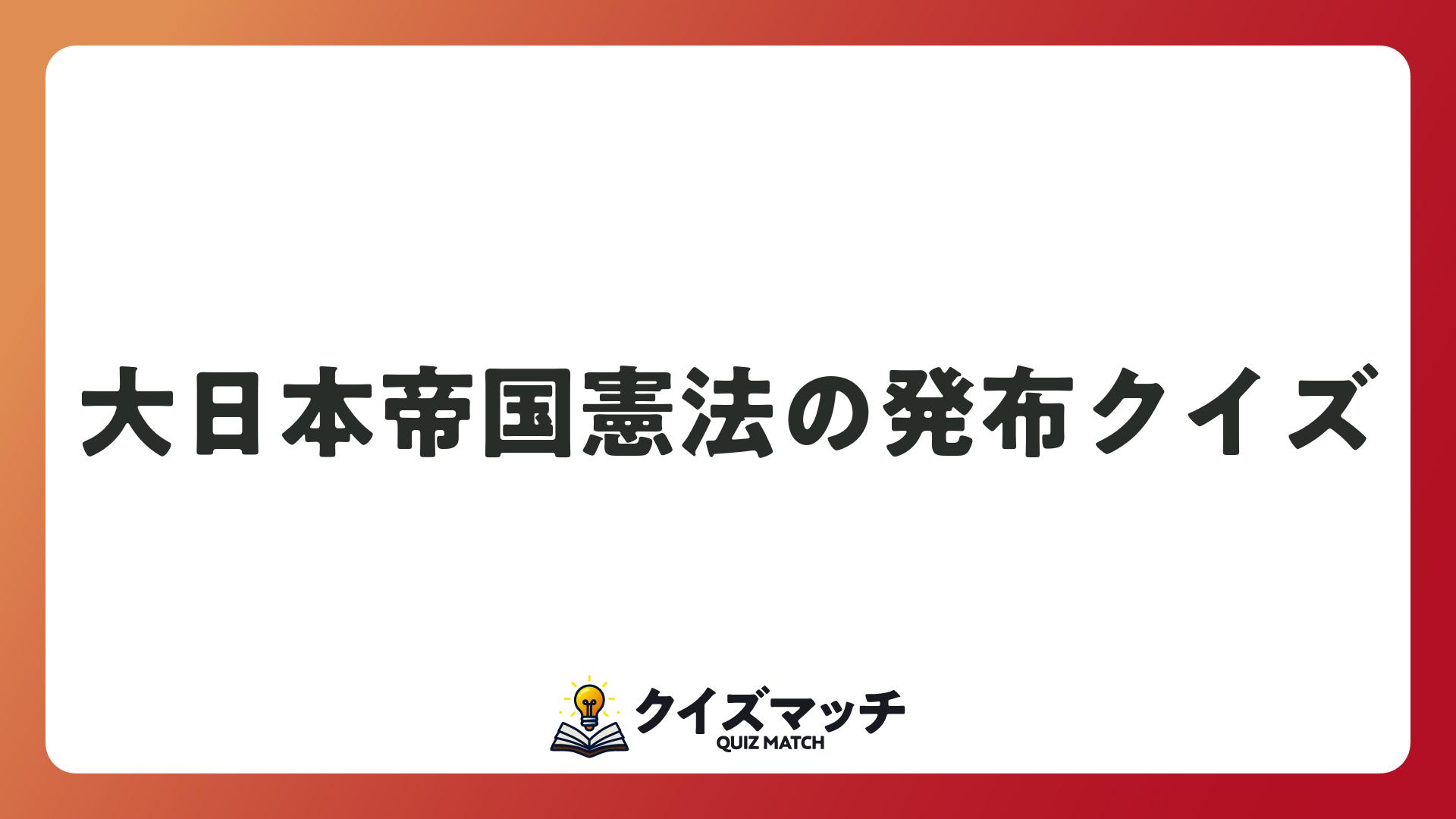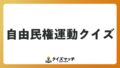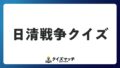大日本帝国憲法の発布から130年以上が経過しました。この憲法は近代日本の体制を大きく変えた重要な出来事でしたが、その時代背景や特徴について詳しく知っている人は意外と少ないのが現状です。本記事では、大日本帝国憲法の発布に関するクイズを10問用意しました。この問題を解きながら、明治期の日本がどのように憲法を整備し、近代国家としての基盤を築いていったのかを振り返ってみましょう。
Q1 : 1947年に大日本帝国憲法に代わって施行された現行憲法の正式名称は?
1947年5月3日、大日本帝国憲法は廃止され、新たに「日本国憲法」が施行されました。現行憲法は国民主権・平和主義・基本的人権尊重を基本原則とし、日本の民主主義体制の礎となっています。正式名称は『日本国憲法』です。
Q2 : 大日本帝国憲法において国民に認められた権利の特徴は?
大日本帝国憲法は国民の権利を『臣民の権利』として認め、法律の範囲内で保障すると規定しました。絶対的なものではなく、国家・法令により制限可能で、現代的な人権思想とは大きく異なる点が特徴です。
Q3 : 大日本帝国憲法の下で設置された議会は何という名前ですか?
大日本帝国憲法の下では、「帝国議会」が設置されました。帝国議会は、貴族院と衆議院の二院制を採用し、予算や法律の制定に関与しましたが、最終的な決定権は天皇にある体制となっていました。
Q4 : 大日本帝国憲法が施行されたのはいつですか?
大日本帝国憲法は発布の翌年、1890年(明治23年)11月29日に施行されました。発布と施行には時差が設けられ、新体制の準備や制度整備のための期間が必要だったためです。同年に第一回帝国議会も開催されています。
Q5 : 大日本帝国憲法の起草にあたって参考にした国の憲法は?
大日本帝国憲法はプロイセン憲法を中心に参考にして起草されました。統治機構や行政制度の強化を重視し、ドイツ(プロイセン)型の立憲君主制を導入しました。伊藤博文らは欧州諸国の制度を広く調査しましたが、特にプロイセン憲法に影響を受けました。
Q6 : 大日本帝国憲法の特徴について、正しいものはどれ?
大日本帝国憲法は天皇主権を基礎に据えた立憲君主制を特徴とし、天皇の大権が強く認められていました。天皇は行政、立法、軍事など重要事項を大権により直接統治できた点が他国の憲法と異なる特徴です。
Q7 : 大日本帝国憲法の発布を担当した内閣総理大臣は誰?
大日本帝国憲法の制定と発布を中心になって担当した初代内閣総理大臣は伊藤博文です。伊藤は憲法調査のために欧州に渡り、プロイセン憲法などを参考に日本の体制に合った憲法草案を作成しました。
Q8 : 大日本帝国憲法の発布を宣布した天皇は誰ですか?
大日本帝国憲法の発布とその布告を行ったのは明治天皇です。明治天皇は近代化政策を進め、日本の体制を西洋型に転換する上で中心的な役割を果たしました。明治天皇の統治のもと、憲法発布と議会創設が実現しました。
Q9 : 大日本帝国憲法の発布日として正しいのは次のうちどれ?
大日本帝国憲法は1889年2月11日に発布されました。この日は神武天皇即位の日(紀元節)と重ねられ、国民的な祝意を込めてこの日が選ばれました。日付の選定は政権の正統性や天皇の威厳を強調する意図もありました。
Q10 : 大日本帝国憲法が発布されたのは西暦何年ですか?
大日本帝国憲法は1889年(明治22年)2月11日に発布されました。これは日本の近代国家形成における重要な出来事であり、日本が近代的な法治国家として西洋に倣い憲法制定を行ったことを意味します。翌1890年から施行され、立憲君主制の体制が整えられました。
まとめ
いかがでしたか? 今回は大日本帝国憲法の発布クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は大日本帝国憲法の発布クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。