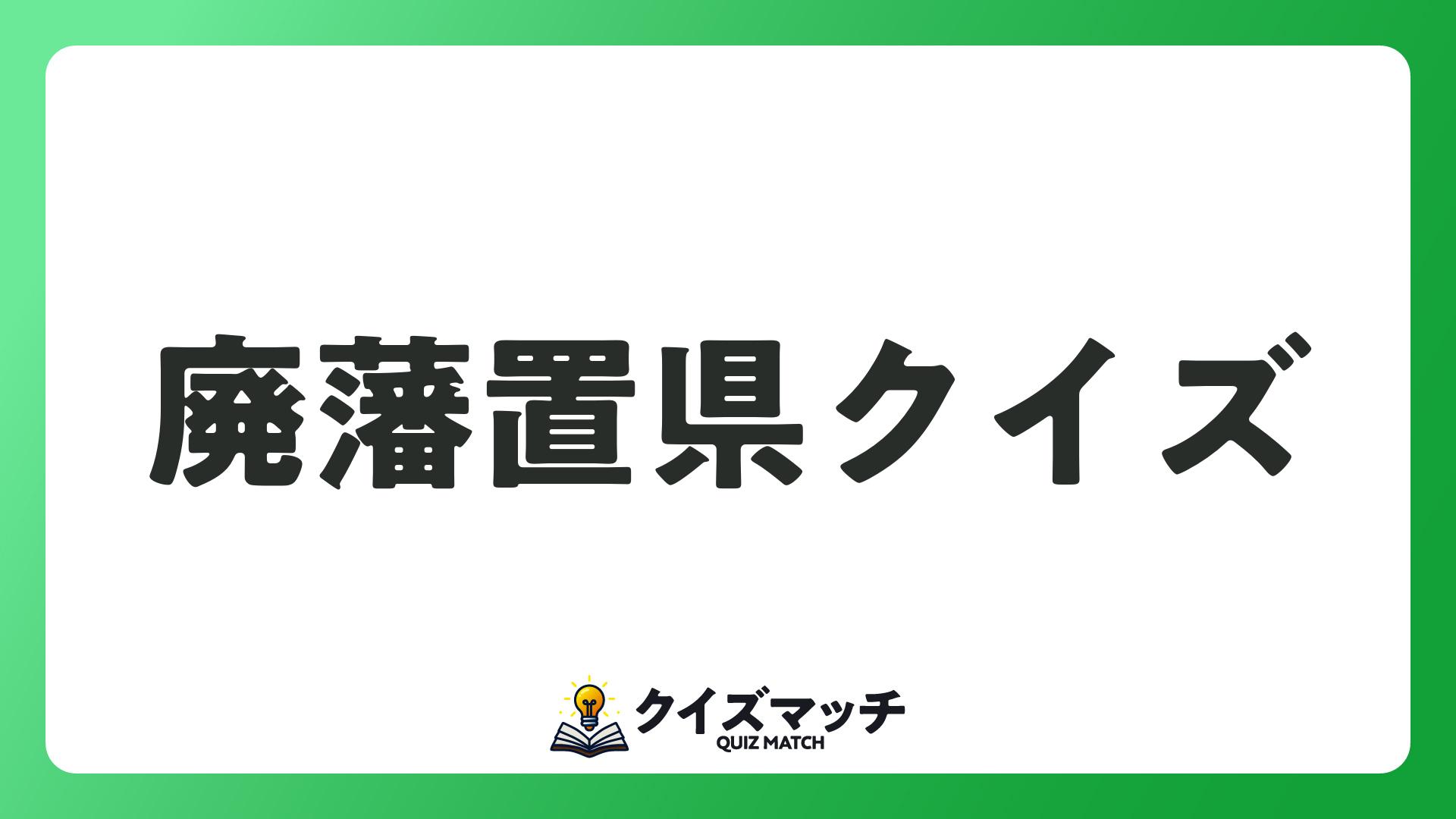廃藩置県は明治政府が推進した重要な政策で、藩を廃止して県を設置したことにより、日本の近代化と中央集権化が加速しました。この大改革は1871年に実施され、それまでは分権的な藩体制が続いていました。このクイズでは、廃藩置県の背景や実施の経緯、それに伴う影響などについて学べます。藩から県への移行や士族への影響など、明治維新期の重要な出来事について理解を深めることができるでしょう。
Q1 : 廃藩置県の進展が地方経済・社会に与えた影響で誤っているものはどれか?
廃藩置県によって、むしろ武士や旧藩士と農民の身分差は解消に向かいました。中央集権化が進み、地方の自治権や特権は縮小しました。士族に対する特権も、秩禄処分や四民平等政策で減少していきました。
Q2 : 廃藩置県を実施するために設置された新たな役所は?
明治政府は廃藩置県実施に際し、各府県に「府知事」や「県令」という役職を設け中央から派遣しました。これは大名や武士による自治の終焉を意味し、地方支配を中央政府の統制下におく道筋となりました。
Q3 : 廃藩置県当初は、県の数が現在より多かったが、初期の県の数として正しい数字はどれか?
廃藩置県直後は藩ごとにそのまま県にしたため、初期の県数は約300にも及びました。しかし、その後の統廃合で70県程度に整理され、最終的に現在の47都道府県になりました。
Q4 : 廃藩置県が断行された背景として正しいものは?
廃藩置県の目的は、中央集権国家の確立にありました。幕藩体制は大名による分権国家だったため、藩を廃止して統一的な近代国家を築くことが急務とされました。諸外国との協調や市民革命といった理由ではありません。
Q5 : 廃藩置県後、士族に支給された特権的な給与制度を何と呼ぶ?
廃藩置県後、旧藩士や武士に支給された給与は「家禄」と呼ばれます。これは江戸時代から続く、身分による給料制度で、明治政府は急激な改革で士族の待遇維持を図りました。しかし財政を圧迫したため、のちに秩禄処分(廃止)が断行されました。
Q6 : 廃藩置県の結果、各県の行政を担当する職名として新たに設けられたのは?
廃藩置県の後、各県には中央政府から「県知事」(当時は府知事・県令とも呼ばれた)が任命されました。これにより、地方行政の主導権は中央に移り、旧藩主による自治は完全に終わりました。現代の「県知事」と同じ由来です。
Q7 : 廃藩置県直前、全国には約いくつの藩が存在したか
廃藩置県直前、全国には約260藩以上が存在しました。明治維新で一部藩の再編や統合もありましたが、江戸時代を通じて約260の大名が各地を治めていました。廃藩後、県の数は数十に整理され、現在の都道府県に繋がっています。
Q8 : 廃藩置県によって藩主(大名)はその後どうなったか
廃藩置県の実施後、旧藩主は東京に移住し「華族」として処遇されました。一部の人は新政府で役職に就くなどしましたが、多くは政治的実権を失い生活費が支給されるだけの存在となりました。県知事には新政府から官僚が派遣されました。
Q9 : 廃藩置県を主導した人物の一人は誰か
廃藩置県の実現に大きく貢献したのは大久保利通です。大久保は中央集権体制を強く推し進め、明治新政府の中枢として政策を立案・実行しました。もちろん、西郷隆盛や木戸孝允も明治維新の要人ですが、特にこの政策で中心となったのは大久保利通です。
Q10 : 廃藩置県が実施された年は?
廃藩置県は1871年に実施されました。それまで日本全国は藩によって分割統治されていましたが、中央集権化を目指す明治新政府により、藩を廃止して県とし、各県に知事を置く形となりました。これにより藩主は東京へ住むことになり、士族による自治は終了しました。西南戦争(1877年)などの年とよく混同されますが、正解は1871年です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は廃藩置県クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は廃藩置県クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。