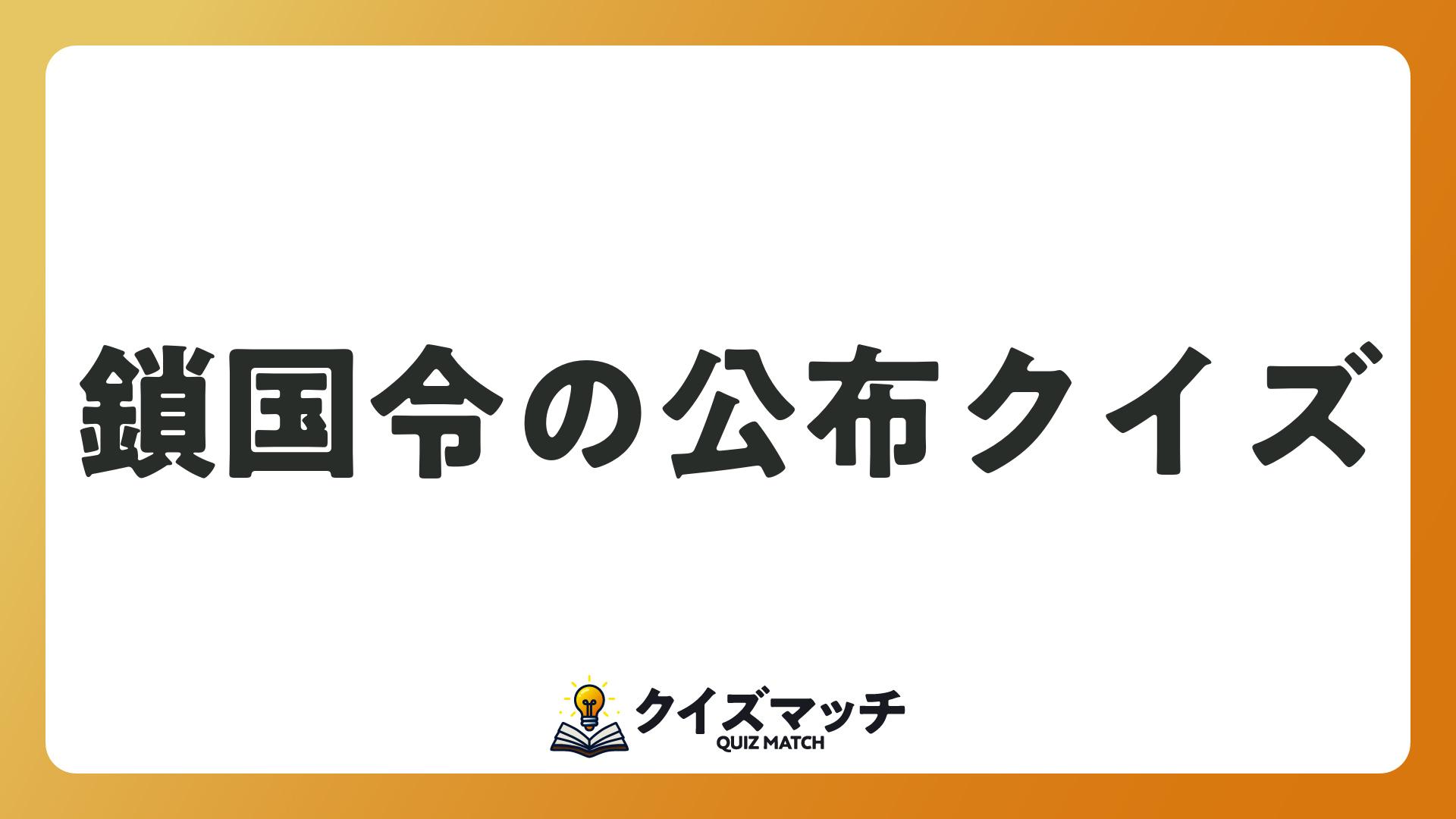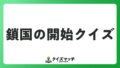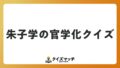江戸幕府の鎖国政策は、日本の歴史を大きく変えた重要な出来事です。1641年に始まったオランダ商館の長崎出島移転を皮切りに、外国からの信仰や文化の浸透を恐れた幕府は、キリスト教の排除や外国船の渡航禁止など、厳しい管理体制を築きました。この鎖国クイズを通して、当時の外交・貿易情勢や、幕府の政策意図について、より深く理解を深めていくことができるでしょう。
Q1 : 鎖国政策の中で唯一、朝鮮と続けていた交流の形式は何か?
江戸時代、朝鮮との国交は断絶されず、朝鮮通信使による使節派遣が継続されていました。これは政治的・文化的な交流が主で、幕府の威信を示す外交行事でもありました。他の選択肢は史実と異なります。
Q2 : 徳川幕府が鎖国体制を維持するため設けた監視の施設は?
江戸幕府は全国の港に「番所」という監視施設を設置し、密航や違法取引を監視しました。奉行所は行政機関、関所は国内の交通や移動管理の拠点、遠見番所は見張り台ですが、通商監視の主役ではありません。
Q3 : 鎖国時代、日本とオランダ・中国を除くすべての外国船来航禁止を示した法令はどれ?
いわゆる「鎖国令」(正式名称は当時存在しませんが、複数の法令の総称)は、オランダ・中国を除く他の外国船の来航を禁止しました。海舶互市新例は明治時代の法令。長崎貿易令や沿海防備令は別の法律です。
Q4 : 鎖国令で来航を禁止された主な理由として間違っているものはどれか?
江戸幕府が鎖国令を出した主な理由は、キリスト教布教の抑止や外国勢力の侵入防止、経済の管理を重視したためです。寒冷化による農民救済は全く関係がありませんでした。
Q5 : 鎖国政策下で通商が許可された中国商人の居住区はどこか?
中国(明・清)の商人は出島ではなく、長崎市内の特定地域(唐人屋敷)に居住させられ、厳しく出入りを監視されていました。オランダ商人は出島、中国商人は唐人屋敷という異なる区分となっています。
Q6 : 鎖国時代、長崎出島を拠点に日本と通商していた国を正しく選べ。
鎖国時代に長崎出島を拠点に公認の通商をしたヨーロッパの国はオランダだけでした。イギリスは早期に貿易から撤退し、中国は出島ではなく唐人屋敷を使用、ロシアとの交流はもっと後の時代です。
Q7 : 1639年に幕府が発布した、ポルトガル船の来航を禁じた政策は何と呼ばれるか?
1639年に発布されたのは「寛永の鎖国令」と呼ばれます。これによりポルトガル船の来航が禁止され、事実上日本が完全な鎖国状態に入りました。他の選択肢の元和や正保、安政は異なる時代や出来事に関連しています。
Q8 : 鎖国政策により日本との外交・貿易が完全に禁止された国はどこか?
スペイン(当時はポルトガルを含むイベリア諸国)は、激しい布教活動が政治介入の恐れありとされ、江戸幕府によって徹底的に排除されました。鎖国時もオランダと中国は限定的ながら貿易を許可されていました。朝鮮は通信使派遣など外交的交流が細々と継続されていました。
Q9 : 鎖国令が出された17世紀、主に禁止されたキリスト教の宗派はどこか?
江戸時代の鎖国政策はキリスト教、とりわけカトリック(特にスペイン・ポルトガルの宣教師が伝えた)を警戒して発布されました。幕府は信者の弾圧や、宣教師の国外追放を行いました。プロテスタントや正教会は当時日本にはほとんど伝わっていませんでした。
Q10 : 江戸幕府が発布した鎖国令によって、オランダ商館が移された場所はどこか?
江戸幕府は鎖国政策の一環として1641年、オランダ商館を平戸から長崎の出島へ移しました。これによりオランダは幕府の厳しい統制下に置かれることになり、出島を通じてのみ貿易が許されました。他の選択肢の下田や佐世保は鎖国時代の主な貿易港ではありません。平戸はもともとオランダ商館があった場所です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は鎖国令の公布クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は鎖国令の公布クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。