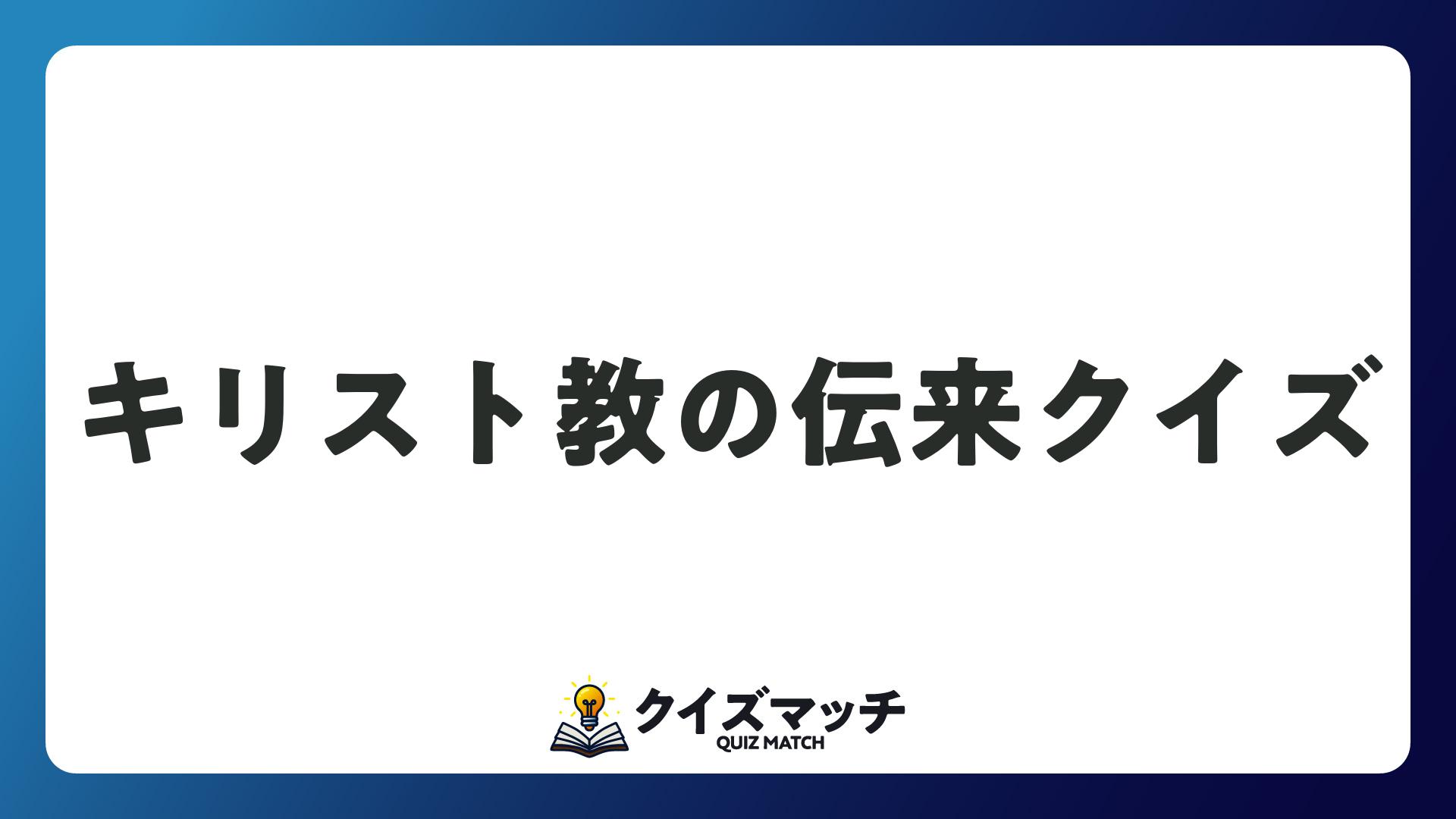日本におけるキリスト教の伝来は、日本の歴史に大きな影響を与えました。1549年にフランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸し、以降各地で布教活動が進められました。長崎や平戸などの地では南蛮貿易と密接に関わり、戦国大名の支援も得ながら、一時は広まりを見せました。しかし、江戸幕府によるキリスト教禁止令などにより、その勢いは衰えていきました。このクイズでは、そうした日本のキリスト教伝来の歴史について、10の問題を用意しました。キリスト教に関する知識を確認し、この重要な歴史を理解する一助となれば幸いです。
Q1 : キリスト教伝来直後に日本で印刷されたキリスト教書物を何と呼ぶか?
「キリシタン版」とは、キリスト教伝来後に日本で印刷・出版された書籍で、教義書や祈祷書、ローマ字での日本語訳などが多く含まれます。宣教師たちによる布教活動の一環でした。伴天連書簡などは特定の文書であり、キリシタン版は書物の総称です。
Q2 : 江戸時代に密かに信仰を守ったキリスト教徒は何と呼ばれたか?
江戸時代の禁教政策下、密かにキリスト教信仰を続けた人々は「隠れキリシタン」と呼ばれました。幕府の厳しい取り締まりにも関わらず、伝統や信仰を親から子へと伝え続けました。他の選択肢は仏教の宗派に関するものです。
Q3 : スペイン人宣教師によって殉教した26人のカトリック信者を何と呼ぶか?
1597年、豊臣秀吉の命により26人のカトリック信者(日本人、スペイン人、ポルトガル人)が長崎で処刑されました。彼らは「長崎二十六聖人」と呼ばれ、日本のキリスト教史において重要な存在とみなされています。
Q4 : 日本でキリスト教が流行した時代はどれか?
日本でキリスト教が流行し始めたのは戦国時代(16世紀中ごろ)です。当時は多くの外国人宣教師が来日し、大名や庶民の中にも信仰する人々が増えました。その後、江戸時代に入ると禁教政策でその勢いは衰えました。
Q5 : 江戸幕府がキリスト教信者を見分けるためにかけた宗教的行動は?
江戸幕府は禁教政策を厳格に施行し、キリスト教信仰を持つ者を見つけるため「踏み絵」を行いました。これはイエス・キリストや聖母マリアの像を踏ませ、信者かどうかを見極めるためでした。踏むことを拒否した者は処罰されました。
Q6 : 平戸や長崎に設けられ、主にキリスト教伝来と関わる貿易の呼称は?
日本における南蛮貿易は、ポルトガルやスペインといった南ヨーロッパの国との貿易を指し、キリスト教の伝来にも深く関与しました。鉄砲やキリスト教が伝来した背景にはこの南蛮貿易の存在がありました。他の選択肢は時代や意味が異なります。
Q7 : 豊臣秀吉が出したキリスト教禁教令の名称はどれか?
豊臣秀吉は1587年、キリスト教宣教師の追放などを定めた「バテレン追放令」を出しました。この政策は国内の混乱やスペイン、ポルトガルの影響力拡大を警戒したものです。禁中並公家諸法度や慶長遣欧使節は別の歴史的出来事に関わるものです。
Q8 : キリスト教の布教を進めた戦国大名として有名なのは誰か?
織田信長は当時新しい宗教であったキリスト教に対して比較的寛容であり、布教活動を自由にさせました。これは仏教勢力の抑制や南蛮貿易の発展を意識した政策でした。豊臣秀吉は後に禁教政策を行い、徳川家康はその禁教を徹底しました。
Q9 : 日本で初めて布教を行ったイエズス会の宣教師は誰か?
日本に初めてキリスト教を伝えたのはイエズス会のフランシスコ・ザビエルです。彼は1549年に鹿児島に上陸し、日本語を学びながら布教活動を行い、多くの改宗者と接触しました。ルイス・フロイスやコエリョは、その後に来日した宣教師です。
Q10 : 日本にキリスト教が初めて伝来した年はどれか?
日本にキリスト教が伝来したのは1549年です。宣教師フランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸し、布教活動を開始しました。この年以降、各地で布教が進められ、多くの日本人がキリスト教に関心を寄せるようになりました。1543年は鉄砲伝来の年、1571年は南蛮貿易の発展、1600年は関ヶ原の戦いが起こった年です。
まとめ
いかがでしたか? 今回はキリスト教の伝来クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はキリスト教の伝来クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。