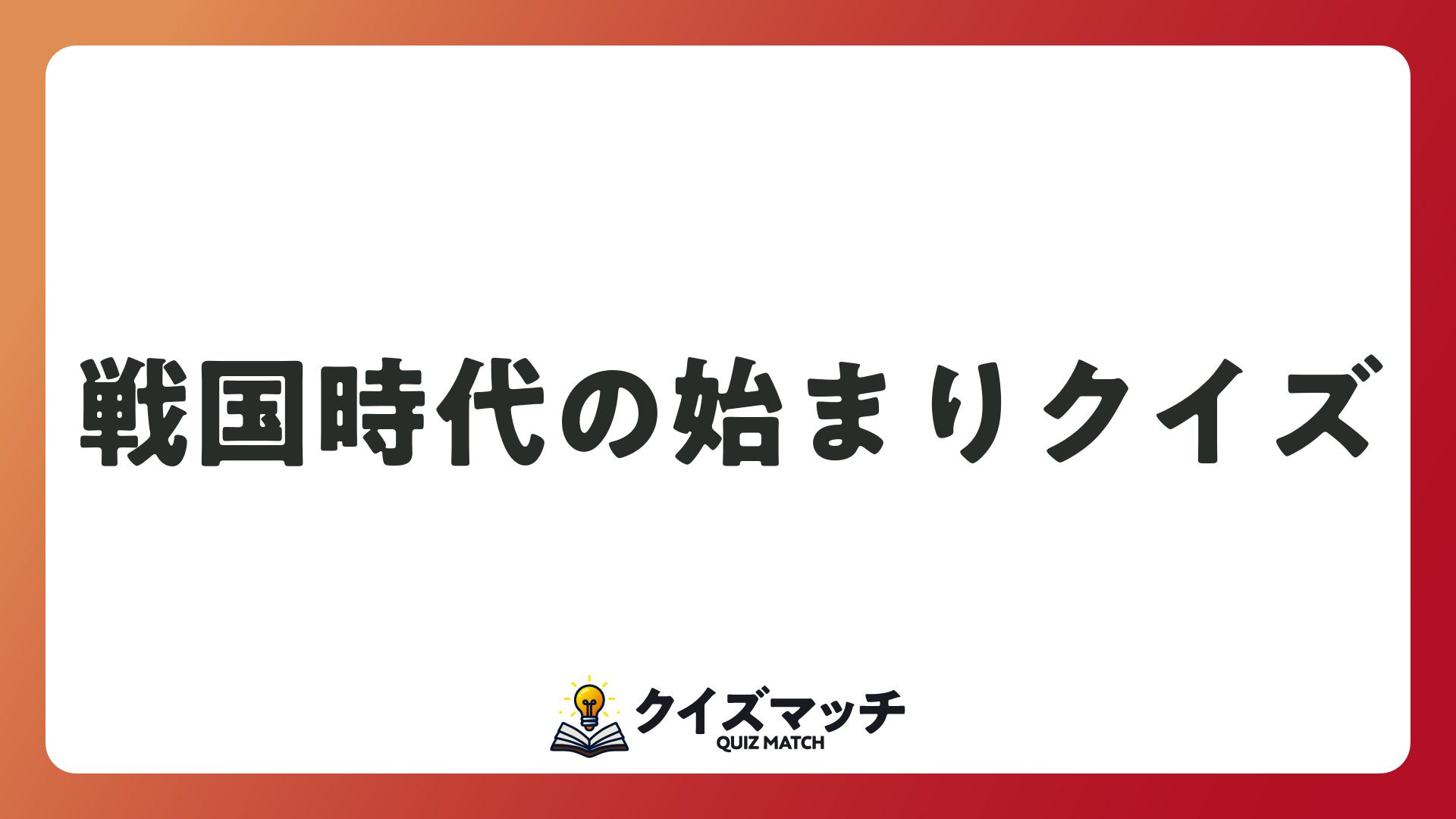戦国時代を象徴する応仁の乱を起点に、各地で激しい権力闘争が繰り広げられました。この内乱を契機に、社会の様相は大きく変容し、新たな勢力が台頭する下克上の時代が幕を開けたのです。本クイズでは、この激動の時代の始まりを象徴する出来事や背景について、10の設問でたっぷりと掘り下げていきます。戦国時代の始まりに隠された歴史の真髄に迫ってみませんか。
Q1 : 応仁の乱後、勢力を拡大した戦国大名の特徴的な政策はどれか?
戦国大名は一向宗(浄土真宗)の門徒を結集した一向一揆などの宗教勢力と協調し、あるいは対抗しながら領国支配を固めました。朝廷から征夷大将軍の任命を受けたり、海外との交易強化、平氏・源氏の復活といった政策は、戦国大名の特徴ではありません。
Q2 : 戦国時代の始まりとは、社会構造の変化も含みます。この時代の特徴として適切なものは?
戦国時代は守護大名による従来の身分秩序が大きく崩れ、在地の国人や有力家臣が主従関係を再編しながら自立的に勢力を拡大しました。荘園制や律令制は弱体化・消滅し、国家統制は分散しました。鎖国は江戸時代初期の政策です。
Q3 : 戦国時代初期の三管領家の一つで、応仁の乱の主要勢力にもなった家はどれか?
室町幕府三管領家は細川、斯波、畠山の三家であり、細川家は応仁の乱で東軍の大将を務めました。細川勝元がその代表です。島津家・徳川家・毛利家はこの時期には全国的な力を持っていませんでしたが、後に戦国大名として台頭しました。
Q4 : 応仁の乱の舞台となった都市はどこか?
応仁の乱は室町幕府の本拠地であり、当時日本の政治・文化の中心地でもあった京都を舞台に繰り広げられました。この乱により京都の市街は焼失し、経済・文化的にも大きな打撃を受けます。大阪や鎌倉、名古屋はこの合戦の主要な戦場ではありません。
Q5 : 下剋上の風潮が広まった戦国時代、その意味として最も正しいものは?
下克上とは「下の者が上の者を倒してその地位につく」ことです。戦国時代、守護大名や領主に代わって有力な家臣や国人が実力で権力を奪い取る動きが全国に広がりました。戦国武将の多くはこうした背景で台頭し、社会全体の流動性を高めました。
Q6 : 応仁の乱の大きな影響の一つとして最も適切なものは?
応仁の乱は従来の守護大名制を大きく動揺させ、各地の在地勢力が台頭しました。これにより大名・家臣・国人層が独自の主導権を握る下克上の社会へと変貌し、後の戦国大名の登場を可能にしました。朝廷や平安貴族の復権、蒙古襲来の再来とは無関係です。
Q7 : 応仁の乱後、戦国大名が支持を得るために行った政策の一つは?
分国法は各戦国大名が自国を統治するために制定した独自の法律です。応仁の乱後、守護権の動揺とともに諸大名が自治を強め、領国支配のために分国法を定めて家臣団や領民の秩序維持に努めました。これが戦国大名の台頭を象徴する代表的な政策です。
Q8 : 応仁の乱で対立した二大勢力、東軍と西軍の指導者は誰だったか?
応仁の乱では東軍の細川勝元と西軍の山名宗全が主導しました。この対立の背景には将軍家の継嗣争いや家督争いがあり、両者を中心に全国から多くの守護大名が参戦しました。この戦いにより守護の力が衰退し、各地で戦国大名が自立する契機となりました。
Q9 : 戦国時代の始まりを告げた応仁の乱が始まったのは西暦何年?
応仁の乱は1467年に細川勝元と山名宗全を中心とする東軍・西軍に分かれて始まりました。室町幕府8代将軍足利義政の後継問題や守護大名の対立が主な要因です。乱は10年以上続き、京都の町は荒廃し、大名家の力関係や土地支配の構造が大きく変動し、戦国時代への道が拓かれました。
Q10 : 戦国時代の始まりを象徴する戦いとして一般的に挙げられる合戦はどれ?
応仁の乱(1467年~1477年)は、京都を中心とした大規模な内乱であり、守護大名の権力が大きく崩れたことで戦国時代の幕開けとされます。それにより各地で国人や戦国大名が台頭し、全国的な下克上の時代となりました。長篠の戦いや桶狭間の戦い、川中島の戦いは応仁の乱以降に起きた戦いなので、正解は応仁の乱です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は戦国時代の始まりクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は戦国時代の始まりクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。