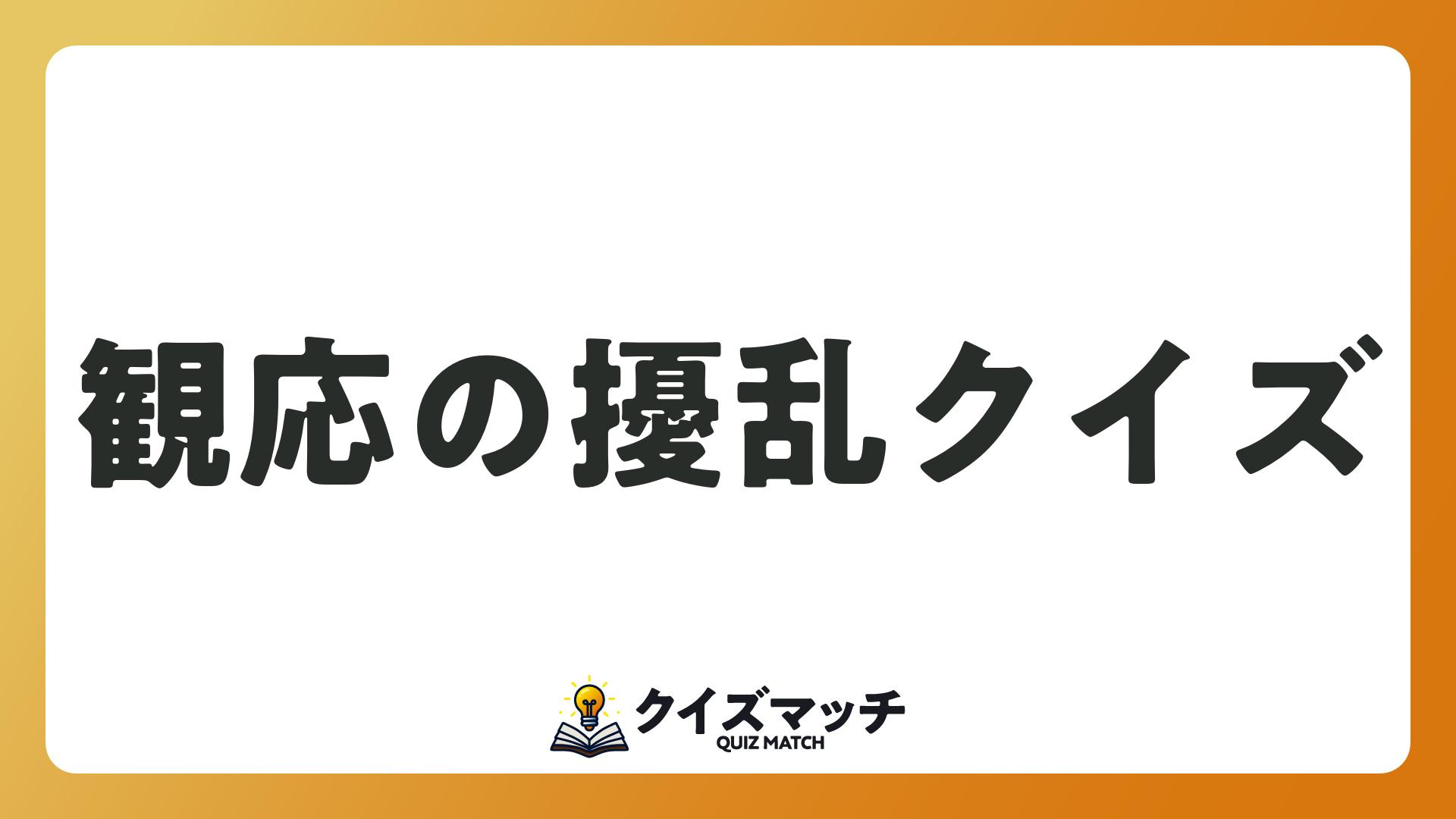観応の擾乱は、室町幕府初期における足利尊氏と足利直義の権力闘争が引き起こした一大内乱です。両者の対立が激化し、最終的に尊氏が直義を討ち取ることで幕府内部の主導権を握りました。この内乱には、恩賞配分をめぐる対立や南朝方への加担など、複雑な背景がありました。足利氏一門の対立が招いた観応の擾乱は、室町幕府の支配体制に大きな影響を及ぼし、守護大名の台頭など、日本中世史の転換点となったのです。
Q1 : 足利尊氏が直義を討つことを決めた事件名として正しいものはどれか?
1351年、南朝方と一時的に和睦するという正平一揆が起こった。これが契機となり、尊氏は直義討伐を決意。正平一揆によって従来の敵味方関係が揺らぎ、尊氏と直義の最終的な決裂をもたらした。
Q2 : 観応の擾乱の一因でもあった「恩賞」の配分問題、直接対立したのは誰と誰か?
観応の擾乱の背景には、幕府初期における戦功に対する恩賞(土地・領地)の配分をめぐる対立があった。直義派と高師直派、それぞれの被官や家臣も巻き込み、配分をめぐる不満が権力闘争を激化させた。
Q3 : 観応の擾乱で足利直義が出家した後保護された人物は誰か?
足利直義は敗北後、足利尊氏の嫡子である足利義詮に保護された形となった。義詮は直義の甥にあたり、鎌倉で直義をかくまった。だが結局、直義はその後毒殺されたとされる。義詮自身は後に第2代将軍となった。
Q4 : 高師直が直義側の武将によって討たれた場所はどこか?
高師直およびその弟の高師泰は、1351年摂津国で直義派の山名時氏らに討たれた。彼らの死によって、直義派が一時的に優位となるが、その後尊氏との対立は続くことになる。この出来事は観応の擾乱における大きな転換点である。
Q5 : 観応の擾乱が及ぼした主な影響はどれか?
観応の擾乱は幕府内部の混乱・動揺を招き、守護大名の権力の自立化、地方武士団の影響力増大など、支配体制の分裂を招いた。これにより守護大名の台頭が加速し、室町幕府の中央集権体制は弱体化の兆しを見せ始める。
Q6 : 観応の擾乱時、南朝方に加勢して戦った足利氏の一門は?
観応の擾乱中、足利尊氏の庶兄弟である足利直冬は、南朝に加担し、尊氏や幕府軍と敵対した。一時的に中国地方を制圧するなど活発に活動したが、最終的には敗れた。この直冬の動向も観応の擾乱の混乱をさらに拡大した要因となった。
Q7 : 高師直が担っていた幕府内の役職は何か?
高師直は室町幕府の執事(しつじ)を務めていた。執事は現在でいう内閣のように、幕府の実務を取り仕切る重要な役職であった。観応の擾乱では、師直の権力が大きくなりすぎたことが、足利直義との対立と内乱の一因となった。
Q8 : 観応の擾乱で死亡した足利直義の最期について正しいものはどれか?
足利直義は観応の擾乱の末期、足利尊氏の命令により毒殺されたと考えられている。戦いで敗北して出家、鎌倉に護送されたが、その後毒殺されたと伝えられる。直義の死で、幕府内部における権力闘争は尊氏の勝利に終わった。
Q9 : 観応の擾乱が始まった年はいつか?
観応の擾乱は観応元年、つまり1350年に起きた。足利幕府の初期、執事の高師直と足利直義、その背後にいる足利尊氏との間で激しい権力争いが巻き起こり、これが戦乱の原因となった。この内乱は2年以上にわたって続いた。
Q10 : 観応の擾乱で直接対立した武将の組み合わせはどれか?
観応の擾乱は、足利尊氏とその弟の足利直義の間で生じた幕府内部の権力闘争であった。尊氏が軍事権を持ち、直義が政務を担っていたが、次第に両者の対立が激化。結果、両者が軍を率いて争う状況となり、日本史上有数の内乱へと発展した。
まとめ
いかがでしたか? 今回は観応の擾乱クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は観応の擾乱クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。