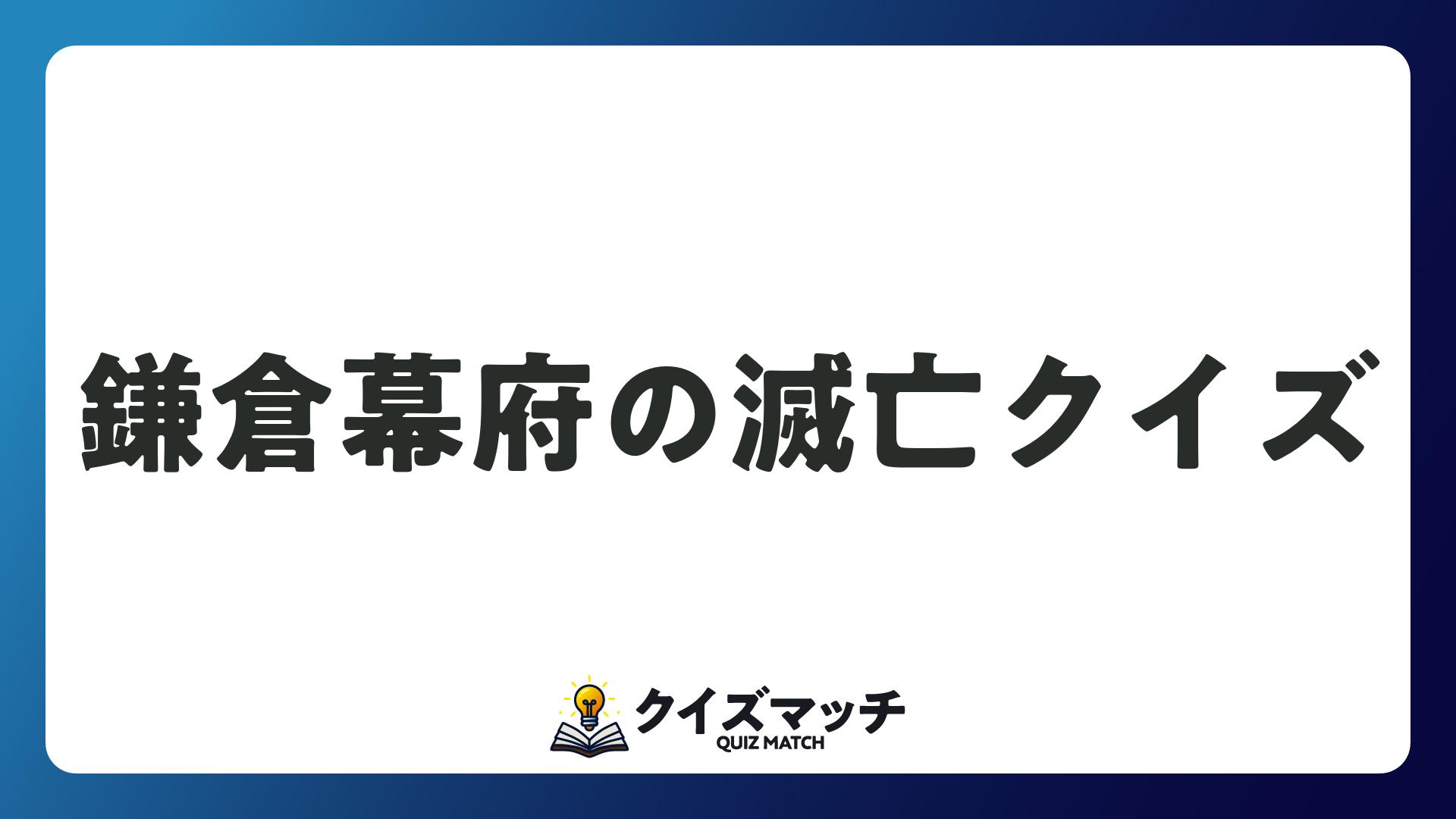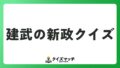鎌倉幕府の滅亡をめぐる重要な出来事を振り返るクイズをご用意しました。建武の新政、東勝寺の合戦、足利尊氏の活躍など、幕府滅亡の直接的な原因や経緯を問う問題を10問収録しています。鎌倉幕府の崩壊は日本中世史における大きな転換点でした。本クイズを通して、当時の激動の歴史をお楽しみください。
Q1 : 幕府滅亡直前、鎌倉に立てこもり最後まで抵抗した北条一族の多数が自害した場所はどこか?
鎌倉幕府滅亡時、執権北条高時をはじめとする北条一族は東勝寺に立てこもり、最終的に自害しました。これは「東勝寺合戦」とも呼ばれ、北条一族終焉の地となりました。他の場所での集団自害の記録はありません。稲村ヶ崎は新田義貞が突破した場所です。
Q2 : 鎌倉幕府倒幕のきっかけとなった天皇の政策は何か?
鎌倉幕府を倒した後醍醐天皇は親政を目指して「建武の新政」を推進しました。これが幕府との対立を生み、各地で討幕運動が活発化します。承久の乱や保元の乱はそれ以前の争乱であり、永仁の徳政令は既存幕府の政策です。
Q3 : 鎌倉幕府の滅亡はどの元号の出来事か?
鎌倉幕府が滅亡した1333年は元弘(げんこう)年間にあたります。後醍醐天皇が倒幕の挙兵をした時期で、「元弘の乱」などとも呼ばれます。弘安は元寇の時期、正中は倒幕計画失敗の時期、延元はそれ以後の南北朝時代の元号です。
Q4 : 幕府滅亡時に起きた火災によって焼失した鎌倉の名所はどれか?
新田義貞の進軍により、北条一族が籠城・自害した東勝寺は火災によって焼失しました。鶴岡八幡宮や建長寺、円覚寺も鎌倉を代表する古刹ですが、鎌倉幕府滅亡に直接結びつくのは東勝寺です。現在も「東勝寺跡」が残っています。
Q5 : 鎌倉幕府滅亡前後、足利尊氏がとった行動として正しいものはどれか?
足利尊氏は後醍醐天皇の討幕命令に従い、京都の幕府出先機関である六波羅探題を攻め滅ぼしました。これが鎌倉幕府滅亡への大きな転機となりました。蒙古襲来や鎌倉防衛、北条氏との和睦ではなく、彼の活躍は京での戦闘でした。
Q6 : 鎌倉幕府滅亡時の執権・北条高時の最期について正しい記述はどれか?
1333年、幕府が新田義貞軍によって攻め落とされた際、執権・北条高時は東勝寺で一族らとともに自害しました。これにより北条氏を中心とする幕府体制は完全に終焉を迎えました。戦死や流罪、脱出といった記録はなく、自害が定説です。
Q7 : 後醍醐天皇はどのような政策を目指していたか?
後醍醐天皇は自ら親政を行うことを目指し、皇政復古(朝廷が直接統治する体制の回復)を掲げました。幕府打倒後の建武の新政はその試みでした。院政の復活や武家政権の維持とは目的が異なり、公地公民制はこれより古い律令制に由来します。
Q8 : 1333年、鎌倉幕府を滅ぼした武将は誰か?
鎌倉幕府は1333年に、後醍醐天皇の討幕命令を受けた新田義貞が鎌倉を攻め落として滅ぼしました。源義経や北条政子はそれよりずっと前の人物、足利義満は室町幕府の第3代将軍です。新田義貞の功績は、幕府滅亡への直接的な decisive action です。
Q9 : 鎌倉幕府の最後の将軍は誰か?
鎌倉幕府の最後(第14代)の執権は北条高時であり、源頼朝や北条泰時は以前の幕府の有力者です。将軍としては実質的には6代目守邦親王が最後ですが、実権は北条高時でした。足利尊氏は、幕府を滅ぼした側で初代室町幕府将軍です。
Q10 : 鎌倉幕府の滅亡につながった出来事はどれか?
鎌倉幕府の滅亡の直接的原因となったのは1333年の建武の新政です。後醍醐天皇が討幕運動を起こし、足利尊氏や新田義貞らが幕府軍を破って鎌倉を攻略し、幕府は滅亡しました。元寇や承久の乱も重要な事件ですが、いずれも幕府の崩壊には直結しませんでした。南北朝の動乱は鎌倉幕府滅亡後に発生した内乱です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は鎌倉幕府の滅亡クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は鎌倉幕府の滅亡クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。