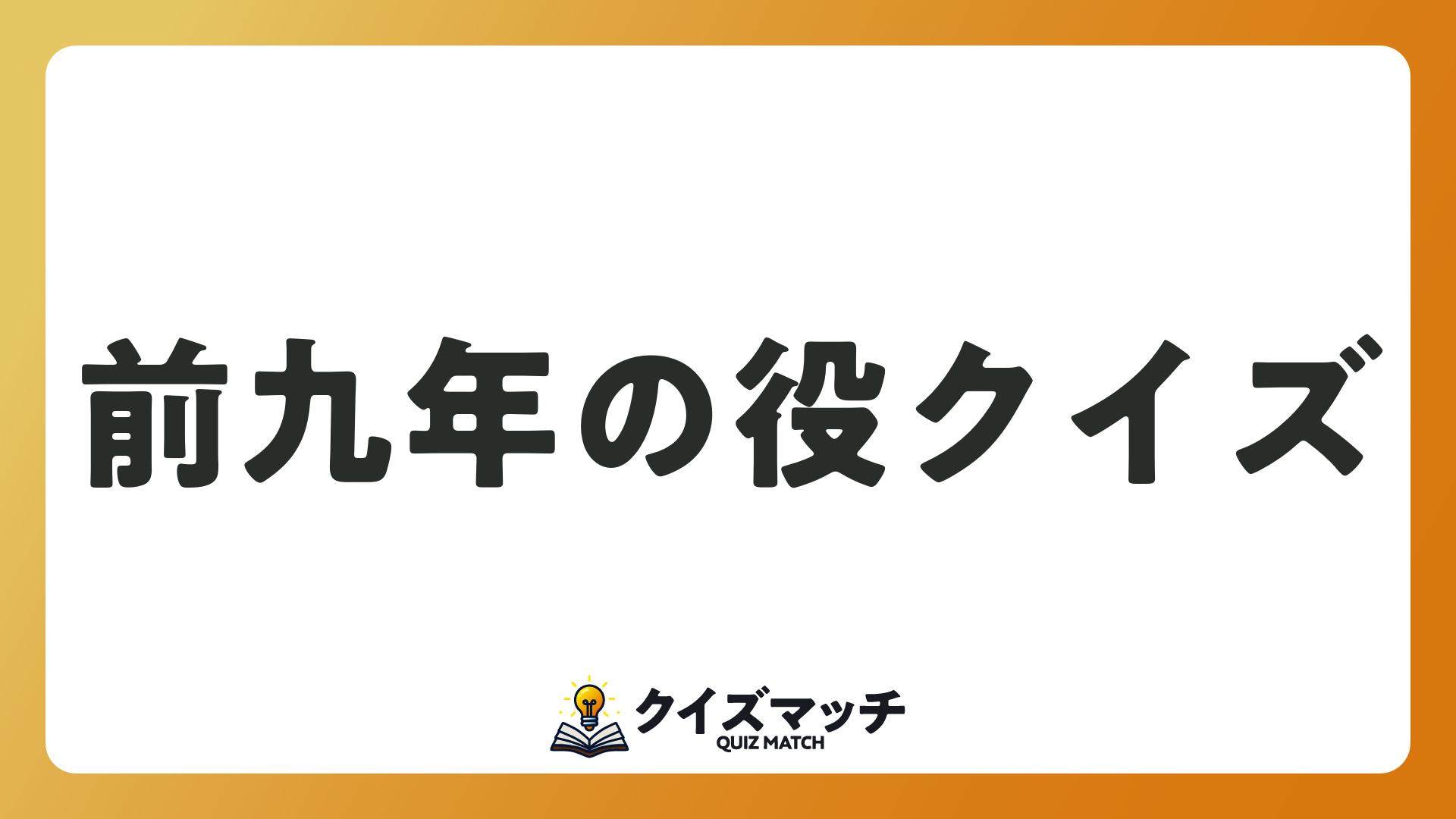前九年の役は、平安時代中期の1051年から1062年まで、陸奥国(現在の東北地方)で起きた戦いです。源頼義・義家親子が朝廷側の武士として、陸奥守として戦い、反乱を起こした安倍氏(安倍頼時・貞任ら)との間で長期にわたる戦となりました。12年にわたるこの戦争は、後の東北地方の支配構造にも大きな影響を与えました。
Q1 : 前九年の役の後、東北地方の支配権を握った清原氏の後裔が築いた政権は何と呼ばれるか?
前九年の役後、安倍氏滅亡とともに東北地方を支配したのは清原氏です。その後、清原氏の後裔である藤原清衡が奥州藤原氏政権を築きました。平泉の文化で有名な奥州藤原氏は、後の東北の歴史や日本史に大きな影響を与える一大政権を作り上げました。
Q2 : 前九年の役の意義として最も正しいものはどれでしょうか?
前九年の役の最大の意義は、朝廷が東北地方に対する支配力を再確認し、同時に源氏等東国武士の実力が認められたことです。武士の台頭を示す代表的な出来事であり、ここから後の源氏や平氏といった武家政権につながる重要なターニングポイントの一つとなります。
Q3 : 安倍氏が勢力を広げていた東北地方の現在の都道府県として最も該当するものはどれか?
安倍氏が特に勢力を誇っていたのは現在の岩手県および宮城県の一部です。厨川や衣川などの地名も現在の岩手県にあります。東北地方一帯を支配下に置くほどの実力をもち、この地で源頼義や清原武則等と戦いました。
Q4 : 前九年の役の安倍氏の討伐軍として協力した、後に奥州藤原氏につながる豪族は誰ですか?
安倍氏討伐軍に加わって活躍したのは、豪族・清原武則です。清原武則は安倍氏に対抗する重要な勢力であり、彼の参戦で戦局が大きく動きました。戦後、清原氏が奥州を支配し、やがて清原家衡の子孫から奥州藤原氏が登場します。
Q5 : 前九年の役で朝廷側として活躍した源頼義と共に戦った息子は誰でしょうか?
源頼義の息子であり、共に前九年の役で奮戦したのは源義家です。義家はこの戦で若くして名声を高め、「八幡太郎義家」として後世に称えられるようになります。義家の活躍は源氏一門の武勇伝となり、後の源氏栄光の礎となりました。
Q6 : 前九年の役のきっかけとなった出来事は何ですか?
前九年の役のきっかけは、安倍氏が中央政府(朝廷)への年貢の納入を怠ったり、勝手に周辺豪族などを討って地域支配を強化し、事実上の独立状態となったことなどの反乱行為でした。このため、朝廷は陸奥守の源頼義を派遣し、安倍氏討伐を命じたのが発端です。
Q7 : 前九年の役で降伏した安倍氏の指導者、安倍貞任はどのような運命をたどったか?
安倍氏の指導者である安倍貞任は、前九年の役の最終段階、厨川柵が落とされた際に討ち死にしました。安倍貞任は勇将として名高く、民衆の支持もあったため苦戦が続きましたが、最終的に敗北し命を落とすこととなりました。この戦いで安倍氏の東北支配は終焉し、源氏の勢力が広がることにつながります。
Q8 : 前九年の役で安倍氏が根拠地としていたお城はどこでしょう?
安倍氏が前九年の役において根拠地としたのは、厨川柵(くりやがわのさく)です。厨川柵は現在の岩手県盛岡市近くにあり、最後まで安倍氏の拠点となっていました。戦いの終盤、この厨川柵が落城し、安倍一族の抗戦も終焉を迎えます。以後、この地は奥州の制圧や源氏の勢力拡大の拠点となりました。
Q9 : 前九年の役で朝廷側の大将となった源氏の人物は誰ですか?
前九年の役で朝廷側の大将に任命されたのは源頼義です。頼義は源氏の棟梁として東国に派遣され、陸奥守に任ぜられ、陸奥国の反乱軍(安倍氏)討伐の指揮を執りました。息子の源義家もともに戦いましたが、義家はまだ若かったため補佐的立場でした。源頼義の戦功は源氏の名声を高め、後世に大きな影響を残すこととなりました。
Q10 : 前九年の役は、何年から何年まで続いた戦いでしょうか?
前九年の役は、平安時代中期の1051年から1062年まで、陸奥国(現在の東北地方)で起きた戦いです。源頼義・義家親子が朝廷側の武士として、陸奥守として戦い、反乱を起こした安倍氏(安倍頼時・貞任ら)との間で長期にわたる戦となりました。12年にわたるこの戦争は、後の東北地方の支配構造にも大きな影響を与えました。
まとめ
いかがでしたか? 今回は前九年の役クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は前九年の役クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。