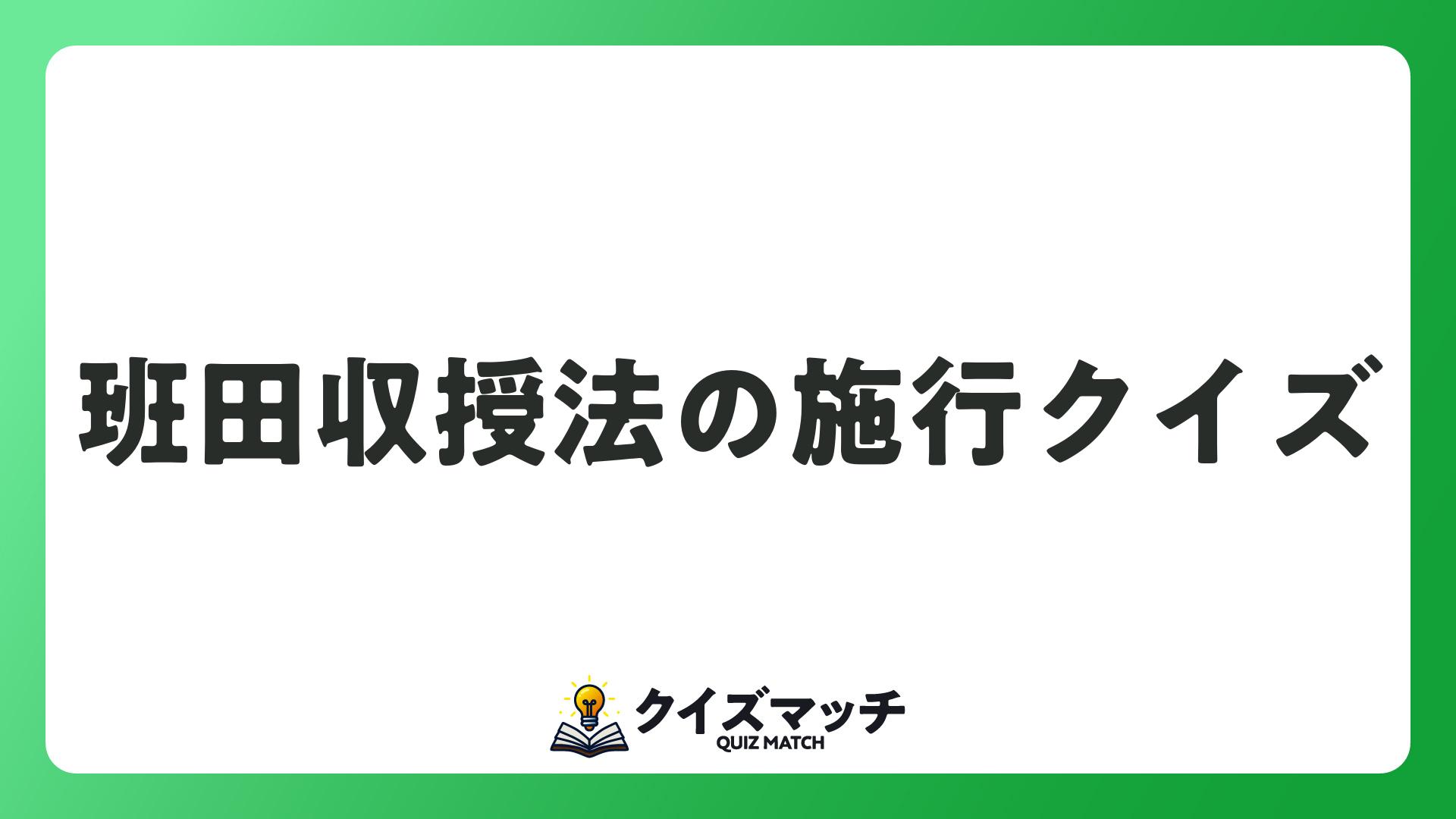奈良時代に誕生し、律令国家の基幹制度であった班田収授法。この制度は、全国民に対して土地を公平に分配し、農業生産の維持と税収確保を目的としていました。史上初の本格的な土地改革と言えるこの制度について、当時の仕組みや特徴を問う10問のクイズをお送りします。奈良時代から平安時代にかけての稲作経済と社会構造の変遷を、このクイズを通して理解を深めていただければと思います。
Q1 : 班田収授法で配分される口分田の面積の単位として使われたのはどれですか?
班田収授法で配分される口分田は「段(たん)」という単位で表されました。成人男性は2段、女性は1段が標準でした。反や町も土地単位ですが、この制度では「段」が基準とされていました。
Q2 : 班田収授法が次第に機能しなくなった理由のひとつはどれですか?
班田収授法は、墾田永年私財法などの政策により私有地(荘園)が増加したことで、口分田として分配できる土地が減り、制度そのものが維持できなくなりました。これが律令制衰退の主な要因の一つです。
Q3 : 6年ごとの班田で、田地の割り当てに使われた土地制度を何と呼びますか?
班田収授法の施行にあたり、土地を条里ごとに区画する条里制(じょうりせい)が採用されました。条里制では正方形の区画を作ることで、班田を効率よく分配しやすくしたのが特徴です。飛鳥時代の終わりごろから導入され始めました。
Q4 : 班田収授法の下で土地を割り当てられた場合、負担しなければならなかった税は何ですか?
班田収授法による土地割り当て(口分田)を受けた場合、その土地の価値に応じて米を納める税(租)が課されました。租は律令制度下の基幹税で、班田収授法と密接に結びついています。庸や調は労働や特産品に対する税です。
Q5 : 班田収授法により支給された田地の所有権はどう定められていましたか?
班田収授法により支給された田地は私有財産ではなく、世襲することも認められていませんでした。あくまで国家が割り当てる土地で、耕作する権利のみが認められました。一定期間が経ったり、受給理由がなくなると田は収公されました。
Q6 : 女性が受け取る口分田の面積は男性の何分の何と定められていたでしょうか?
女性が受ける口分田の面積は、男性の半分(1/2)と定められていました。男女別に割り当てられ、成人男性は2段、女性は1段でした。これにより、社会的役割や労働力の違いを反映して配分されていました。
Q7 : 口分田の支給に年齢制限が設けられていました。受給停止年齢は何歳でしょうか?
班田収授法では、6歳以上が口分田を受ける対象となり、60歳になるとその受給資格を失い、口分田を返還する仕組みでした。老人には田の耕作が困難になると考えられたためです。この年齢制限が社会保障的な役割も果たしていました。
Q8 : 6歳以上の男女に与えられた田地のことを何と呼びますか?
班田収授法で6歳以上の男女に与えられる田地は口分田と呼ばれました。口分田は人口に応じて一人一人に一定の面積が分け与えられる土地で、一定の年齢で収公される仕組みでした。これにより農業生産の基盤を維持しました。
Q9 : 班田収授法では、戸籍を基準に班田が行われましたが、戸籍は何年ごとに作られましたか?
班田収授法においては、人々に土地を分け与える際に戸籍を基準としました。この戸籍の作成は6年ごと(六年一造)に行われ、その情報を元に土地の再配分が行われました。これにより人口の変動に対応して公平な班田を実現しました。
Q10 : 班田収授法が施行されたのは、どの時代でしょうか?
班田収授法は、律令制の初期に施行された法律で、特に奈良時代の代表的な制度です。この制度は、全国民に対して土地を公平に分配し、農業生産を維持および税収を確保するためのものでした。最初に実際に施行されたのは大宝律令が整えられた奈良時代です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は班田収授法の施行クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は班田収授法の施行クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。