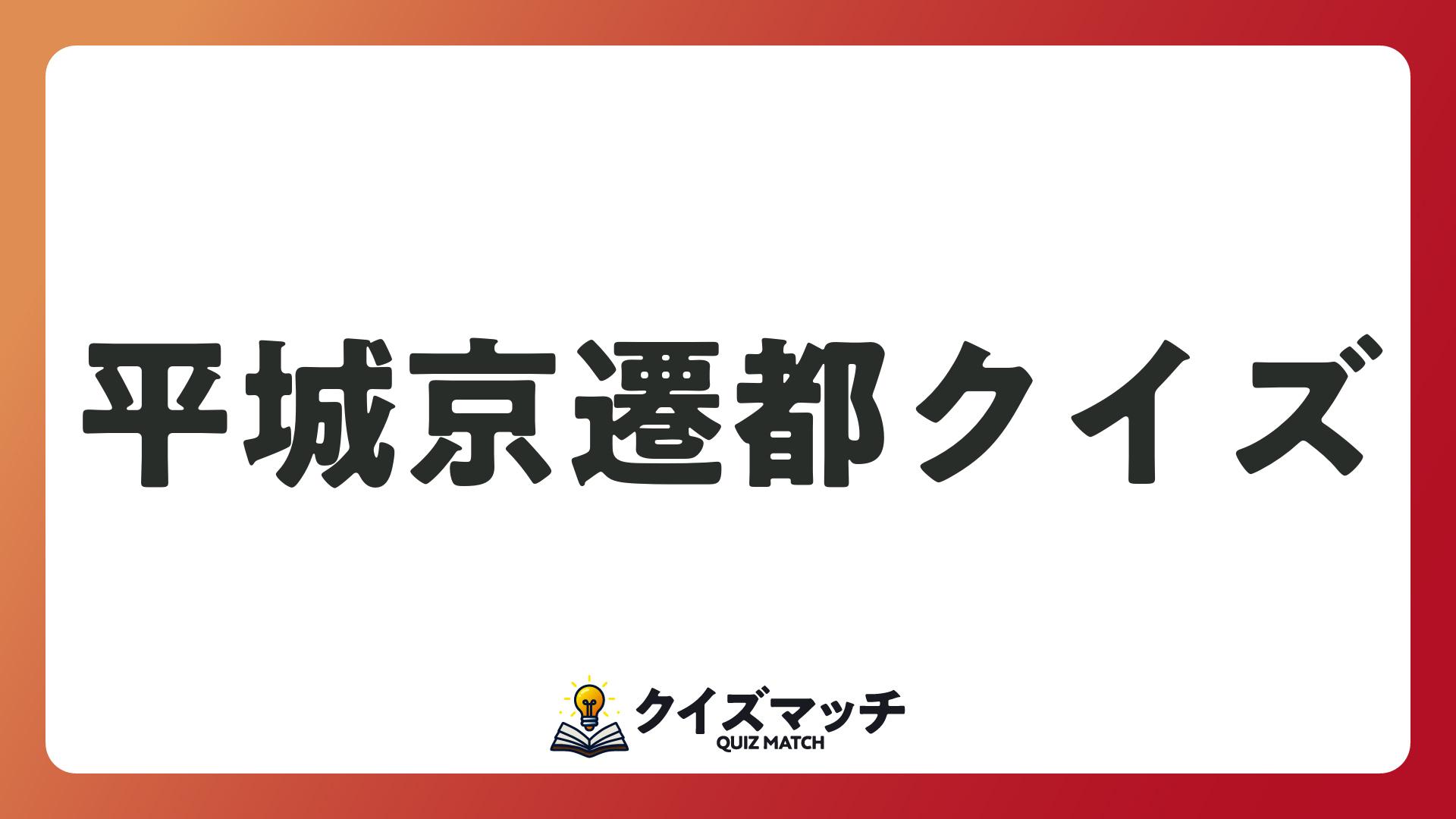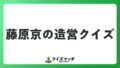平城京への遷都は710年(和銅3年)に行われました。元明天皇の時代であり、それまでの藤原京から新たな都として移されたのが平城京です。平城京の都は、中国の長安をモデルにして計画的に建設されました。律令制国家の確立を目的とした平城京遷都は、政府機構の整備や交通網発達の基礎を築きました。この記事では、平城京遷都にまつわる10の興味深いクイズをお楽しみいただけます。
Q1 : 平城京遷都後、仏教が盛んになったきっかけともなった巨大仏教建築はどれ?
東大寺は、奈良時代を代表する大寺院であり、聖武天皇が国家安泰を祈願して建立を発願しました。大仏もこの東大寺に納められました。平城京遷都後に仏教が国家的に重視される中、大仏建立が大きな象徴となりました。他の寺院も有名ですが、大仏と結びつきが強いのは東大寺です。
Q2 : 奈良時代初期、平城京に建てられた電飾のある有名な門はどれでしょう?
朱雀門(すざくもん)は、平城京の正門として知られる門です。都の南側正面に位置し、都城の象徴でもありました。羅生門や応天門は平安京の門、大極門は平城宮の門ですが、都全体の正門としては朱雀門です。
Q3 : 平城京から使節団などが派遣されて交流のあった国はどれでしょう?
平城京時代、日本は遣唐使や遣新羅使などを送り、朝鮮半島の新羅と交流しました。高麗・モンゴルは時代が異なり、朝鮮という表現は当時の国名ではありません(新羅が当てはまります)。
Q4 : 平城京の造営時に行われた、役人に土地を給付する仕組みは何ですか?
班田収授法は、律令体制下で人々に耕作地(口分田)を定めた期間ごとに与える制度です。奈良時代初期、平城京造営の時代の基幹制度です。三世一身法や墾田永年私財法は後年のもの、口分田制は班田収授法の具体化にあたります。
Q5 : 次のうち平城京遷都と同じく和銅年間に起こった出来事はどれでしょう?
和同開珎(わどうかいちん)と呼ばれる日本最初期の流通貨幣は、和銅年間(708年~)に鋳造・流通が始まりました。平城京遷都もほぼ同時期であり、経済基盤の強化が進められました。大仏建立は8世紀半ば、仏教伝来は6世紀半ば、蘇我氏滅亡は645年です。
Q6 : 平城京のあった現在の都道府県はどこでしょう?
平城京は現在の奈良県奈良市にあたります。平城宮跡は現代でも奈良市に存在しており、世界遺産「古都奈良の文化財」の一部となっています。京都府は平安京、他は都の所在地ではありません。
Q7 : 平城京遷都の目的と密接な関係があるのは次のうちどれでしょう?
平城京遷都の大きな目的は律令制国家の体制を強化・確立するためでした。律令制の下で国の統治体制を整え、中央集権化を進める必要があったのです。農業の振興や仏教の排除(むしろ仏教の発展はこの頃進む)、神道の発展直接の要因ではありません。
Q8 : 平城京のモデルとなった中国の都はどこでしょう?
平城京の都市設計のモデルは、中国の唐の都である長安です。長安は碁盤の目のような整然とした都市計画で知られ、平城京もこれにならって計画的に造られました。それにより政府機構の整備や交通網発達の基礎が作られました。
Q9 : 平城京を建設した天皇は誰でしょう?
平城京を建設し遷都したのは第43代元明天皇です。元明天皇は女性天皇で、都の建設を通して律令国家体制の確立を進めました。聖武天皇は後に東大寺の創建などで有名ですが、平城京建設時の天皇ではありません。
Q10 : 平城京に遷都されたのは西暦何年でしょう?
平城京への遷都は710年(和銅3年)に行われました。これは元明天皇の時代であり、それまでの藤原京から新たな都として移されたのが平城京です。平城京の都は、中国の長安をモデルにして建設されたとされています。794年は平安京遷都、645年は大化の改新、672年は壬申の乱の年です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は平城京遷都クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は平城京遷都クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。