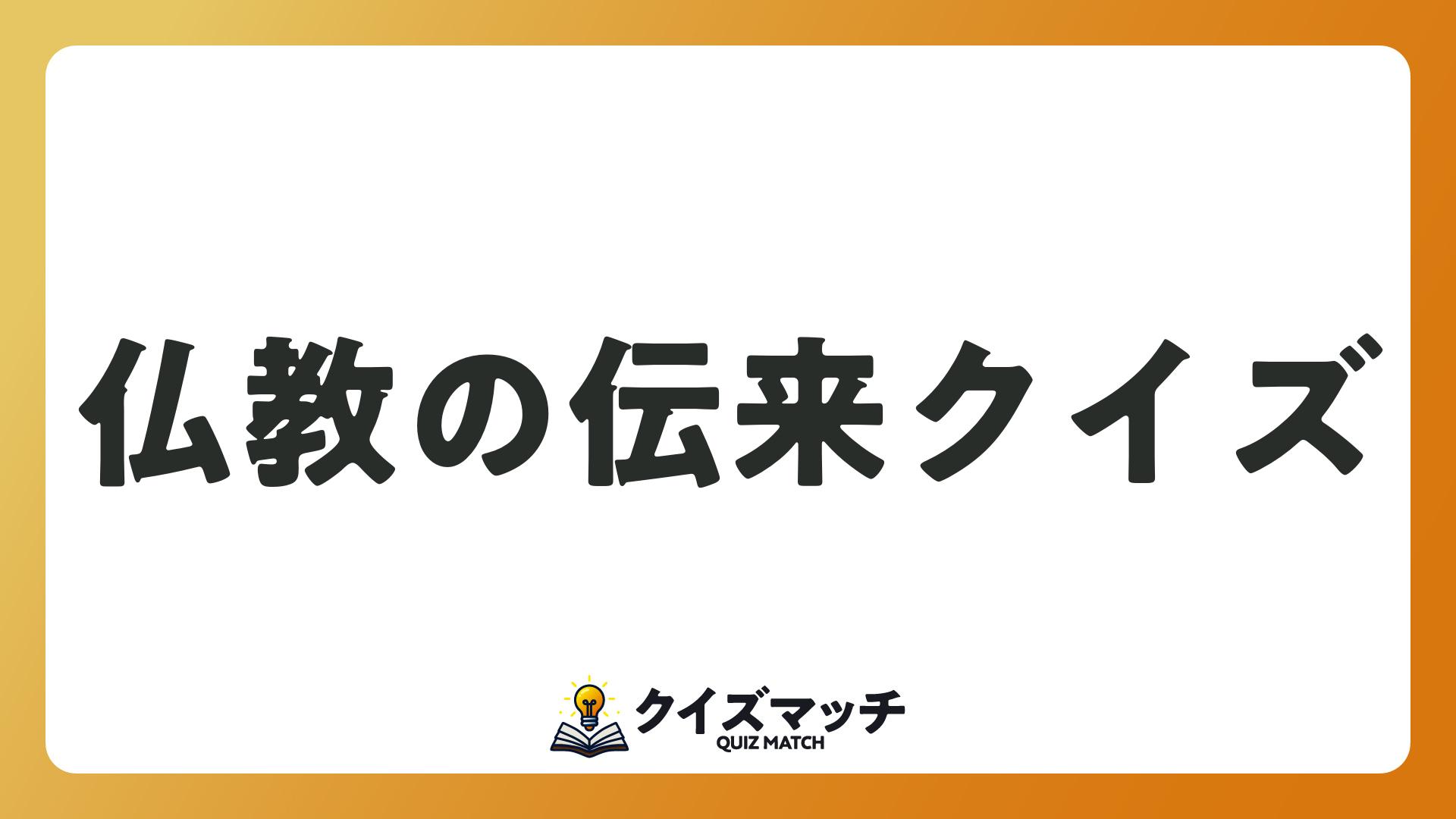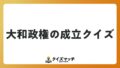日本に仏教がいつ、どのように伝わったのか、その歴史をクイズを通して楽しく学べる機会が待っています。仏教伝来の経緯や、当時の政治・社会情勢との関わりについて、さまざまな角度から見ていくことができます。仏教受容に反対した豪族の存在や、聖徳太子の仏教奨励策など、日本の歴史を深く知る上で重要なできごとが取り上げられています。仏教伝来の歴史に興味のある方は、この10問のクイズに挑戦してみてください。
Q1 : 仏教の伝来を描いた最古の公式記録はどれか?
日本への仏教伝来について最も早い時期の公式記録に『日本書紀』があります。『日本書紀』には百済からの仏像・経典の伝来や、日本における崇仏論争など詳細が記述されています。仏教伝来の年や状況についても、この資料が主要な根拠となっています。『続日本紀』や『古事記』などにも仏教関係の記述はありますが、成立時期や詳しさで『日本書紀』が現在も指標とされています。
Q2 : 聖徳太子が定めた仏教奨励のための法令はどれか?
聖徳太子は十七条の憲法の中で「篤く三宝を敬え」と仏教尊重を強調しました。三宝とは仏・法・僧を指し、国家統治の重要理念として規定され、これが日本の仏教興隆の原点となりました。聖徳太子による仏教推進策が飛鳥時代の宗教・政治両面に大きな影響を与えました。
Q3 : 仏教伝来時、日本で仏像が初めて祀られた場所はどこ?
『日本書紀』によれば、仏教伝来時に百済聖明王より贈られた仏像はまず日本の宮中に安置されました。しかしこの時、物部氏や中臣氏の反対によって仏像は川に投げ捨てられてしまったと記されます。その後、本格的な寺院建立へと至っていきますが、この話が仏教受容の困難さを物語っています。
Q4 : 奈良時代、国分寺建立の勅命を出した天皇は?
奈良時代の聖武天皇は、全国60余か国に国分寺・国分尼寺を建立することを命じました。これは仏教による国家安泰・疫病鎮護を目的としたもので、「天平の国分寺建立の詔」として知られます。最も大きな東大寺もこの時期に建立されました。
Q5 : 飛鳥寺を建立した豪族は誰か?
飛鳥寺(法興寺)は日本最初の本格的寺院とされ、蘇我氏によって建立されました。蘇我氏は仏教保護政策を推し進め、仏教施設や関連技術を積極的に導入し、飛鳥文化の発展にも寄与しました。飛鳥寺はその後も日本仏教の中心的な役割を果たしました。
Q6 : 物部氏と蘇我氏の宗教論争で最終的に勝利したのは誰か?
崇仏論争において、物部氏(物部守屋)は仏教反対派、蘇我氏(蘇我馬子)は仏教容認派でした。最終的には蘇我馬子が物部守屋を滅ぼし勝利し、仏教の受容が進みました。この勝利により、日本の社会や文化に仏教が積極的に広まる契機となりました。
Q7 : 仏教伝来時に、仏像や経典とともに日本にやってきた僧侶の名前は?
日本に仏教が伝来した際、百済から仏像や経典とともに僧侶の恵便(えべん)が派遣されました。彼は日本に仏教を伝える役割を担い、仏教理解や儀礼の指導にあたったとされています。このような外国僧の存在は、日本での仏教の受容と定着に大きく貢献しました。
Q8 : 仏教伝来後、日本で仏教の受容に反対した有力豪族はどれか?
仏教伝来当初、日本国内では仏教の受容を巡って対立が起こりました。特に物部氏は神道を重視する伝統的な勢力であり、仏教受容に強く反対しました。一方、蘇我氏は積極的に仏教を受け入れ、両者の激しい争い(崇仏論争)へと発展します。この対立は後の仏教広まりと深い関係があります。
Q9 : 仏教を日本に伝えたとされる百済の王の名は?
仏教を日本に伝えたとされるのは百済の聖明王(聖王、聖明王とも書く)です。聖明王は、日本の欽明天皇に仏像や経典、僧侶などを贈りました。この仏教の受容を巡って、日本国内では崇仏派と排仏派に分かれ、争いが生じました。聖明王の贈り物が日本に仏教文化を広げる大きな契機となりました。
Q10 : 日本に仏教が公式に伝来したとされる年はどれか?
日本への仏教伝来の年については『日本書紀』と『元興寺縁起』などで諸説ありますが、一般的には欽明天皇13年である552年とされています。『日本書紀』には百済の聖明王から仏像などをたまわったことが記述されています。538年説もありますが、多くの教科書や資料では552年説が採用されています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は仏教の伝来クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は仏教の伝来クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。