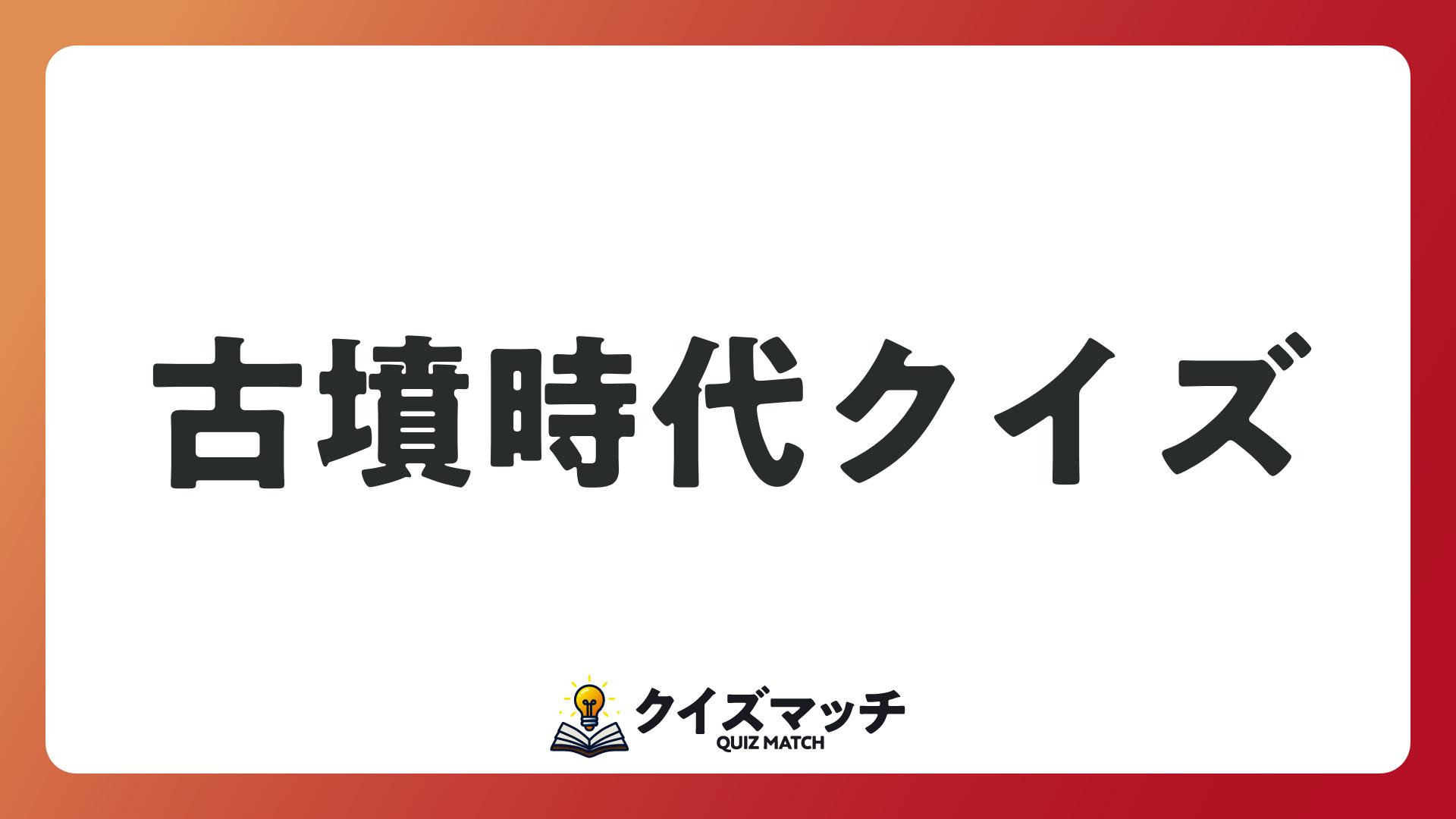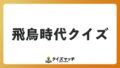古墳時代は日本の歴史の中でも特に重要な時代です。この時代、様々な形態の古墳が全国各地で築造され、当時の支配層の権力や交流関係を示す数多くの貴重な遺物が出土しています。本記事では、前方後円墳をはじめとする古墳の形態、日本最大の古墳、古墳時代の始まりと終わり、古墳に見られる副葬品や埴輪など、古墳時代の特徴的な事項について、10個の問題形式のクイズを用意しました。この古墳時代クイズを通して、古代日本の歴史に対する理解を深めていただければと思います。
Q1 : 世界遺産に登録されている「百舌鳥・古市古墳群」はどこにありますか?
ユネスコ世界文化遺産に2019年登録された「百舌鳥・古市古墳群」は大阪府に位置します。堺市(百舌鳥)および藤井寺市・羽曳野市(古市)に大規模な前方後円墳を中心とした多くの古墳が集まっています。これらは日本の古墳時代の政治勢力や文化の発展を象徴する重要な遺構群です。
Q2 : 古墳時代の人々が利用した代表的な土器は何ですか?
古墳時代の代表的な土器は土師器です。赤褐色の素焼きで、弥生土器に続く形態ですが、より大量生産されました。やがて須恵器も登場しますが、須恵器は古墳時代中期以降の特徴であり、主に前期〜中期の代表は土師器です。
Q3 : 前方後円墳が最初に築かれた地域はどこでしょう?
前方後円墳が最初に築かれたとされているのは大和地方、現在の奈良県周辺です。特に箸墓古墳(奈良県桜井市)は“最初期の前方後円墳”として有名です。その後、前方後円墳の築造は日本各地に広がりましたが、まずは大和地方から始まりました。
Q4 : 古墳時代に中国や朝鮮半島から伝わった重要な技術は何ですか?
古墳時代には大陸から多くの技術や文化が伝来しましたが、とりわけ重要なのが製鉄技術です。これにより、鉄製の武器や農具、工具の生産が日本で拡大しました。これらの鉄製品は支配構造の変化や生産力向上に大きな影響を与えました。養蚕も後の時代、印刷や火薬技術はさらに後に中国からもたらされます。
Q5 : 古墳の周囲に並べられた、祭祀や区画のために使われた素焼きの像を何と呼びますか?
古墳の周囲に立て並べられた素焼きの像は「埴輪」と呼ばれます。埴輪は、形状が人物・動物・家など多様化していき、古墳の築造時に祭祀や外部と内部の区画の役割も果たしていたと考えられています。須恵器は時代後半で使われる実用的な土器の一種、土偶は縄文時代のもの、かわらけは素焼きの皿です。
Q6 : 古墳時代の支配層が権威を表すために使った副葬品には何が多いですか?
古墳時代の支配層の副葬品としては、武器・武具などの鉄器や、中国から伝わった銅鏡が多く見つかっています。これらはその当時の支配層の権力や交流関係を示すものであり、巨大古墳の副葬品から多様な金属製品が出土します。木簡や布などはこの時代にはまだ一般的でなく、まが玉や土器は副葬品に含まれますが、権威の象徴として重要視されたのは鉄器や銅鏡です。
Q7 : 古墳時代の終わりは何によって区切られることが多いでしょうか?
古墳時代の終わりは、おおむね飛鳥時代(7世紀後半)の開始で区切られます。仏教伝来や律令国家体制の形成といった文化・政治の大きな変革によって古墳築造が衰退したためです。奈良時代や大和政権の滅亡ではなく、6世紀後半から7世紀初頭の飛鳥時代の到来が一つの目安となります。
Q8 : 古墳時代の始まりは約何世紀ごろとされていますか?
古墳時代の始まりは、3世紀ごろと考えられています。大量の古墳が作られ始め、特に大型の前方後円墳が出現した時期です。魏志倭人伝に見られる卑弥呼の時代と重なることも多く、弥生時代の後期から続く社会的変革の一環とされています。
Q9 : 日本最大の古墳は次のうちどれでしょう?
日本最大の古墳は大阪府堺市にある大仙陵古墳(大山古墳、仁徳天皇陵とも言われます)です。全長約486メートルというスケールで、クフ王のピラミッド、秦の始皇帝陵と並ぶ世界三大墳墓の一つとされています。他の選択肢も大型古墳ですが、大仙陵古墳が最大規模です。
Q10 : 古墳時代に最も多く造られた古墳の形は何ですか?
古墳時代には様々な形状の古墳が造られましたが、最も多いのは前方後円墳です。前方後円墳は、前方部が四角く、後円部が丸い特徴的な形をしています。4世紀から6世紀にかけて日本各地で盛んに築造され、特に大和政権の勢力下で多く見られます。円墳や方墳も存在しますが、規模や数、社会的な重要性から前方後円墳がもっとも代表的です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は古墳時代クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は古墳時代クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。