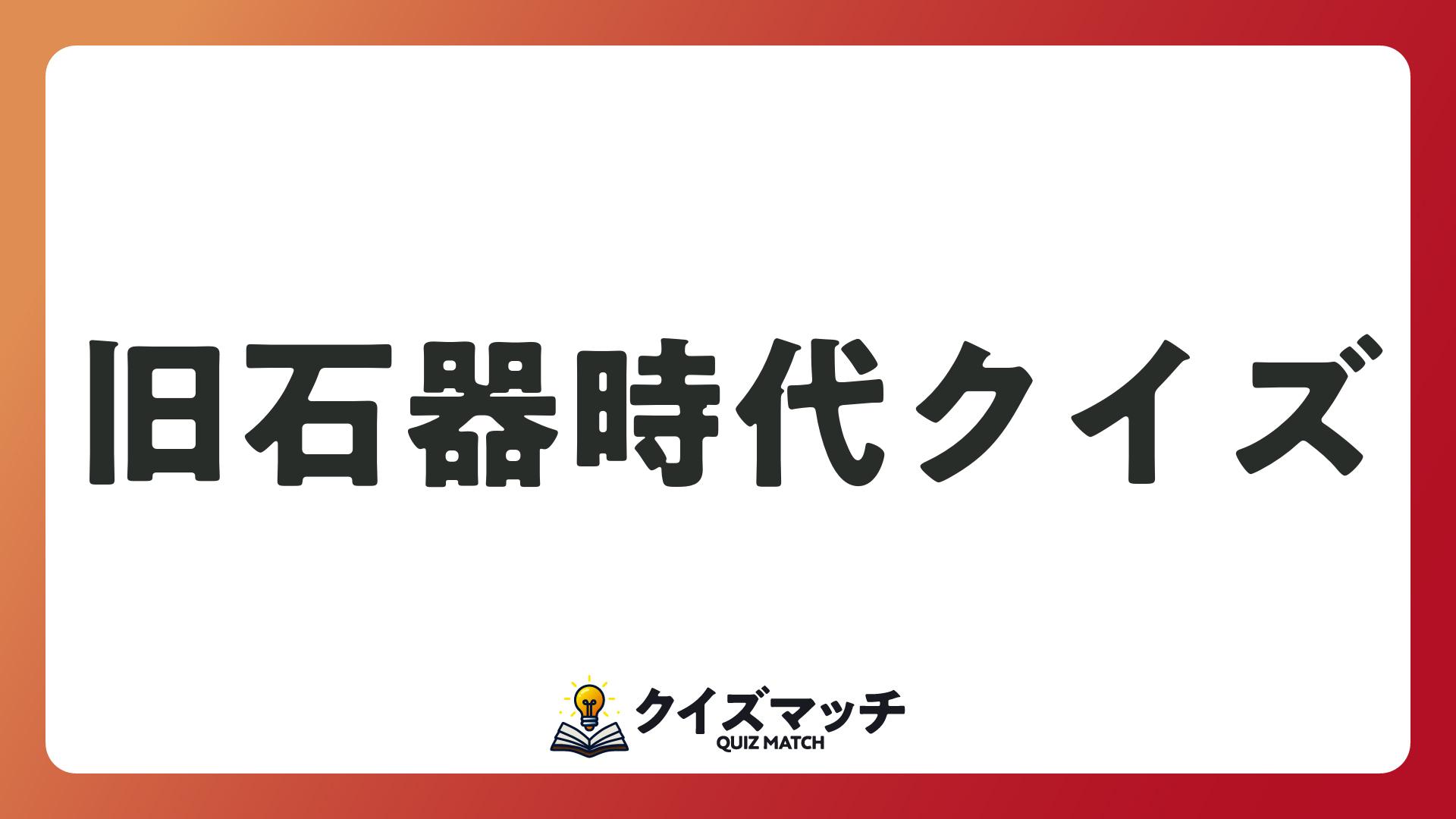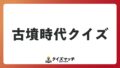旧石器時代のさまざまな特徴や発見について解説する本記事では、最新の考古学的研究をもとに、その起源や石器の特徴、生活様式、主な遺跡などについて、10問のクイズを通して理解を深めていきます。これらの問題に答えることで、日本列島における旧石器時代の歴史と文化を丁寧に探っていきます。新たな発見や研究の進展によって、従来の見方が変わってきている点にも注目しながら、過去から現在につながる人類史の一端を学んでいきましょう。
Q1 : 旧石器時代の人類が生きていた時代区分はどれか?
旧石器時代の人類は約260万年前から約1万年前の更新世(第四紀)に生きていました。完新世は約1万年前から現在に至るまで、更新世の後の時代です。白亜紀や三畳紀は恐竜の時代で、人類はまだ登場していません。
Q2 : 旧石器時代の人類が火を使っていた証拠として日本国内で発見されたものは何か?
旧石器時代の遺跡からは、火を使った痕跡として炉穴跡や炭化した木片などが発見されており、人類がすでに火を利用していたことがわかります。水田跡はもっと新しい弥生時代のもの、土偶は縄文時代以降、製鉄炉は古墳時代以降に登場します。
Q3 : 旧石器時代の遺跡でよく出土する、石を打ち割って作られた鋭い刃を持つ石器の名称は?
旧石器時代の遺跡からよく出土する、鋭い刃を持つ石器はナイフ形石器です。これは木や骨、肉などの加工に用いられたと考えられています。石鏃は弓矢の矢じりとして使われますが、主に縄文時代以降に出現します。石包丁は弥生時代、土偶は縄文時代の信仰具です。
Q4 : 日本列島の旧石器時代に見られる『細石器』とはどのようなものか?
細石器とは、細長く尖った形の石刃片を作り出し、木の棒などに埋め込んで刃物や道具として使った石器です。この石器は後期旧石器時代に広く見られ、日本でも北海道、東北などでよく発見されています。骨や木で作られた道具、大型打製石器、磨製石器とは異なるものです。
Q5 : 旧石器時代人が主に使っていた住居形式は?
旧石器時代はまだ定住生活が確立する前の狩猟採集時代であり、洞窟や岩陰などの自然の地形を利用した穴居生活が中心でした。竪穴住居は縄文時代やそれ以降の定住生活の発展した時期に見られます。高床倉庫や土塀の家も旧石器時代には存在しない形式です。
Q6 : 旧石器時代の終わりと縄文時代の始まりを区分する特徴的な発明・発見は何か?
旧石器時代と縄文時代の大きな違いは、磨製石器と土器の使用開始です。これらは縄文時代の特徴とされ、旧石器時代はあくまで打製石器しか使っていません。青銅器や鉄器はさらに新しい時代で使われ、馬の家畜化もずっと後のことです。
Q7 : 日本で初めて発見された旧石器時代の遺跡はどれか?
日本で初めて発見・認知された旧石器時代の遺跡は群馬県の岩宿遺跡です。1946年に相沢忠洋によって打製石器が発見され、日本にも旧石器時代があったことが明らかになりました。他の選択肢である三内丸山遺跡、吉野ヶ里遺跡、登呂遺跡は、いずれも縄文時代あるいは弥生時代の遺跡です。
Q8 : 旧石器時代の人々の主な生活方法は何か?
旧石器時代の人々は、定住した農耕や牧畜を行う前の時代に暮らしており、主に野生動物の狩猟や野草・木の実の採集によって生活していました。稲作などの農耕は縄文時代や弥生時代に始まるため、旧石器時代にはまだ行われていません。都市生活もこの時代には存在しません。
Q9 : 日本の旧石器時代に特徴的な石器として発達したものはどれか?
日本の旧石器時代は、主に打製石器が使われていた時代です。石を打ち欠いて鋭い刃を作り、狩猟や作業に利用していました。磨製石器は縄文時代以降に発展した石器で、旧石器時代には登場しません。また青銅器や鉄器は弥生時代以降に導入・製作されるようになります。
Q10 : 日本列島の旧石器時代のおおよその始まりは、今からどれくらい前と考えられているか?
最新の考古学的研究によると、日本列島の旧石器時代の始まりは約3万5千年前頃とされています。かつては約1万8千年前頃(遺跡の出土状況など)ともされていましたが、更新世後期の石器の発見や遺跡調査の進展により、より古い年代に遡ることが明らかになりました。他の選択肢は新石器時代の始まりや、旧い時期と最新の研究成果に合致しない年数です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は旧石器時代クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は旧石器時代クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。