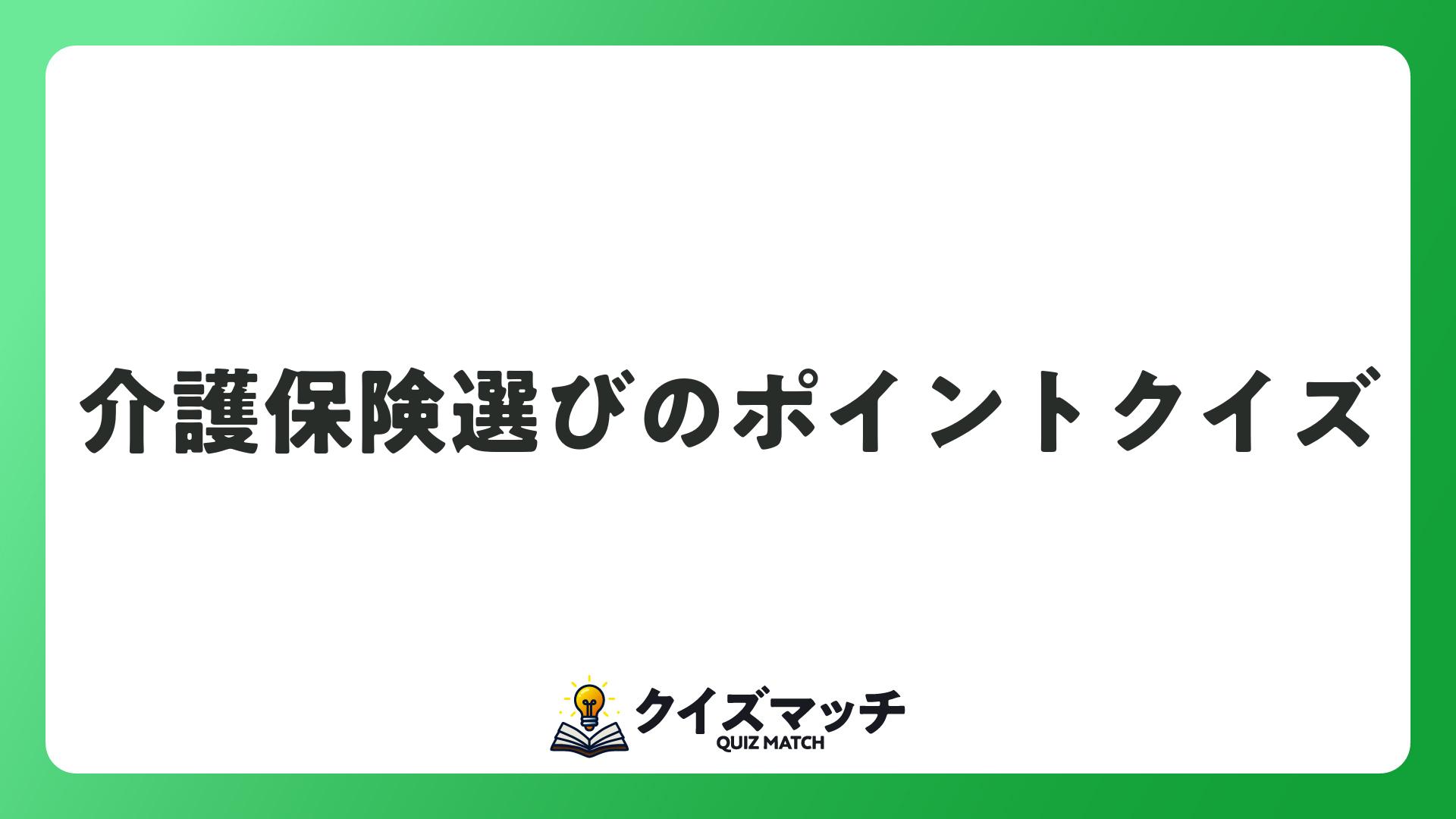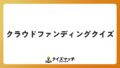介護保険の選び方について知っておきたいポイントを10問のクイズでご紹介します。介護サービスを利用する前に、加入条件や自己負担割合、支援の仕組みなど、さまざまな面から理解を深めましょう。これらの知識を持っていれば、自分にぴったりのサービスを見つけられるはずです。介護保険の基本をしっかりチェックして、安心して制度を活用できるよう準備しましょう。
Q1 : 地域包括支援センターが主に担当している支援は何ですか?
地域包括支援センターは、主に要支援者や高齢者の総合相談・ケアマネジメントを担当しています。その他、虐待防止や権利擁護、地域ネットワーク作りにも関与します。施設入所手続きや医療費支払い、保険料徴収は本来の業務ではありません。
Q2 : サービス付き高齢者向け住宅の家賃や食費は介護保険の給付対象か?
サービス付き高齢者向け住宅において、家賃や食費など生活費部分は介護保険の給付対象になりません。介護保険で賄えるのは、介護サービス利用料部分のみです。家賃や食費は自己負担することになるため、費用計画に注意が必要です。
Q3 : 介護保険で利用できるサービスに含まれないものはどれですか?
介護保険で利用できるのは生活支援・介護サービスで、医療行為(治療)は原則含まれていません。医療は医療保険の範疇です。住宅改修や訪問サービス、デイサービスなどは介護保険によりカバーされますが、治療そのものは対象外です。
Q4 : ケアプランの作成費用は原則誰が負担しますか?
ケアプラン(介護サービス計画)の作成費用は介護保険から全額給付され、利用者負担はありません。したがって、安心してケアマネジャーに相談可能です。これも介護保険の重要な特徴の一つです。
Q5 : 介護保険サービスを利用するには、最初にどのプロセスが必要ですか?
どの介護サービスでも、まず『要介護認定の申請』が必要です。これにより、利用可能なサービスや支給限度額が明確になります。ケアマネジャーの選定や施設相談は、その後の流れです。認定申請なしでは保険給付対象となりません。
Q6 : 40歳から64歳までの第2号被保険者が介護保険のサービスを受ける条件で誤っているものは?
40~64歳の第2号被保険者が介護保険を利用できるのは、特定疾病(主に16種類)が原因で介護が必要となった場合です。交通事故など特定疾病以外の理由では利用不可です。医師の診断は必要ですが、条件とは直接一致しません。
Q7 : 要介護認定の更新申請は、認定期間満了のどのくらい前から申請可能ですか?
要介護認定の更新申請は、認定期間が切れる2か月前から行うことができます。これにより、継続してサービス利用が途切れないよう配慮されています。申請忘れや遅れがあると、サービスに支障が生じる場合があるので、残り期間に注意して手続きを進めましょう。
Q8 : 介護保険サービス利用時の自己負担原則はどうなっていますか?
介護保険サービスを利用する場合、基本的な自己負担は原則1割です。ただし、所得に応じて2割または3割となることもあります。残りの9割分は公費および保険料でまかなわれます。所得要件による負担割合の見直しが数年ごとに行われています。
Q9 : 要介護認定を受けるために申請する先として最も正しいのは?
介護認定の申請は、住民票のある市区町村の窓口で行います。市区町村が認定窓口となり、申請後は調査や主治医意見書などを基に審査判定が行われます。福祉事務所や地域包括支援センターも相談はできますが、正式な申請先は市区町村だけです。
Q10 : 介護保険の加入年齢は通常何歳から始まりますか?
介護保険は原則として40歳から加入が始まります。第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳~64歳)に分類され、保険料の支払いが義務付けられています。老後の備えとして、40歳になったら自動的に保険に組み込まれますが、知らずにいるケースも多いので注意しましょう。
まとめ
いかがでしたか? 今回は介護保険選びのポイントクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は介護保険選びのポイントクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。