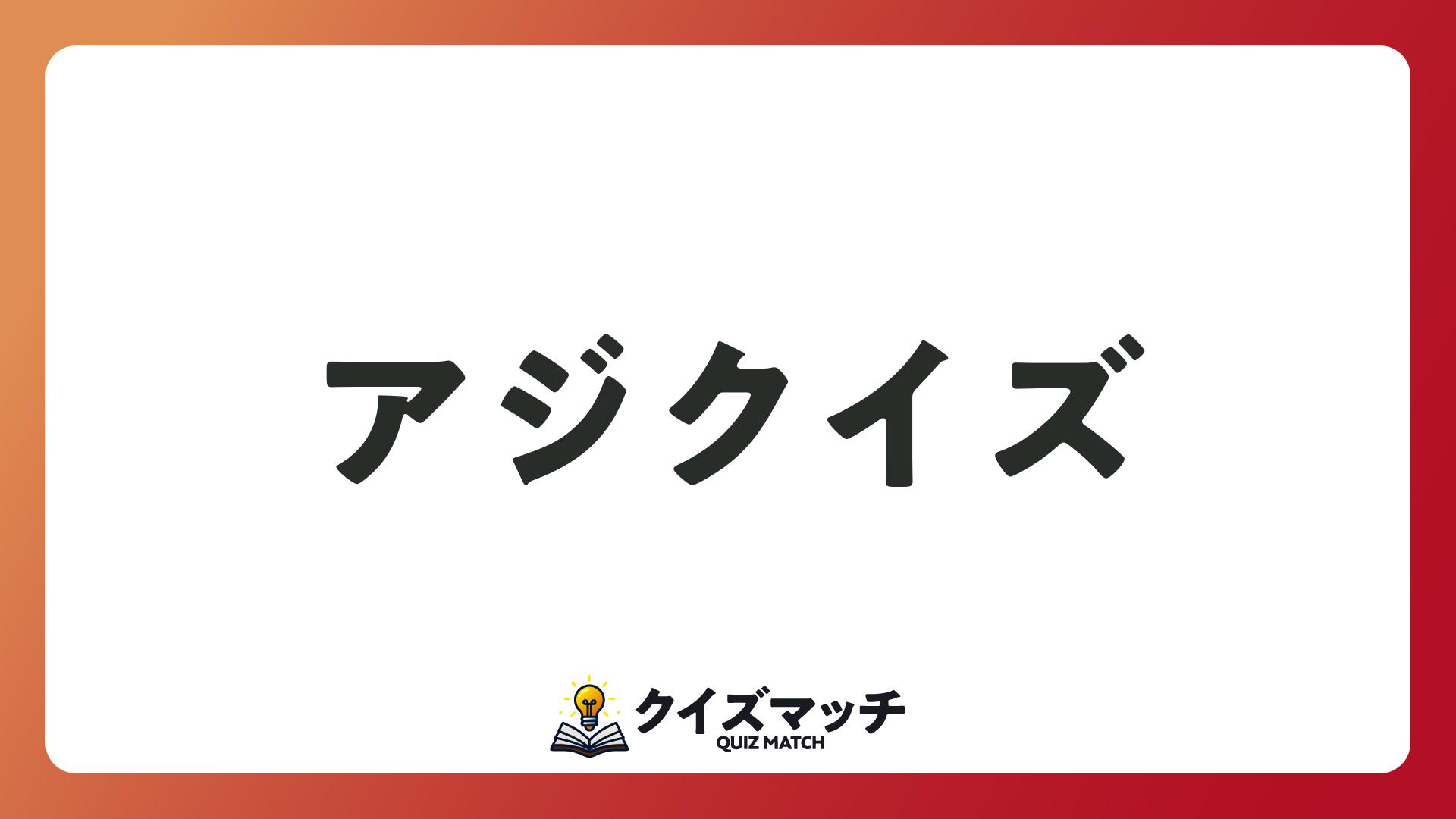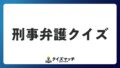アジは日本人に馴染み深い魚の一つで、特に夏が旬とされています。刺身やフライ、酢締めなど多様な調理法で楽しめ、種類によってはブランド品扱いされることも。アジの特徴的な黄色い線や骨、DHA・EPA含有量など、アジについて知っておきたい基礎知識を10問のクイズで確認できます。日本のアジ文化を深く理解するための、興味深い情報が満載の記事となっています。
Q1 : 日本において、アジはどのような漁法で最も多く獲られている?
日本ではアジの漁獲方法として「巻き網漁」が最も多く用いられています。巻き網は大きな網で魚群を一気に囲い込む方法で、大量の小型〜中型魚を効率的に捕獲できます。定置網や一本釣りもありますが、漁獲量の観点では巻き網が圧倒的です。
Q2 : マアジと呼ばれるアジの学名はどれ?
マアジの学名は「Trachurus japonicus」です。Scomber japonicusはサバ、Caranx melampygusはギンガメアジ、Seriola quinqueradiataはブリの学名です。学名は分類の基本情報ですが、魚好きなら覚えておくとちょっとした自慢になるポイントでもあります。
Q3 : アジの刺身を作る際、必ず取り除く部分はどれ?
アジの背中側にある硬いうろこ状の部分を「ゼイゴ」と呼びます。ゼイゴはとても固く、そのままでは食べにくいので、刺身やタタキをつくるときに必ず包丁で切り取ります。これはアジ特有の下処理であり、料理初心者でも覚えておきたいポイントです。
Q4 : アジのDHA・EPA含有量は魚類の中でどう評価される?
アジはDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)といった高度不飽和脂肪酸を多く含みます。魚類の中でも含有量は多い部類で、健康食品やサプリメントにも使われるほどです。これらの成分は脳の発育や生活習慣病予防に効果があるため、積極的に摂取したい魚として推奨されています。
Q5 : アジのブランド産地として有名な場所はどこ?
大分県の佐賀関(さがのせき)で水揚げされる「関アジ」は日本を代表するブランドアジです。身が締まり脂がのっていて高値で取引されることが多いです。氷見(富山県)のブリ、金華山沖(宮城県)の金華サバなど、有名なブランドがありますが、アジでは「関アジ」が特に有名です。
Q6 : アジの骨について正しい説明はどれ?
アジは頭部から尾にかけて中骨があり、この骨はとても鋭いのが特徴です。とくにゼイゴ(背側のかたいウロコ状の部分)や中骨は未調理だと食べにくく、調理時に丁寧に取り除く必要があります。骨が柔らかいということはなく、小骨も多いため自宅で調理の際は怪我に注意が必要です。
Q7 : アジが多く獲れる日本の海域はどこ?
アジは非常に広範囲に分布していますが、特に太平洋沿岸(千葉県から鹿児島県、四国・九州沿岸など)は全国的に生産量が多いことで有名です。温暖な海域を好み、産卵や餌が豊富な外洋や沿岸域を回遊します。日本海でも獲れますが、全国生産でみると太平洋沿岸が一番多いです。
Q8 : アジの代表的な調理法でないものはどれ?
アジは脂質が多く、刺身やタタキ、なめろう、酢締め、フライなど、多様な調理法で食されます。しかし煮物として出されることは少なく、煮てしまうと身が崩れやすく味も淡泊になりやすいため、あまり一般的とはいえません。焼きものや揚げもの、酢締めなどが主流の食べ方です。
Q9 : アジの仲間で体側に一本黄色い線が走る特徴を持つものはどれ?
キアジは成魚になると体側に一本黄色い線が走るため、その名前がついています。マアジにも黄色線はありますが、キアジほど鮮明ではありません。一般的に「アジ」と呼ばれるのはマアジですが、黄アジは美味で産地によってブランド扱いされることも多いです。ムロアジやシマアジもアジ科ですが、この特徴的な黄色い線はありません。
Q10 : アジ(鯵)の旬は日本で一般的にいつと言われている?
アジ(鯵)の旬は一般的に初夏から夏(5月〜7月ごろ)とされています。アジは回遊魚で、産卵前の脂がのった時期が最も美味とされ、日本では夏が旬と位置づけられています。特に真アジはこの時期が味も良く、値段も高くなります。旬のアジは刺身や寿司、焼き物として高級料亭でも使われるほどで、日本人にとって非常に馴染み深い魚です。
まとめ
いかがでしたか? 今回はアジクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はアジクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。