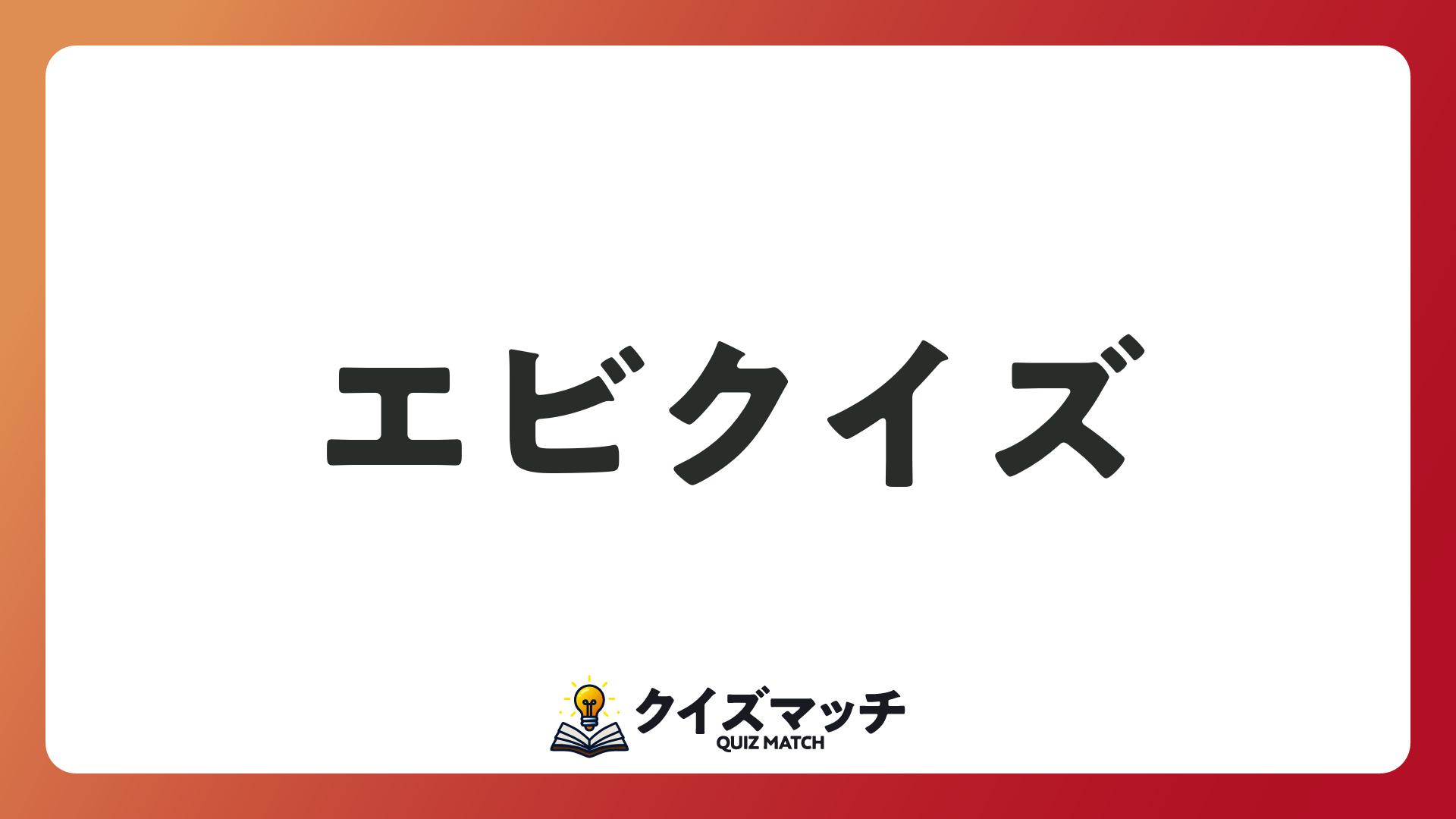エビはバランスの良い高たんぱく質の食材として知られており、私たちの食生活に欠かせない存在です。本クイズでは、エビの生態や特徴、栄養成分、調理法など、様々な角度からエビに関する知識を問います。クルマエビやイセエビ、バナメイエビなど、身近なエビの種類や生息地、さらには加熱時の色の変化など、エビに関する豆知識が満載です。エビ好きはもちろん、エビについて詳しくない方にも楽しめる内容となっています。クイズに挑戦して、エビの世界をもっと知っていきましょう。
Q1 : 伊勢エビの禁漁期間が定められている理由として正しいものは?
伊勢エビの禁漁期間は、主に繁殖期に漁獲による資源量減少を防ぎ、種を守るために定められています。日本では多くの県や地域で6月頃から9月末まで禁漁とし、新たな稚エビの誕生や成長を守ることで、持続的な伊勢エビ漁業が可能となっています。
Q2 : バナメイエビはどの地域原産のエビ?
バナメイエビ(ホワイトレッグシュリンプ)は、実は南アメリカ原産のエビです。エクアドル、メキシコ、ペルーなどで元々生息しており、養殖技術の発展とともに現在では世界中で主要な養殖エビとして流通しています。
Q3 : エビの赤い色素は加熱したときに現れますが、その色素の正体は?
エビの殻が加熱によって赤くなるのは、アスタキサンチンという色素が熱によって殻たんぱく質から遊離し、鮮やかな赤色を呈するためです。天然の状態では複合たんぱく質で隠れています。サケやカニの赤色もこの色素に由来しています。
Q4 : 桜エビの国内一大漁場として知られている場所は?
桜エビの一大漁場として有名なのは静岡県の駿河湾です。桜エビは日本ではほぼ駿河湾だけでまとまった漁獲があり、春と秋に漁が行われます。水揚げされた桜エビは生食や干しエビ、かき揚げなどさまざまな料理に利用されています。
Q5 : エビが含む栄養素として、次のうち特に豊富なのは?
エビはタウリンというアミノ酸の一種が多く含まれており、肝臓の機能向上や血圧降下作用に効果があるとされています。カルシウムも多少含みますが、カニや魚ほど多くはありません。ビタミンCや糖質はあまり含まれていません。
Q6 : エビが後ろ向きに泳ぐ理由について正しいものはどれ?
エビは天敵から攻撃された際に、尾を勢いよく動かして瞬時に後ろへ跳ねるように泳ぐことで逃げます。この方法は『カーリング』と呼ばれ、筋肉の発達した尾を利用して素早く移動するための防衛本能による動作です。視界や食事とは直接関係ありません。
Q7 : エビの仲間で世界最大の体長を誇る種はどれ?
エビの中で最も大きく成長するのは、テナガエビ科のオニテナガエビ(Macrobrachium rosenbergii)です。オスの個体は50cm以上に成長することもあり、世界最大級のエビとされています。一方、イセエビも大きいですが、主にロブスター類となります。
Q8 : 日本でエビの天ぷらによく使われる品種は?
日本の天ぷらでよく使われるエビはクルマエビです。身が太く、しっかりとした食感と甘みが人気で、特に高級天ぷら店ではクルマエビが好まれます。他にもブラックタイガーやバナメイエビが一般家庭や外食チェーンで使われていますが、伝統的にはクルマエビが主流です。
Q9 : エビの殻の主成分として正しいものは?
エビの殻は主にキチンという多糖類で構成されています。キチンは昆虫や甲殻類の外骨格を作る成分であり、硬さと弾力性を持っています。カルシウムも含みますが主成分ではありません。キチンは医療用途や工業材料としても利用されるなど重要な物質です。
Q10 : クルマエビが主に生息する場所として正しいのはどれ?
クルマエビは主に日本を含む西太平洋やインド洋などの暖かい海域に生息している海水性のエビです。特に沿岸の浅い泥底や砂底で多く見られます。一方で、成長段階によって一時的に汽水域に入ることもありますが、淡水や氷河地帯には生息しません。養殖も主に塩分のある水で行われています。
まとめ
いかがでしたか? 今回はエビクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はエビクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。