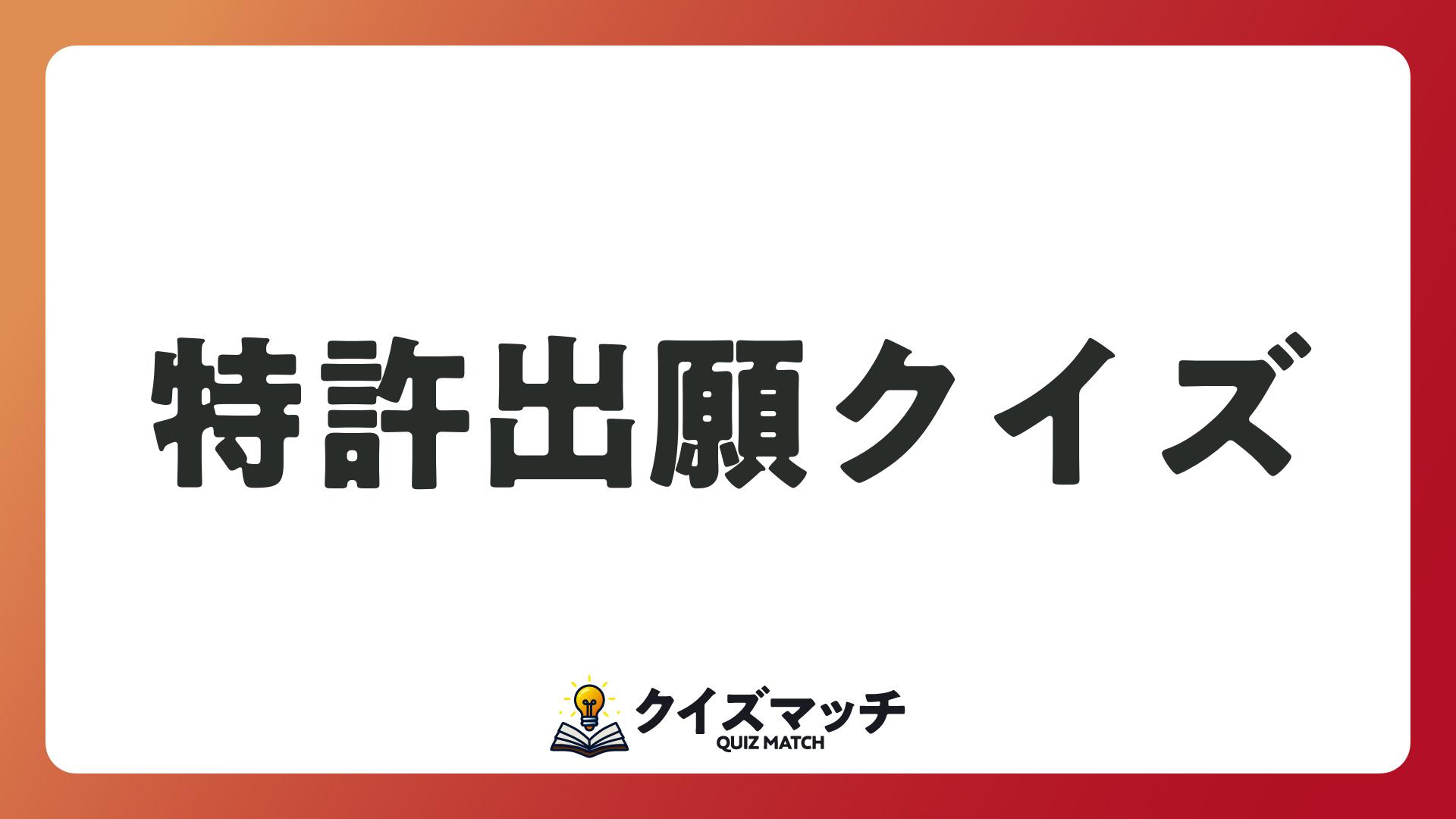特許出願は企業にとって重要な知的財産戦略の一環です。しかし、特許制度は複雑で、出願手続きや審査請求期限、権利発生のタイミングなど、理解を誤ると大きなリスクにもなり得ます。本記事では、特許出願に関する基本的な知識をクイズ形式で確認していきます。制度の理解を深めることで、特許取得をより確実なものにできるでしょう。特許出願に詳しくない方から、知財担当者まで、幅広い読者層に役立つ内容となっています。
Q1 : 特許出願の主な要件で、特許法上最も重要な要件とされるものはどれですか?
特許出願の最大要件の一つが新規性です。新規性とは、出願時にその発明が公知(すでに知られている)でないことを指します。公開性は特許出願公開制度に関するもので、意匠性・類似性は意匠法または商標法の概念であり、特許出願の要件ではありません。
Q2 : 日本で特許の審査を早くしたい場合に利用できる制度はどれですか?
日本特許庁では、一定の条件を満たした出願に対して、審査が早く行われる『早期審査制度』があります。早く権利化したい発明や、事業展開上急ぎたい場合などに活用されます。その他の制度は早期権利化には直接繋がりません。
Q3 : 出願公開後、審査請求がされないままの特許出願はどうなりますか?
日本の特許法では、特許出願後、指定された期間(通常は出願日から3年以内)内に審査請求がなければ、その出願は取り下げたものとみなされます(取り下げ擬制)。自動的に登録されることはなく、永久に出願中となることもありません。
Q4 : 優先権主張出願において、パリ条約による優先権主張ができる期間は原則として何か月ですか?
パリ条約による優先権主張は、原則として最初の出願日から12か月以内にしなければなりません。これを過ぎると優先権主張が認められません。特にグローバルに特許戦略を展開する企業にとって、12か月という期間管理は極めて重要です。
Q5 : 特許出願に関して、日本で認められている出願の種類に該当しないものはどれですか?
「意匠出願」は特許法上の出願の種類ではありません。意匠は意匠法に基づき保護されるもので、特許出願とは異なります。日本の特許出願の種類には、通常出願、分割出願、さらに特例(例えば優先権主張出願など)がありますが、意匠出願は特許の対象外です。
Q6 : 特許権が発生するのは、いつからですか?
特許権の効力が実際に発生するのは「設定登録日」からです。出願日、公開日、審査請求日では特許権は未成立で、特許庁の審査を通過し、登録簿に登録されて初めて権利が発生します。特許出願してすぐに特許権が発生するわけではなく、審査を経て設定登録されることが前提です。
Q7 : 特許審査請求の期間は、原則として出願日から何年以内ですか?
日本の特許制度では、原則として出願日から3年以内に審査請求をする必要があります。この期間内に審査請求が行われない場合は、出願は取り下げられたものとみなされます。審査の順番を早めたい場合には早期審査制度を利用することも可能ですが、通常は出願後3年以内の審査請求が基本です。
Q8 : 日本における特許出願の公開は、出願日から何か月後に行われるのが原則ですか?
日本の特許法において、特許出願は原則として出願日から18か月経過したときに公開されます。これを出願公開制度といいます。出願人の請求があれば早期公開も可能ですが、通常は18か月後です。審査の有無や特許証の発行とは異なる手続きですので、混同しないよう注意しましょう。
Q9 : 特許出願をするために必要な書類として正しいものはどれですか?
特許出願の際に必須となる書類は出願願書です。出願願書には発明の名称や出願人の氏名などが記載されます。構造図は技術内容を示す図として添付されることがありますが、必須ではありません。審査請求書は出願後に提出する書類であり、出願時点では不要です。移転登録願も出願手続き時には必要ありません。
Q10 : 日本においての特許の存続期間は、出願日から何年ですか?
日本の特許法において、特許権は出願日から20年の存続期間が認められています。ただし、医薬品など特定の分野では特許期間延長制度がありますが、通常の発明では20年が原則です。登録日ではなく出願日からの起算である点に注意が必要です。更新手続等が適正に行われなかった場合は途中で消滅することもあります。
まとめ
いかがでしたか? 今回は特許出願クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は特許出願クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。