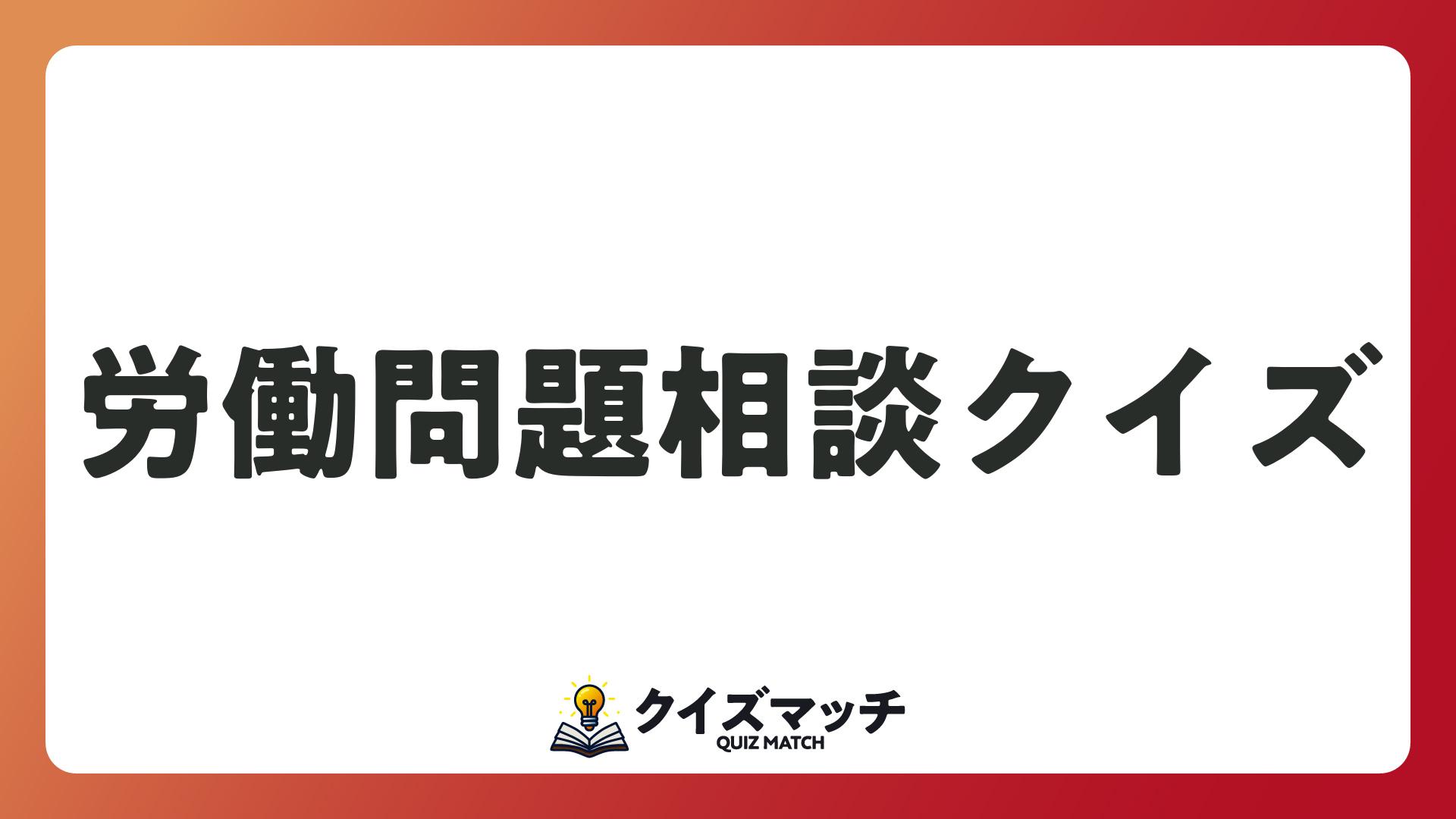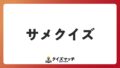労働問題について知っておくべき基本的な知識をチェックできる、10問の「労働問題相談クイズ」をお届けします。労働基準法や雇用契約、パワハラ対策など、従業員の権利と会社の義務について解説します。働く上で抑えておきたい重要な法制度をわかりやすく解説しているので、是非チェックしてみてください。労働問題に詳しくなって、自分の権利を守るためのヒントを見つけましょう。
Q1 : 労災保険で補償されるのはどのような場合ですか?
労災保険は、業務中または通勤中の事故や業務が原因の疾病等を補償する制度です。これにより、労働者が仕事や通勤の際に発生した災害について、治療費や休業補償等が支払われます。私的な活動中や退職後の病気等は補償の対象外で、基準を満たす労災事故のみが対象となります。
Q2 : 残業代は請求できる時効までの期間は何年ですか?
2020年4月1日施行の民法改正及び労働基準法改正により、残業代請求の時効は原則3年となりました(それ以前は2年)。ただし、賃金全般の支払請求権は5年ですが、残業代・退職金には個別規定があります。時効を過ぎると請求できないため、権利行使は計画的に行うことが重要です。
Q3 : 試用期間中の解雇は、どのような規制が適用されるか?
試用期間中であっても、労働基準法の解雇制限・手続きは適用されます。客観的に合理的な理由が必要で、社会通念上相当でない限り解雇は無効です。また、14日を超えて勤務した場合、通常の解雇予告義務も発生します。試用期間内だからといって自由に解雇できるわけではありません。
Q4 : パワーハラスメントに該当する行為はどれか?
パワーハラスメントには、業務上必要・相当な範囲を超えた言動(例:人格を否定、著しい侮辱や暴言、無視や排除)が含まれます。業務指導自体は適切であればパワハラにはなりません。パワハラは労働施策総合推進法で企業の防止義務が明記されており、被害を受けた場合は会社や労働局への相談が勧められています。
Q5 : 育児休業の取得が認められているのは次のうち誰ですか?
育児・介護休業法では、原則として1年以上継続雇用されている従業員は、正社員や契約社員、パートタイム問わず取得する権利があります。一方、雇用期間が1年未満や退職が決まっている人など除外規定もありますが、雇用形態に制限はありません。育児と仕事の両立を支援する目的です。
Q6 : パートタイマーにも有給休暇を取得する権利がありますか?
労働基準法では、パートタイマーであっても、継続勤務6か月を超え、全労働日の8割以上出勤していれば有給休暇付与の対象となります。パートやアルバイトの労働者にも労働基準法上の権利は保障されているため、正社員と同様に取得できます。職種や雇用形態に関わらず、この規定は適用されます。
Q7 : サービス残業は法律によってどのように扱われていますか?
サービス残業とは、労働者が賃金の支払いを受けずに就業時間外に働くことです。労働基準法第37条により、残業には割増賃金の支払いが義務付けられています。サービス残業は違法であり、たとえ本人が同意していても法的には認められません。会社には労働時間を正確に把握し、賃金を支払う義務があります。
Q8 : 解雇予告の義務に関し、会社が従業員を即日に解雇する場合、最低限必要な対応はどれですか?
労働基準法第20条では、解雇の際は少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。突然の解雇で生活に支障が出ることを防ぐための取り決めです。理由の説明だけでは足りず、解雇予告もしくは解雇予告手当が法的に義務付けられています。
Q9 : 有給休暇を取得する際、会社は理由を聞いて許可しないことができますか?
労働基準法第39条によれば、有給休暇の取得理由を会社が求めたり、理由によって取得を認めないことは原則としてできません。会社側は繁忙期など業務上やむを得ない事情がある場合、取得日を変更することはできますが、理由そのもので許可しないことは法律違反です。労働者の権利を守るため、休暇取得の自由度が重視されています。
Q10 : 労働基準法で定める法定労働時間は、1日何時間以内とされていますか?
日本の労働基準法第32条では、原則として1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないと定められています。これは、労働者の健康や生活の質を守るための基本的な取り決めです。時間を超過して労働させる場合は36協定(労使協定)を結ぶ必要がありますが、それでも限度があります。不当な長時間労働を防ぐためにこの規定が存在しています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は労働問題相談クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は労働問題相談クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。