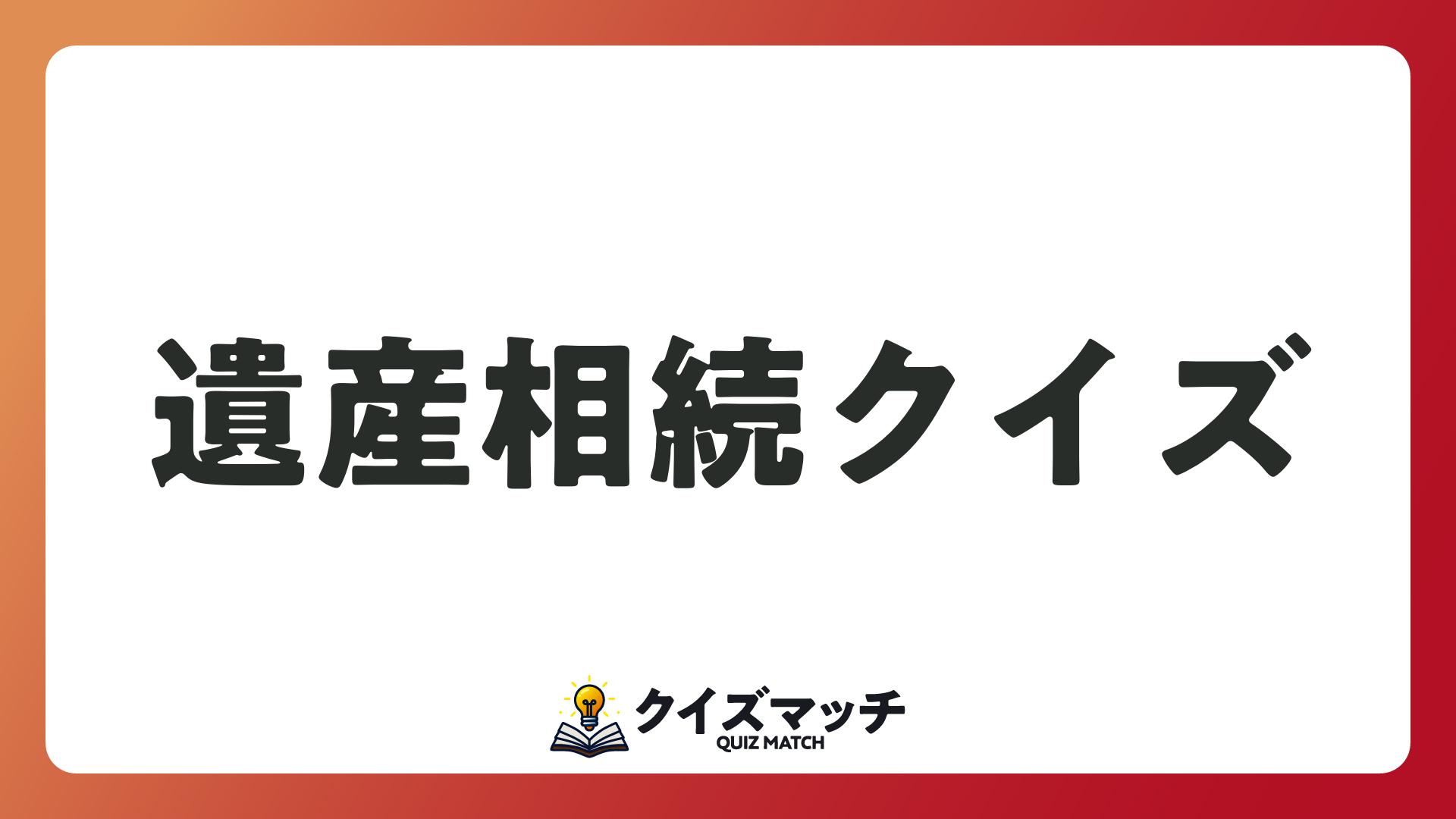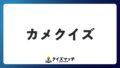遺産相続をめぐっては、様々な法律上の知識と実務の対応が必要となります。本記事では、相続の基本的な仕組みからトリッキーな論点まで、10問のクイズを通じて遺産相続に関する理解を深めていきます。相続に関する大切なルールを簡単な設問形式で解説し、相続時の対応に役立つヒントを提供します。遺産相続をスムーズに行うには、事前の知識と準備が欠かせません。この機会に、相続に詳しくなりましょう。
Q1 : 相続税の申告・納付期限は、被相続人死亡から原則として何か月以内でしょうか?
相続税の申告・納付期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(相続税法27条)。この期日を過ぎると加算税や延滞税の対象となる場合があるため要注意です。申告が必要かどうかは、課税価格や控除額によって変わります。
Q2 : 寄与分とは、どのような場合に認められる制度ですか?
寄与分とは、相続人の中で被相続人の生前に特別な貢献(例:介護、事業協力など)をした人が法定相続分より多く財産を受け取るための制度です。民法904の2に規定があり、他の単なる相続人への救済制度や全員協力、特定財産の受取りとは異なります。
Q3 : 被相続人死亡後、遺産分割がまだ終わっていない間の遺産の扱いは?
遺産分割協議がまとまるまでは、被相続人の財産は相続人全員の共有財産として扱われます(民法898条)。この間、各相続人は持分に従って財産に関する管理等に参加できますが、単独処分などは原則できません。分割後に各自が所有することになります。
Q4 : 法定相続人ではない人物でも、遺言によって財産を受け取れる方法は何と呼ばれますか?
法定相続人以外の人物でも、遺言によって財産を遺せる仕組みを「遺贈」といいます。被相続人が遺言書で指定することで、相続人以外の個人・団体にも財産を受け取らせることができます。相続とは異なる手続きや制限もあるため注意が必要です。
Q5 : 配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者の法定相続分はいくらですか?
被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と子どもが法定相続人となり、配偶者の法定相続分は2分の1、残りの2分の1を子どもが頭数で等分します(民法900条)。たとえば子供が2人であれば各々が4分の1ずつ相続します。
Q6 : 相続放棄をした場合、放棄した人はその後再びその相続に関与することはできますか?
相続を放棄した場合、その人は最初から相続人でなかったことになります(民法939条)。そのため、放棄後は財産の分配や遺産分割協議に一切関与することはできなくなります。なお、相続放棄は原則として家庭裁判所への申述によってのみ有効です。
Q7 : 兄弟姉妹が相続人となる場合、遺留分が認められているか?
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。遺留分は、配偶者、子、直系尊属(父母など)にのみ保障される権利です。したがって、被相続人が遺言で財産をすべて他人や公益団体等に遺贈した場合も、兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。
Q8 : 未成年者が相続人となる場合の取り扱いについて正しいものはどれですか?
未成年者でも相続人になることはできますが、遺産分割協議など法律行為については法定代理人(通常は親権者等)が代理して行います。例外的に利益相反がある場合は特別代理人の選任が必要となります。
Q9 : 遺言書を使って財産を遺したい場合、公正証書遺言の作成には証人が必要ですが、最低何人必要ですか?
公正証書遺言を作成する際には証人が2人以上必要であると民法969条に規定されています。公証人の面前で遺言者が遺言内容を述べ、それを公証人が筆記し、読み聞かせる際にも証人2人が立ち会います。証人の要件も細かく定められているため注意が必要です。
Q10 : 相続人が全くいない場合、被相続人の財産は最終的にどこに帰属しますか?
被相続人に法定相続人が誰もいない場合、その遺産は「特別縁故者」への分与請求が認められる場合を除き、最終的には国庫に帰属します。民法959条によりその定めがあり、地方自治体やNPO等ではありません。なお、特別縁故者等の請求がなければ国に帰属されるのが原則です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は遺産相続クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は遺産相続クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。