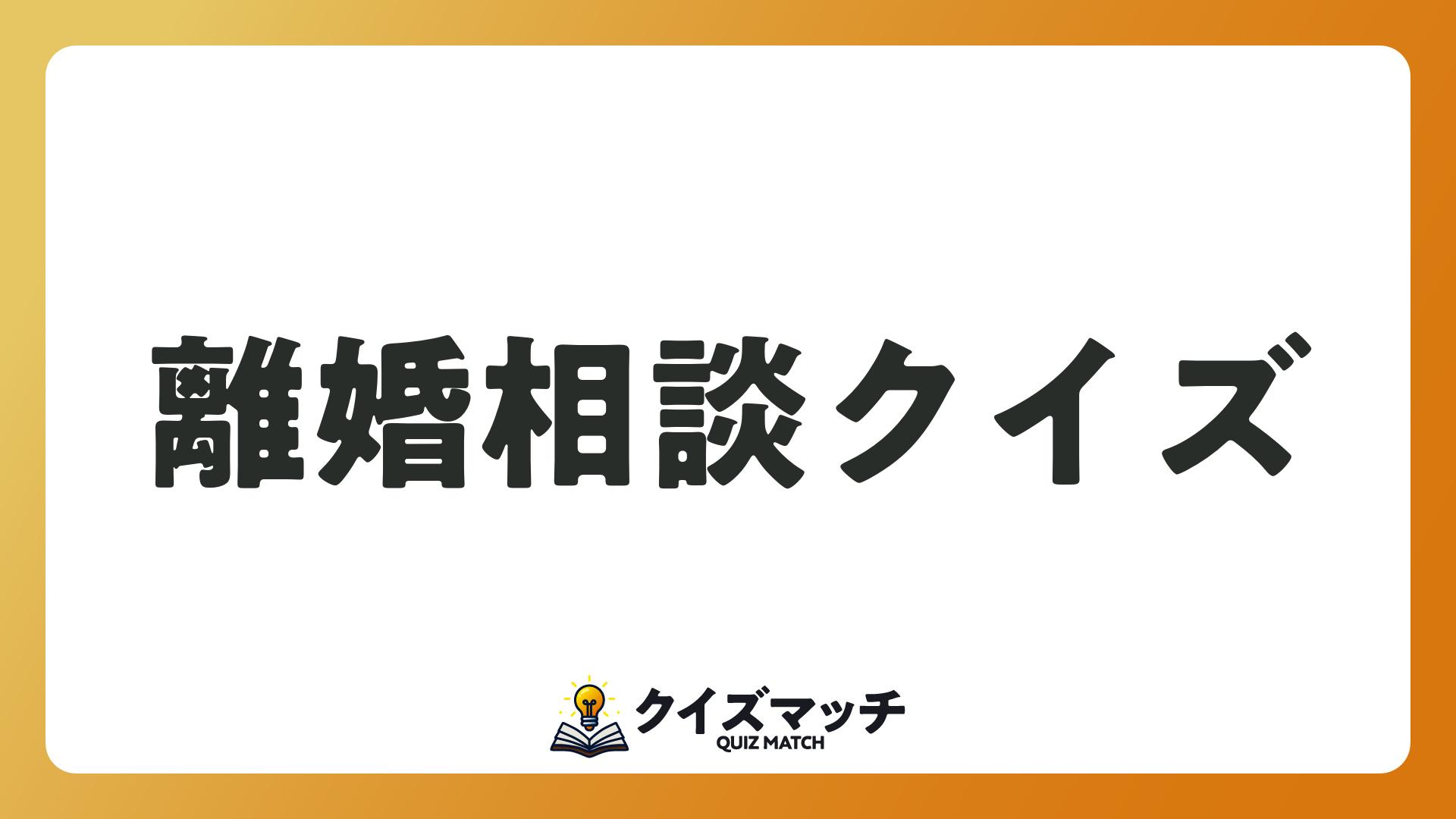離婚は人生の大きな岐路となる事柄ですが、その手続きや権利関係について正しく理解することが大切です。本記事では、日本における離婚の方法や親権、財産分与、養育費などについて、クイズ形式で解説していきます。離婚をお考えの方や、関心のある方は、この機会に離婚に関する知識を深めてみてはいかがでしょうか。
Q1 : DVを理由に離婚する場合、役所が発行する証明書は何か?
DV(家庭内暴力)被害者は、警察や配偶者暴力相談支援センターなどに相談すると『DV被害証明書』を発行してもらえる場合があります。この証明書があれば、住民票の閲覧制限などの保護措置を申請したり、裁判所の手続きに利用できます。
Q2 : 別居期間が長期化し、裁判所が離婚を認めやすくなるのは一般にどれくらいか?
裁判での離婚認容例では、5年以上別居していると認められるケースが多いですが、3年以上でもそれが理由で婚姻関係が破綻していると認められることが多いです。期間のみで判断されるものではありませんが、目安として3年以上が一つの基準です。
Q3 : 養育費の金額を決める際に日本で広く参照されているものはどれか?
日本で養育費を決める場合、当事者間の話し合いだけでなく、家庭裁判所では「養育費・婚姻費用算定表」という指針表が広く使用されています。算定表は両親の収入、子どもの人数などによりおおよその金額を示しています。
Q4 : 離婚調停と訴訟の違いとして正しい説明はどれか?
離婚調停は裁判所の調停委員を交えて夫婦間で合意を目指す手続きです。一方、訴訟は当事者間で合意できない場合に、最終的に裁判官が判決を下します。調停が不成立だと訴訟に進むケースが多いですが、手続き内容も異なります。
Q5 : 日本で離婚時に発生する『慰謝料』について正しいものはどれか?
慰謝料は離婚した場合に必ず認められるものではありません。主に配偶者の不貞や暴力、精神的苦痛を与えたような場合に限り、請求が認められるものです。また、慰謝料と財産分与は意味が異なります。
Q6 : 離婚の理由として『民法上の法定離婚事由』に含まれないものはどれか?
日本の民法では離婚訴訟における「法定離婚事由」として、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明などが挙げられています。「性格の不一致」は法定理由ではなく、裁判離婚の直接理由にはなりませんが、双方の同意による協議離婚では認められることがあります。
Q7 : 離婚が成立した場合、法律上子どもとの面会交流についてどうなるか?
面会交流(面接交渉)は離婚しても親子関係がなくなるわけではないため、非監護親(親権を持たない親)にも面会交流を認めるのが原則です。しかし、子の福祉に反すると考えられる場合には制限されることもあります。
Q8 : 離婚財産分与において、結婚後に取得した財産について正しい原則はどれか?
日本の民法では、婚姻中に夫婦が協力して得た財産は、名義がどちらであっても『共有財産』として、原則として分与の対象になります。婚前の財産や相続財産など、一部例外を除き、離婚時にはこれらを夫婦で分けることになります。
Q9 : 離婚する際の「親権」を巡る争いで、日本で決まることが多い原則は何か?
日本では未成年の子がいる場合、親権者は父母のどちらか一方に決めなければなりません。特に子が幼い場合や乳幼児のケースでは、母親が親権者となることが多いのが現状です。ただし、必ずしも母親が選ばれるとは限らず、個別事情も考慮されます。
Q10 : 日本で離婚するための方法として正しいものはどれか?
日本で離婚するには主に「協議離婚(話し合いによる離婚)」「調停離婚(家庭裁判所での調停を経ての離婚)」「審判離婚(調停後、裁判所の審判による離婚。稀)」「裁判離婚(訴訟離婚)」があり、これらはいずれも正式な方法です。従って『以上すべて』が正しい選択になります。
まとめ
いかがでしたか? 今回は離婚相談クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は離婚相談クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。