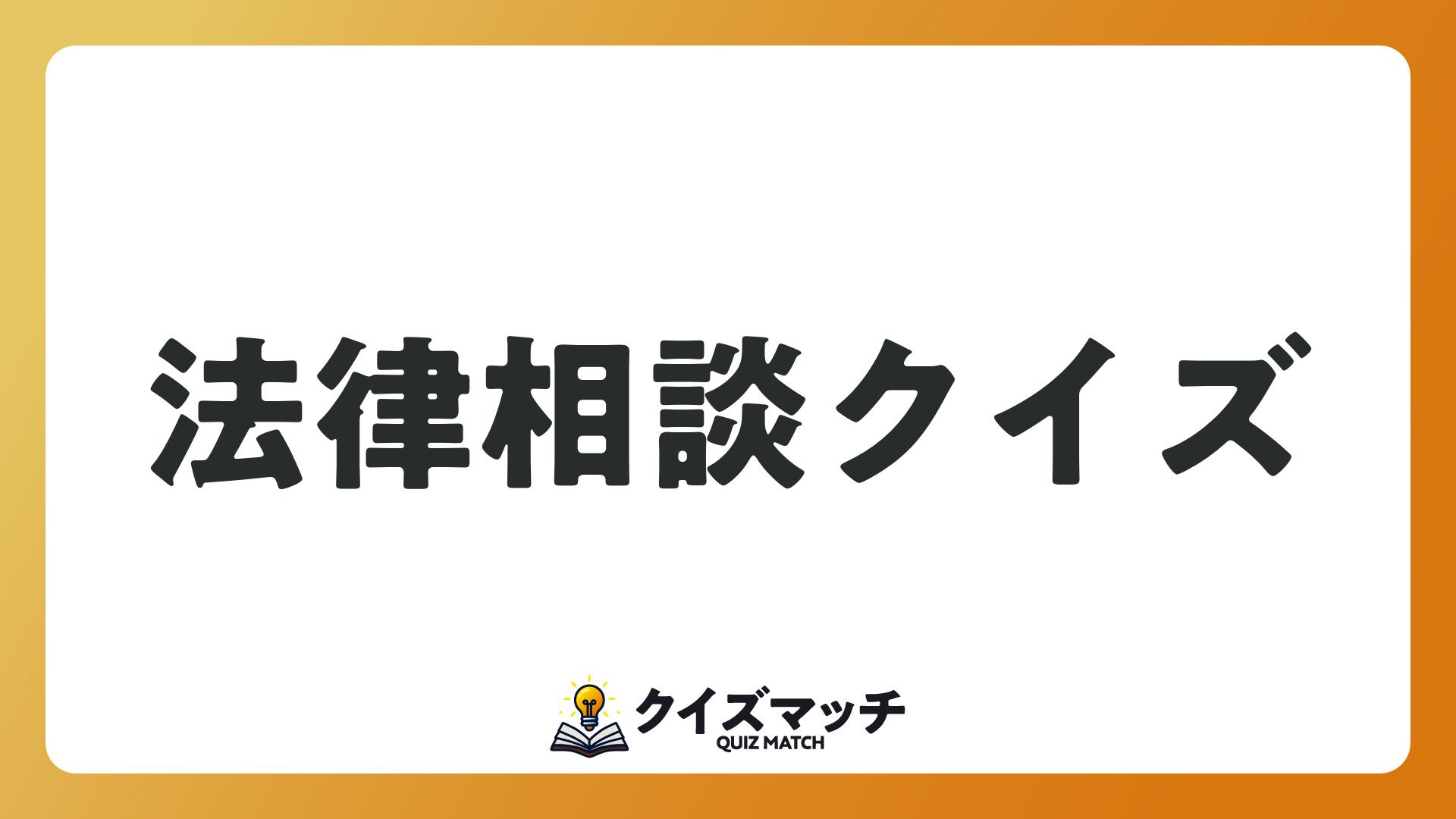法律を日常生活に上手く活用するための10の基礎知識 ー法律相談クイズで学ぼう ー
法律は私たちの生活に深くかかわっています。しかし、法律の細かい内容や専門用語に惑わされ、適切に活用できていないことも多いのが実情です。この記事では、10の法律相談クイズを通して、暮らしに役立つ法的知識を簡単に習得できます。遺言書の作成、SNSでの写真掲載、未成年の契約など、身近な話題から学べる内容となっています。法律の基礎を理解し、暮らしに役立てましょう。
Q1 : 「就業規則」を企業が作成しなければならない最低人数は何人以上の会社ですか?
労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、届け出なければなりません。10人未満の場合は作成義務はありませんが、作成することは可能です。人数が義務発生の分かれ目です。
Q2 : 名誉毀損(めいよきそん)に該当しないケースはどれですか?
名誉毀損の成立は、「たとえ真実でも」名誉を毀損した場合に認められますが、公共の利害に関することで、その目的が公益性に基づき、かつ真実である場合は、違法性が阻却され名誉毀損には該当しないとされます。
Q3 : 交通事故で相手が無保険の場合、損害賠償はどのように請求するのが一般的ですか?
加害者が無保険車だった場合、自賠責保険や被害者自身の無保険車傷害保険が利用できる場合があります。加害者本人に損害賠償を請求することも一般的です。警察への届け出や事故現場での滞在だけでは損害賠償は解決しません。
Q4 : 定期借家契約において、普通借家契約との一番大きな違いは何か?
定期借家契約は、契約期間が満了すると更新されずに終了する点が普通借家契約と大きく異なります。普通借家契約は更新が前提ですが、定期借家契約は期間満了で確実に終わります。他の項目(敷金・礼金等)には直接法律上の差はありません。
Q5 : 離婚後の子どもの親権は、原則としてどのように決定されますか?
離婚する場合、未成年の子がいるときは、協議離婚の場合は親権者を協議で定める必要があります。協議で定められなかった場合には、家庭裁判所が子の福祉を最優先して親権者を決めますが、協議が原則です。自動的に母または父になるわけではありません。
Q6 : 民事と刑事の裁判で、一番の違いは何ですか?
民事裁判は主に損害賠償や権利義務に関する争いを扱うのに対し、刑事裁判は犯罪事実があったかどうかを争う点が一番の違いです。手続や目的が異なり、刑事は国家が被告人を訴追します。なお、裁判官の人数や服装などは本質的な違いではありません。
Q7 : 過労死(過重労働による死亡)が労災認定されるために重視される要素はどれですか?
過労死が労災認定されるかは、通常、発症前1か月から6か月間の時間外労働(目安は月80時間超)の有無や業務の密度・負荷が重視されます。業務に関連した明らかな過重な労働があったかがポイントです。会社の規模や家族構成、年齢だけでは認定されません。
Q8 : 未成年者が親の同意を得ずに契約を結んだ場合、その契約はどうなりますか?
民法上、未成年者が親権者等の法定代理人の同意なしに契約した場合、その契約は未成年者または法定代理人が取り消すことができます。ただし、未成年者が成人と偽る等の例外もあります。取り消すまでは「有効だが取り消すことができる」という状態です。
Q9 : 無断で他人の写真をインターネットに掲載するのは、何の侵害となる可能性がありますか?
無断で他人の写真をインターネットに掲載することは、その人のプライバシー権や肖像権の侵害となります。肖像権は人格権の一部で、同意なしに写真を公表されない権利です。例外もありますが、特別な事情がない限り無断掲載は禁止されます。
Q10 : 遺言書が自筆で書かれている場合、法的に認められる条件の一つとは何ですか?
自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し、押印することが有効要件です。特に日付が明確でなければなりません。証人や公証人等の関与は不要ですが、日付や印の漏れは内容が正しくても無効となるため、注意が必要です。自筆証書遺言の法的効力はこれらの形式面の整備によります。
まとめ
いかがでしたか? 今回は法律相談クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は法律相談クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。