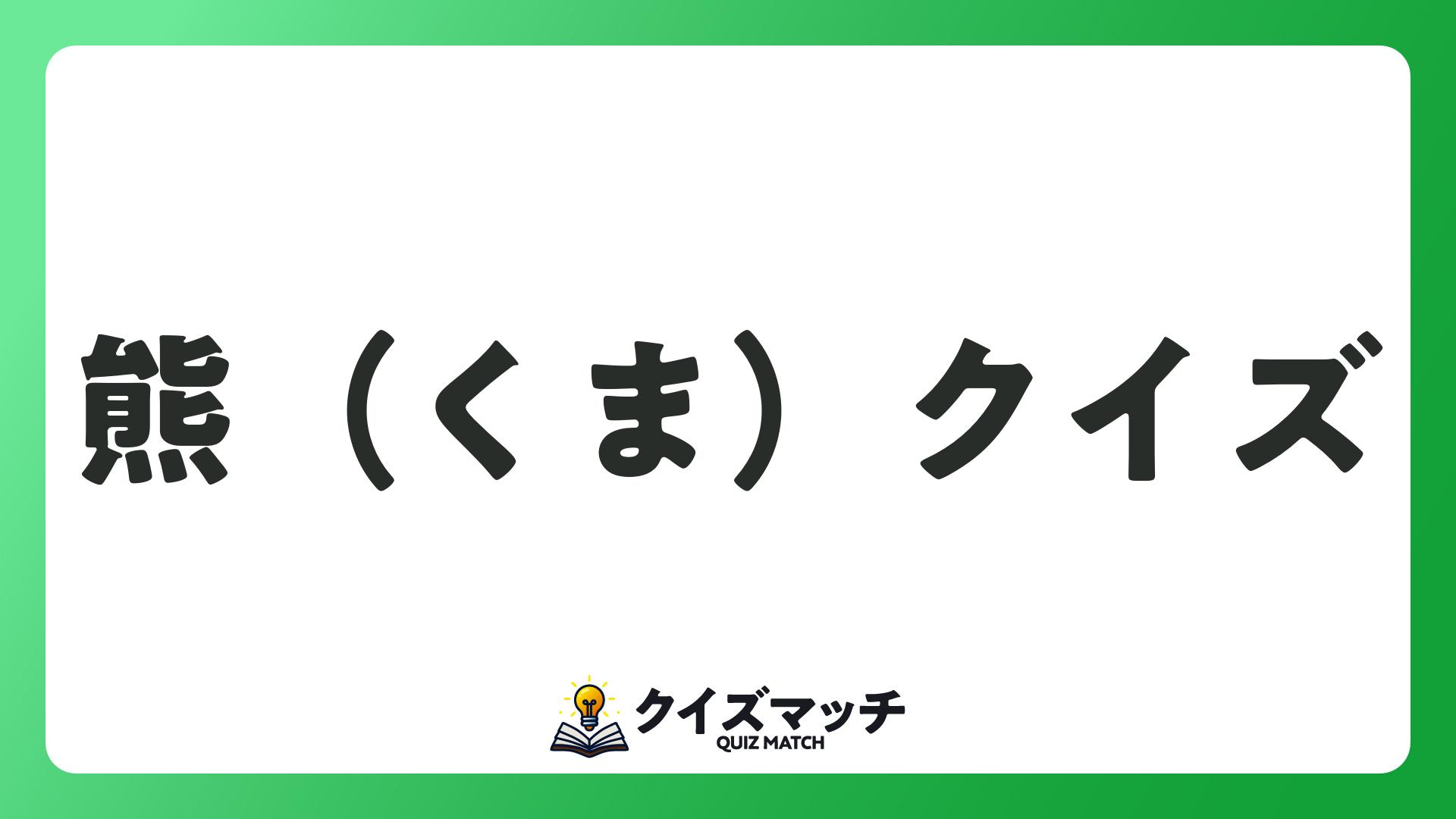熊(くま)は私たちの身近にいる大型の哺乳類です。世界には8種類のクマが生息しており、その中でも最大のクマであるホッキョクグマは北極圏に生息しています。日本には2種類のクマ、ヒグマとツキノワグマが生息しており、それぞれ北海道と本州・四国に分布しています。クマは冬眠する習性があり、その冬眠中にも様々な生理機能を保っています。また、ジャイアントパンダのような竹食性のクマも存在するなど、クマの食性は実に多様です。そんな興味深いクマについて、10問のクイズをお楽しみください。
Q1 : 日本神話や伝説にクマとして登場する有名な生き物の名前は?
「キンタロウ」は日本の昔話で有名な伝説上の人物で、幼いころからクマと親しく、クマと相撲を取ったりする逸話があります。このエピソードから、キンタロウ=力持ち=クマというイメージも強く、日本文化におけるクマの象徴的な存在です。他の選択肢はクマの伝説とは異なります。
Q2 : クマは主にどんな食性でしょう?
クマは多くの種類が雑食性です。果実、草、昆虫、魚、小動物など幅広く食べます。例としてヒグマやツキノワグマは主に植物質(果実・木の実など)や昆虫もよく食べますが、状況に応じて動物を捕食することもあります。ただし、ホッキョクグマは主に肉食傾向が強いです。
Q3 : ヒグマの繁殖期は主にいつですか?
ヒグマの繁殖期は主に夏(6月〜8月)にあたります。この時期にオスとメスが出会い交尾します。ただし、受精した卵は着床遅延(着床遅延現象)により、冬眠前まで発育が止まり、冬眠中に発育し始めるのが特徴です。このため、子グマは翌年の冬眠中に生まれます。
Q4 : ヒグマの学名はどれでしょう?
ヒグマの学名はUrsus arctosです。Ursusはラテン語でクマ、arctosはギリシャ語でクマを意味します。Ailuropoda melanoleucaはジャイアントパンダ、Ursus thibetanusはツキノワグマ、Melursus ursinusはナマケグマの学名になります。学名は国際的に生物を識別する大事な呼び方です。
Q5 : クマのうち海に最も近い環境で生活しているのは?
ホッキョクグマは極地の海氷上で生活しており、「海のクマ」とも呼ばれるほど、海との関わりが深い動物です。主な餌はアザラシで、氷の上で狩りをしたり、長い距離を泳ぐことができます。ツキノワグマ、ヒグマ、マレーグマはいずれも基本的に森林など陸地に生息しています。
Q6 : ツキノワグマの名前の由来は何でしょう?
ツキノワグマは胸に白い三日月型の模様があることからその名が付けられました。これは個体によって形や大きさが異なりますが、特徴的な模様です。英語ではAsian black bearと呼ばれています。夜行性の傾向もありますが、名の由来は模様からきています。
Q7 : ジャイアントパンダの主な食べ物はどれでしょう?
ジャイアントパンダの主な食べ物は竹です。パンダはクマ科の動物ですが、食事の99%以上が竹で構成されています。竹の幹や葉を一日中食べ、1日に20kg以上も消費することがあります。野生では時に小動物を食べることもありますが、ほとんどの栄養を竹から摂取しています。
Q8 : クマの冬眠について正しい説明はどれでしょう?
クマの冬眠明けはすぐに活発になるわけではありません。体が目覚めるまで徐々に活動量が増えていきます。また、多くのクマは冬眠中に子を産みます(特にメス)。冬眠中も多少は水分を摂ることもあり、生理機能は完全に停止するわけではありません。
Q9 : 日本に生息しているクマは何種類でしょう?
日本に生息しているクマは2種類です。ヒグマは北海道に分布し、ツキノワグマは本州、四国に生息しています。沖縄や九州には現在クマは生息していません。ジャイアントパンダなどは中国などに生息しており、日本には野生では存在しません。この2種類が日本のクマ類代表です。
Q10 : 世界最大のクマの種類は何でしょう?
世界最大のクマはホッキョクグマです。成獣のオスは体長2.5〜3メートル、体重400〜600kgに達し、最大で700kgを超えることもあります。ヒグマも非常に大きいですが、ホッキョクグマのほうが平均して大きくなります。この大きな体は、厳しい北極圏の寒さや長期間の空腹に耐えるための脂肪を蓄えるために必要です。ジャイアントパンダやツキノワグマも有名ですが、体の大きさはホッキョクグマに及びません。
まとめ
いかがでしたか? 今回は熊(くま)クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は熊(くま)クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。