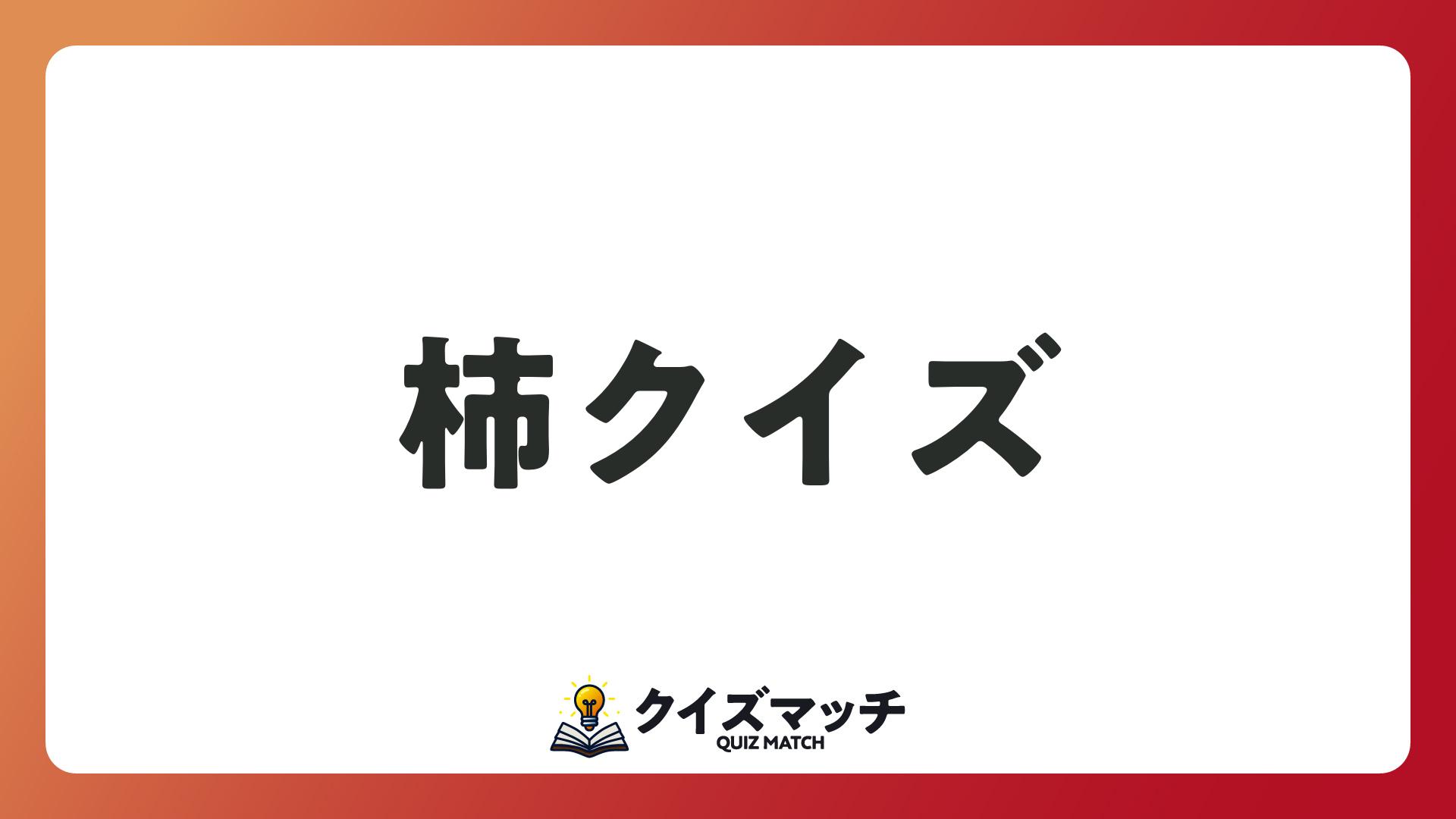柿は、日本人に愛されてきた果物の代表格です。その魅力的な味わいや、豊かな歴史には、まだまだ知らないことが多いかもしれません。この「柿クイズ」では、柿の品種、渋み成分、干し柿、歴史など、様々な柿の知識を楽しく学べます。柿の魅力を深く理解し、新しい一面を発見できる、まさに”柿通”になれるクイズの数々をお楽しみください。
Q1 : 柿の語源には諸説あるが、一説によるその名前の由来に一番近いのは?
柿の語源については諸説ありますが、有力な説の一つに「赤い色になる」ことにちなんで名付けられた、というものがあります。古代日本語で「赤い」を「かき」と発音していたことが転じて柿となったという説です。中国語では「柿」と書いて「シー」と読みますが、日本語の語源はこの赤みから来ているとされます。
Q2 : 柿はビタミンCが豊富だが、100gあたりのおおよその含有量は?
柿にはビタミンCが多く含まれており、100gあたり約20mgが一般的です。これはミカンよりはやや少ないものの、リンゴなどの果物と比べるとかなり多い量です。ビタミンCは風邪予防や美肌作りに役立つことで知られ、柿1個で1日の摂取目安量の3割程度を賄うことができます。
Q3 : 次のうち、渋抜きをしなくてもそのまま食べられる甘柿は?
「次郎柿」はそのまま食べても渋みのない“完全甘柿”として知られています。刀根早生や平核無柿はもともと渋柿で、渋抜きをして食べられるようになりますが、次郎柿は収穫した状態で完熟すると甘味が強く渋みがありません。甘柿は柿全体の中では数が少なく、特に次郎柿は特徴的です。
Q4 : 柿の葉寿司が名物の都道府県はどこ?
柿の葉寿司は主に奈良県や和歌山県で名物とされる郷土料理です。特に和歌山県はその代表的な産地として知られています。柿の葉には殺菌作用があり、酢飯と共にサバやサケの寿司ネタを包むことで保存性や風味が高まります。伝統的な保存食として祭事や贈答にも使われてきました。
Q5 : 干し柿の白い粉の正体は何?
干し柿の表面に現れる白い粉は、糖分(主にブドウ糖や果糖)が結晶化したものです。乾燥の過程で果実の水分が抜け、糖分が表面に析出して白い粉となるもので、カビではないので安心して食べられます。この現象は干し柿がしっかりと乾燥し、保存状態が良いとより現れやすくなります。
Q6 : 奈良時代から食べられてきた、非常に古い歴史を持つ柿の日本名は?
「やまとがき」とは奈良、つまり大和(やまと)の地を指し、日本古来から栽培・食用されてきた柿を指す伝統的な呼称です。奈良時代の文学や記録にも登場し、日本を代表する果物の一つとして知られています。柿は中国原産ですが、日本で独自の品種改良が進み、やまとがきもその一つです。
Q7 : 柿の学名に該当するのはどれ?
柿の学名は「Diospyros kaki」といいます。Diospyrosは柿属を表し、kakiは日本語のカキ(柿)から由来しています。他の選択肢はそれぞれリンゴ、モモ、ミカンの学名です。柿属は世界中に分布していますが、食用として広く栽培されているのは主にDiospyros kakiです。
Q8 : 干し柿作りに最適とされる、小さめの渋柿の代表的な品種は?
干し柿にすると甘味が引き立つため、「西条柿(さいじょうがき)」は干し柿用として非常に人気のある品種です。西条柿は渋柿ですが、干して水分が抜けることでタンニンが不溶化し、強い甘味とねっとりした食感が生まれます。本場は広島県西条地域で、広く干し柿に使われています。
Q9 : 柿の渋み成分であるタンニンの別名は?
柿の渋み成分は主に「シブオール」と呼ばれるタンニンによるものです。シブオールは水溶性から不溶性に変化すると渋みを感じにくくなりますが、未熟な柿には渋みが強く感じられます。熟すか、アルコールや炭酸ガス処理などでタンニンが不溶化することによって、渋みが取れ、おいしく食べられるようになります。
Q10 : 日本で最も多く栽培されている柿の品種はどれ?
日本で最も多く栽培されている柿の品種は「富有柿(ふゆうがき)」です。富有柿は明治時代に岐阜県で誕生した品種で、果肉が柔らかく、甘味が強いことから全国的に人気があります。日本国内の柿の生産量の中でも約60%を占めるとされており、主に岐阜県、奈良県、和歌山県などで多く栽培されています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は柿クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は柿クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。