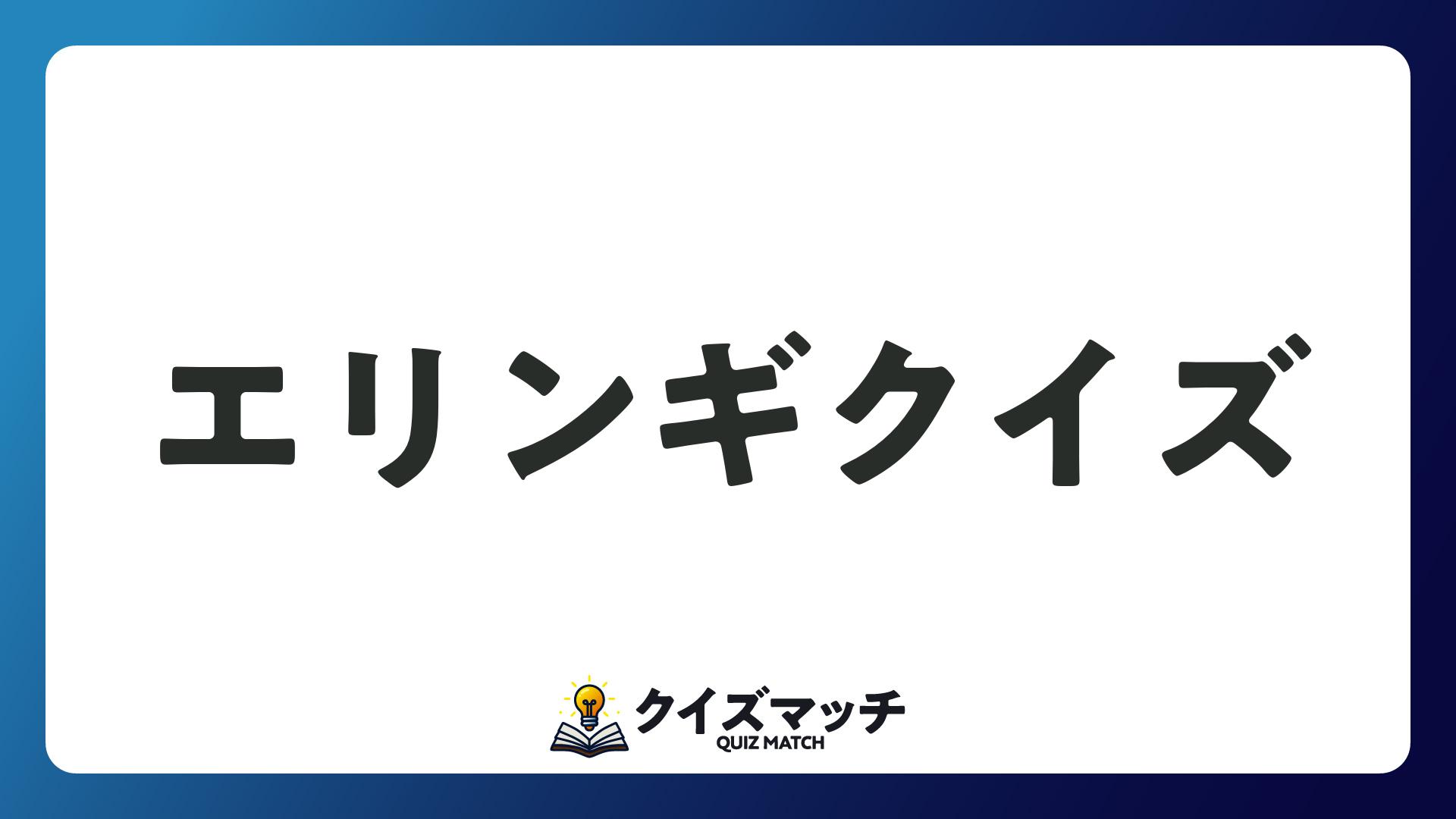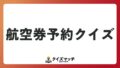エリンギの魅力を探るクイズ!食感や食材としての特徴、歴史など、さまざまな側面から”エリンギ”の知識を深めていきましょう。エリンギは一見するとキノコの定番種のようですが、実は意外な事実がたくさん隠れています。10問のクイズに挑戦して、エリンギの魅力を再発見してみてください。
Q1 : エリンギを主役に使ったイタリア料理でよく見かけるものは?
エリンギはリゾットの具材としてよく使われます。加熱しても旨味と食感が残り、リゾットのクリーミーさとマッチします。他の選択肢(スープカレー、タコライス、お好み焼き)は、エリンギが使われることもありますが、リゾットの具として世界的に知られています。
Q2 : エリンギの英語表記で正しいものはどれ?
エリンギは英語圏では “King trumpet mushroom” または “King oyster mushroom” と呼ばれています。Enoki mushroomはえのきたけ、Shiitake mushroomはしいたけ、Maitake mushroomはまいたけにそれぞれ対応します。
Q3 : エリンギの傘の色として標準的でないものは何?
エリンギの傘は一般的に白色から淡い褐色をしています。黒色や黄色の傘を持つものは通常のエリンギでは見られません。栽培環境により多少の色の違いはありますが、基本的に傘は淡い褐色が標準です。
Q4 : エリンギに多く含まれる食物成分として正しいものは?
エリンギには食物繊維が豊富に含まれています。他にもカリウム、ビタミンD、ビタミンB群などが含まれますが、ビタミンB12やカフェインはエリンギには含まれていません。食物繊維は腸内環境を整えるなど健康にも良い成分です。
Q5 : エリンギの主な収穫方法は?
エリンギは工場などで「菌床栽培」と呼ばれる室内管理された人工培地を用いた方法で主に生産されています。原木を使う栽培法はシイタケやマイタケで用いられますが、エリンギは主に菌床(オガクズやコーンコブなど)を材料とした環境で育成されます。
Q6 : エリンギが本来寄生する植物は?
エリンギは本来、セリ科植物の根元などに発生します。特にウスベニタチコウイカ(Eryngium campestre)などのセリ科植物との共生関係が見られます。そのためエリンギの学名(Pleurotus eryngii)もセリ科の学名に由来しています。
Q7 : 日本でエリンギの商業栽培がはじまったのは何年代?
エリンギの商業栽培は日本では1990年代に本格的に始まりました。最初は1993年ごろから長野県などで全国的に普及し、急速に一般家庭の食卓にのぼるようになりました。それ以前はほとんど流通しておらず、日本人にはあまり知られていませんでした。
Q8 : エリンギが持つ独特の食感は何と表現されることが多い?
エリンギは「コリコリ」としたしっかりした食感が特徴です。調理しても歯ごたえが残り、他のキノコにはないしっかりした食感を楽しむことができます。生のままや加熱して食されることも多く、そのコリコリ感が様々な料理で活かされています。
Q9 : エリンギは何科のキノコでしょう?
エリンギはヒラタケ科に属しています。一般的に「ヒラタケ」というと異なる種類のキノコを指しますが、エリンギはヒラタケ科ヒラタケ属の一種です。この科には食用として人気のキノコが多く含まれています。なお、シイタケはキシメジ科、マツタケはキシメジ科、ベニタケはベニタケ科です。
Q10 : エリンギの原産地として最も正しいものはどれ?
エリンギ(Pleurotus eryngii)はヨーロッパ地中海沿岸が原産のキノコで、地中海沿岸や中央ヨーロッパで自生しています。日本では主に人工栽培されており、もともとは日本には自生していません。現在では日本や中国、韓国などでも大量に栽培されていますが、元々の自生地としてはヨーロッパが正解です。
まとめ
いかがでしたか? 今回はエリンギクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はエリンギクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。