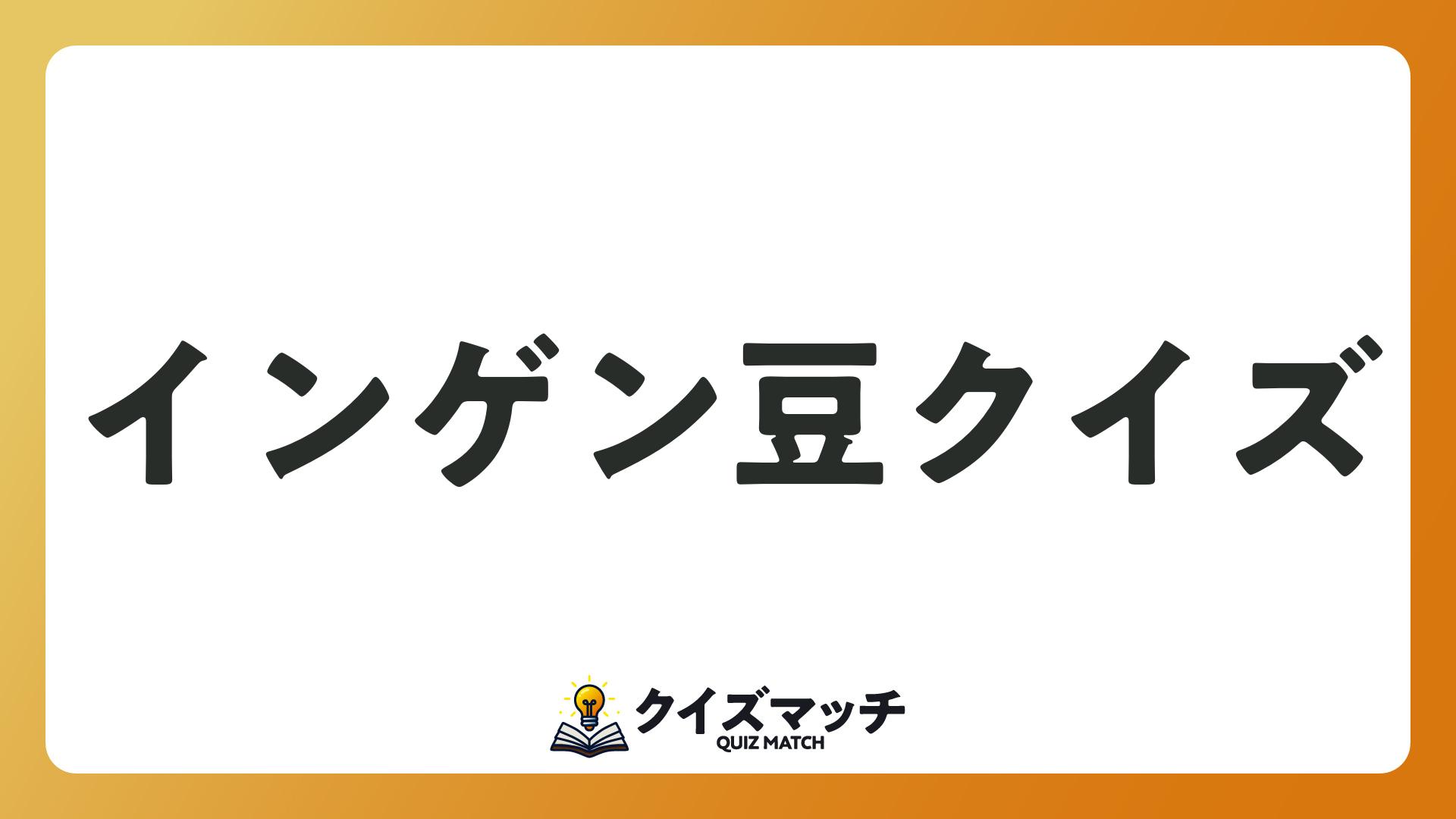インゲン豆はアンデス地方が原産地と考えられており、南アメリカを中心に世界中で栽培されるようになりました。日本にも江戸時代に伝来し、さまざまな料理で活用されています。この記事では、インゲン豆についての知識を深めるため、10問のクイズに挑戦してみましょう。豆の特徴や歴史、料理への活用方法など、インゲン豆にまつわる様々な情報を学べるはずです。インゲン豆の魅力を探る良い機会となるでしょう。
Q1 : インゲン豆を家庭菜園で育てる場合、花が咲いてから収穫するまでの目安期間は?
インゲン豆は花が咲いてからだいたい1週間〜10日ほどでサヤが大きくなります。実が柔らかい時期が一番美味しいため、このタイミングで収穫します。取り遅れると実が固くなるので注意が必要です。比較的短期間で収穫できる野菜です。
Q2 : インゲン豆1食分(約50g・ゆで)の食物繊維量は?
インゲン豆(ゆで)50gには、約4gの食物繊維が含まれています。これは野菜類の中でも多い部類で、腸内環境を整えたり、血糖値の上昇を緩やかにしたりするのに役立ちます。乾物状態ではさらに多くの食物繊維を含みます。
Q3 : 赤インゲン豆(レッドキドニービーンズ)が主役のアメリカ南部料理はどれ?
チリコンカンは、アメリカ南部やメキシコで親しまれている料理で、赤インゲン豆(レッドキドニービーンズ)や牛挽肉、トマト、チリパウダーなどを煮込んで作ります。豆の存在感があり、主役級の食材となっています。
Q4 : インゲン豆の品種で、甘納豆や煮豆に多く使われるのは?
甘納豆や煮豆など和菓子や惣菜に多く使われるのは白インゲン豆(大福豆、手亡豆など)です。これらは煮ても色移りせず、ほくほくした食感や淡白な味わいが和菓子作りに向いています。赤インゲン豆は主に西洋料理に使われます。
Q5 : 乾燥インゲン豆を調理する際に必要な下処理は?
乾燥インゲン豆を調理する場合は、調理前に数時間〜一晩ほど水に浸して戻す必要があります。これにより、豆が柔らかくなって加熱しやすくなり、消化もしやすくなります。水に浸さない場合、調理時間が大幅に長くなり、食感も悪くなります。
Q6 : 「いんげん豆」の名称の由来は?
「いんげん豆」という名前は、江戸時代に中国からこの豆の種を持ち帰った隠元禅師(いんげんぜんじ)に由来しています。隠元禅師がこの豆を日本に伝えたとされており、そこから「いんげん豆」と呼ばれるようになりました。
Q7 : インゲン豆の中で『虎豆』として有名なのはどんな模様?
虎豆と呼ばれるインゲン豆は、白と茶色のぶち模様が特徴です。日本では「虎の皮のような模様」が名前の由来です。その見た目と、煮ると柔らかく甘味があることから人気があります。他のインゲン豆と区別しやすい特徴的な豆です。
Q8 : インゲン豆が持っている有毒成分は何でしょう?
インゲン豆には「レクチン(フィトヘマグルチニン)」という有毒成分が含まれています。特に赤インゲン豆は加熱せずに食べると中毒を起こすおそれがあり、通常は必ず十分に加熱して使用します。茹でることで毒性が分解されて安全に食べられるようになります。
Q9 : 日本で一般的な「さやいんげん」は、どの部分を食べるでしょう?
日本で一般的に食べられている「さやいんげん」は、未熟なさやと中の種子が両方とも柔らかい状態のものです。したがって、さやと種子の両方を一緒に食べます。逆にインゲン豆が完全に成熟すると、固くなるため主に乾燥させて豆だけを利用します。
Q10 : インゲン豆の原産地はどこでしょう?
インゲン豆(フェーズォルス・ウルガリス)は南アメリカが原産とされています。特にペルーやメキシコなどのアンデス地方や中南米が起源です。16世紀の大航海時代にヨーロッパにも伝わり、今では世界中で栽培されています。日本には江戸時代に中国を経て伝来し、現在ではさまざまな料理で利用されています。
まとめ
いかがでしたか? 今回はインゲン豆クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はインゲン豆クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。