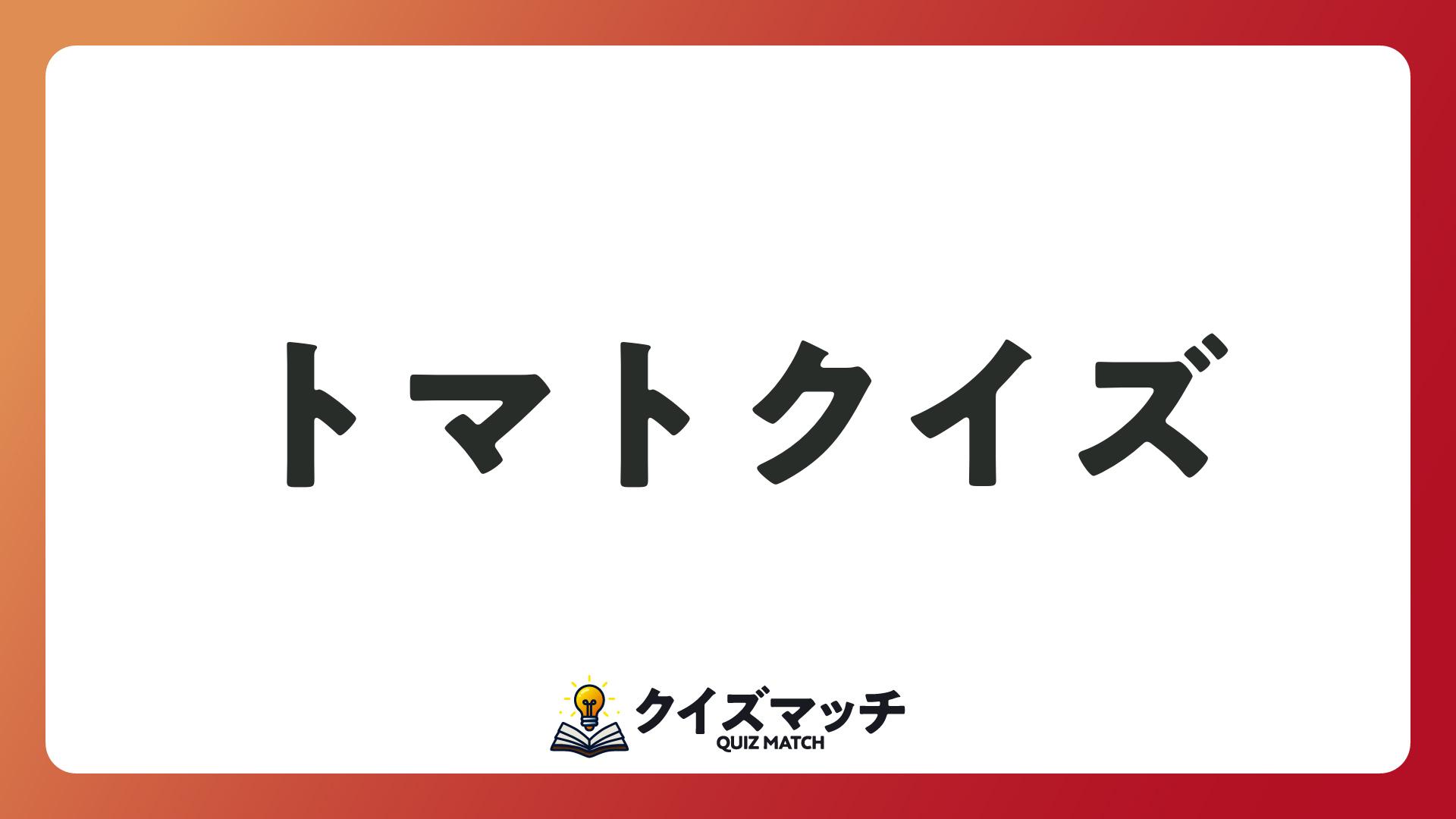トマトは私たちの食生活に欠かせない重要な食材です。意外にも、その原産地や歴史、栄養成分などには多くの興味深い事実が隠されています。本記事では、そんなトマトに関する10の知識を問うクイズを用意しました。トマトの深い魅力を感じていただけると思います。クイズにチャレンジして、トマトの魅力を探っていきましょう。
Q1 : トマトを加熱調理すると増える健康成分はどれですか?
トマトに含まれるリコピンは加熱調理によって細胞壁が崩れ、体内への吸収率が高まります。生のまま食べるより、煮込み料理やトマトソース、スープにするとリコピンの健康効果をより得やすくなります。ビタミンCは加熱すると壊れやすいため、調理後の量が減少します。他の栄養素も変動しますが、リコピン吸収率の増加が最も顕著です。
Q2 : ミニトマトの学名(種名)は何ですか?
ミニトマトは学名で「Solanum lycopersicum var. cerasiforme(ソラナム・リコペルシクム・バル・セラシフォルメ)」と言います。通常のトマトと同じ種ですが、変種となります。Solanum tuberosumはジャガイモ、Capsicum annuumはピーマン、Solanum melongenaはナスの学名です。
Q3 : トマトが苦手な人によく見られる「青臭さ」の主な原因物質は何ですか?
トマトの青臭さ(草っぽいにおい)は、主に「ヘキセナール(n-ヘキサナール)」という化合物によるものです。この成分は未熟なトマトや葉・茎から多く発生します。ヘキセナールは切った草のような匂いが特徴で、これが苦手意識の原因になることがあります。ほかの成分は主に他の植物の香り成分です。
Q4 : トマトの果実分類上の正しいカテゴリは?
トマトは普段「野菜」として扱われますが、植物学的な分類(果実分類)では「果物」に該当します。花が咲き実をつける部分で、種子を含む部分を「果実」と呼びます。厳密には「液果」という種類に分類されます。ただし、食文化や流通上の慣習として野菜扱いされることが多いです。
Q5 : 次のうち、トマトの熟す過程で主に生成される香り成分は?
トマトの熟成中に増加し特徴的な香りを出す成分の1つがメチルヘプテノン(特に2-メチルヘプタ-2-エノ-1-オール)です。甘くフルーティなトマトの香りを構成するのにおいて重要です。他の選択肢は柑橘類に多く含まれる芳香成分ですが、トマトの代表的な香り成分ではありません。
Q6 : 日本のトマトの生産量が最も多い都道府県は?(2022年データ基準)
日本で最もトマトの生産量が多い都道府県は熊本県です。熊本県は温暖な気候や日照量、水資源に恵まれており、ハウス栽培も盛んです。北海道や茨城県、愛知県もトマトの主要産地ですが、熊本県が長らくトップを維持しています。近年は品種開発や出荷体制の充実にも注力しています。
Q7 : 以下のうち、トマトの仲間(ナス科)に該当しない野菜はどれ?
トマトはナス科に属します。ジャガイモ、ナス、ピーマンも同じくナス科の植物ですが、ホウレンソウはヒユ科(旧アカザ科)に分類されるため、ナス科の仲間ではありません。ナス科の野菜は他にもトウガラシなどがあります。ホウレンソウは葉物野菜の代表格です。
Q8 : トマトに多く含まれる赤い色素成分の名称は?
トマトの赤い色は主に「リコピン」によるものです。リコピンはカロテノイド系色素の一つで、強い抗酸化作用を持つことでも知られています。β-カロテンやアントシアニンも色素成分ですが、それぞれニンジンやナスなどに多く含まれる物質です。クロロフィルは緑の葉野菜に含まれる緑色素です。
Q9 : 次のうち、トマトが日本にもたらされた時代はいつですか?
トマトが日本に伝わったのは江戸時代のことです。17世紀の後半にオランダ人によって長崎に持ち込まれたのが始まりといわれています。しかし、当初は観賞用として栽培されており、食用として普及し始めたのは明治時代以降です。平安時代や昭和時代は伝来時期から外れています。
Q10 : トマトの原産地として最も正しいものはどれですか?
トマトの原産地は南アメリカ、特にアンデス山脈一帯とされています。ペルーやエクアドル、ボリビアなどの地域で、野生のトマトが自生していたことが証拠とされています。16世紀頃にスペイン人によってヨーロッパに伝えられ、その後、世界中に広まりました。北アメリカやヨーロッパ、オーストラリアは伝播地であり、原産地ではありません。
まとめ
いかがでしたか? 今回はトマトクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はトマトクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。