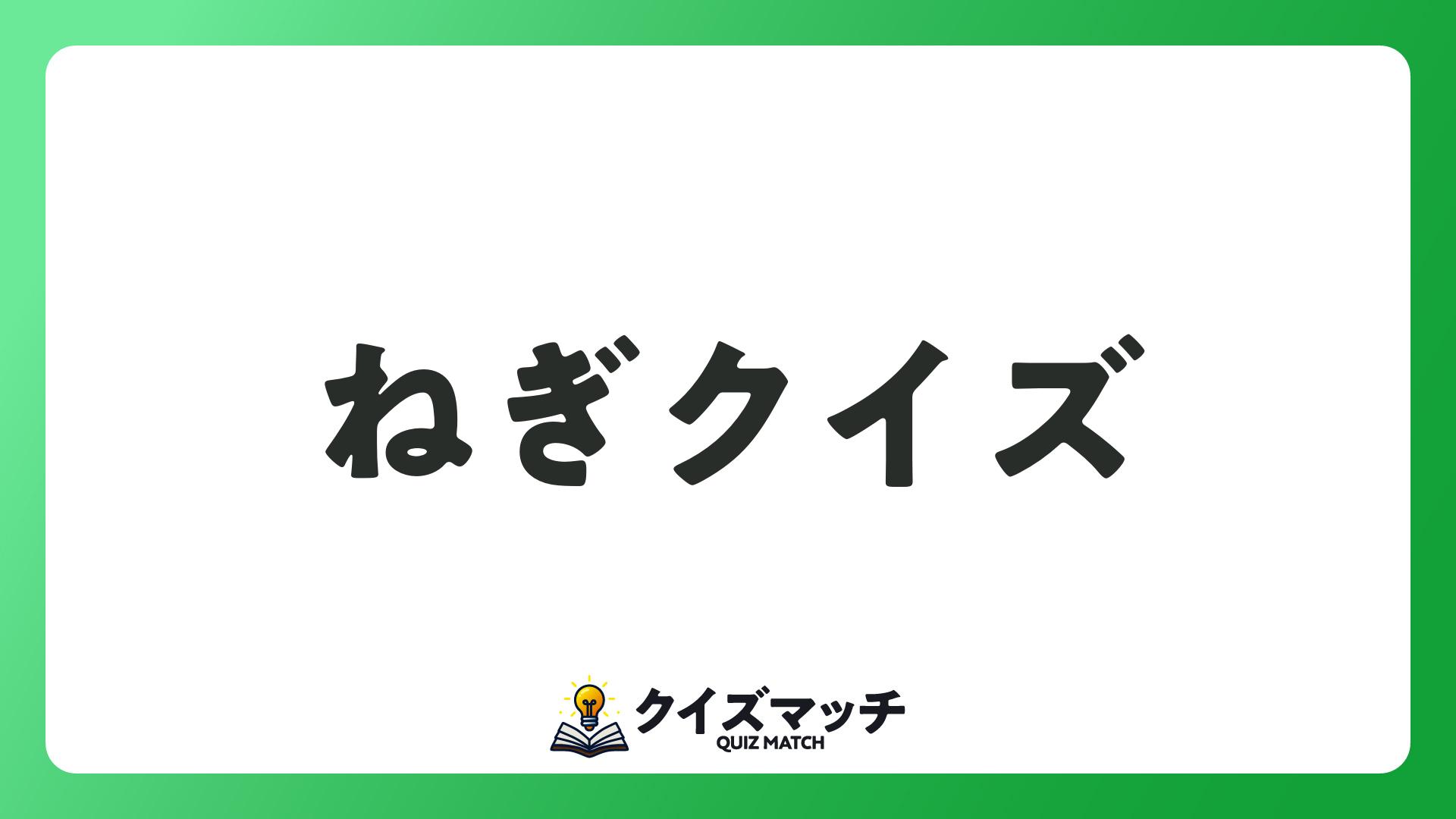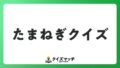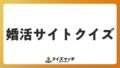ねぎクイズ – ねぎの豆知識をチェックしよう!
日本で生産量が特に多いねぎの品種は「根深ねぎ(白ねぎ)」です。関東地方や東北地方では白ねぎの利用が多く、主に炒め物や鍋物などで使われています。一方で、関西地方や中国・九州地方では青ねぎの消費が多い傾向にありますが、全国的な生産量でみると白ねぎが最も多いです。ねぎにまつわる豆知識をチェックできる、全10問のクイズをお楽しみください。
Q1 : 歌で『ねぎをしょって歩く』と表現される動物はどれ?
ことわざ「鴨が葱を背負ってくる」で知られるように、カモとねぎは鍋料理の代表的な組み合わせです。「鴨がねぎを背負ってくる」は、「うまい話が都合よくやってくる」という意味で使われています。ねぎとカモの料理は日本でも古くから親しまれています。
Q2 : 以下のうち、青ねぎの一大産地で有名な府県はどれ?
福岡県は「博多万能ねぎ」など青ねぎの生産で一大産地として知られています。暖かい気候と豊かな土壌が青ねぎの栽培に適しており、全国に出荷されています。他の選択肢もねぎの生産はありますが、福岡県が特に有名です。
Q3 : ねぎを加熱すると甘みが増す理由は何?
ねぎにはデンプンが含まれており、加熱することでデンプンが分解されて糖に変わるため、甘みが増します。さらに、辛みの元になるアリシンも加熱で揮発し、マイルドな味わいになるのが特徴です。
Q4 : 山形県特産の「だだちゃねぎ」の特徴は?
山形県特産の「だだちゃねぎ」は、甘みが強いのが特徴です。寒暖差が大きい地域ならではの味わいで、煮ても焼いても甘味が引き立ちます。「だだちゃ」とは方言で「お父さん」という意味があり、地域に根付いた野菜です。
Q5 : 白く長い部分(白ねぎ)はどのような栽培方法で作られる?
白ねぎ部分を長く育てるには「盛土(もしくは土寄せ)」という方法を用います。ねぎの成長に合わせて土をかぶせることで、日光が当たらない部分が白く長く育ちます。これが柔らかくて甘味のある白ねぎ部分になる理由です。
Q6 : ねぎの収穫時期として最も適している季節は?
ねぎは1年を通して出回りますが、最もおいしいとされるのは冬です。寒さが厳しいほど旨味や甘みが増し、鍋物などの需要が高まります。また、冬のねぎは霜にあたって甘みが増すため、特に好まれます。
Q7 : ねぎはヒガンバナ科に分類されますが、どの植物とも同じ科に属していますか?
ねぎはヒガンバナ科に属しており、同じヒガンバナ科の野菜には「ニラ」や「ラッキョウ」などがあります。これらの植物は見た目や利用法は異なりますが、科が同じであるため、特徴的な香りや辛味を持つものが多いです。
Q8 : 薬味として使われることが多い、細かく刻んだ青ねぎの名称はどれ?
「小口ねぎ」は青ねぎを細かく輪切りにしたもので、多くの料理の薬味に使用されます。そばやうどん、冷奴、ラーメンなどにのせて風味と食感を楽しみます。青ねぎは見た目も鮮やかで、料理の引き立て役です。
Q9 : ねぎに含まれ、独特の辛味やにおいの元となる成分は?
ねぎに含まれる「アリシン」は、ねぎ特有の辛味やにおいの元となる成分です。アリシンは切ったりすりつぶしたりすることで発生し、抗菌作用や血行促進効果も知られています。にんにくや玉ねぎにも含まれる成分で、健康効果が期待されています。
Q10 : 日本で生産量が最も多いねぎの品種はどれ?
日本で生産量が特に多いねぎの品種は「根深ねぎ(白ねぎ)」です。関東地方や東北地方では白ねぎの利用が多く、主に炒め物や鍋物などで使われています。一方で、関西地方や中国・九州地方では青ねぎの消費が多い傾向にありますが、全国的な生産量でみると白ねぎが最も多いです。
まとめ
いかがでしたか? 今回はねぎクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はねぎクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。