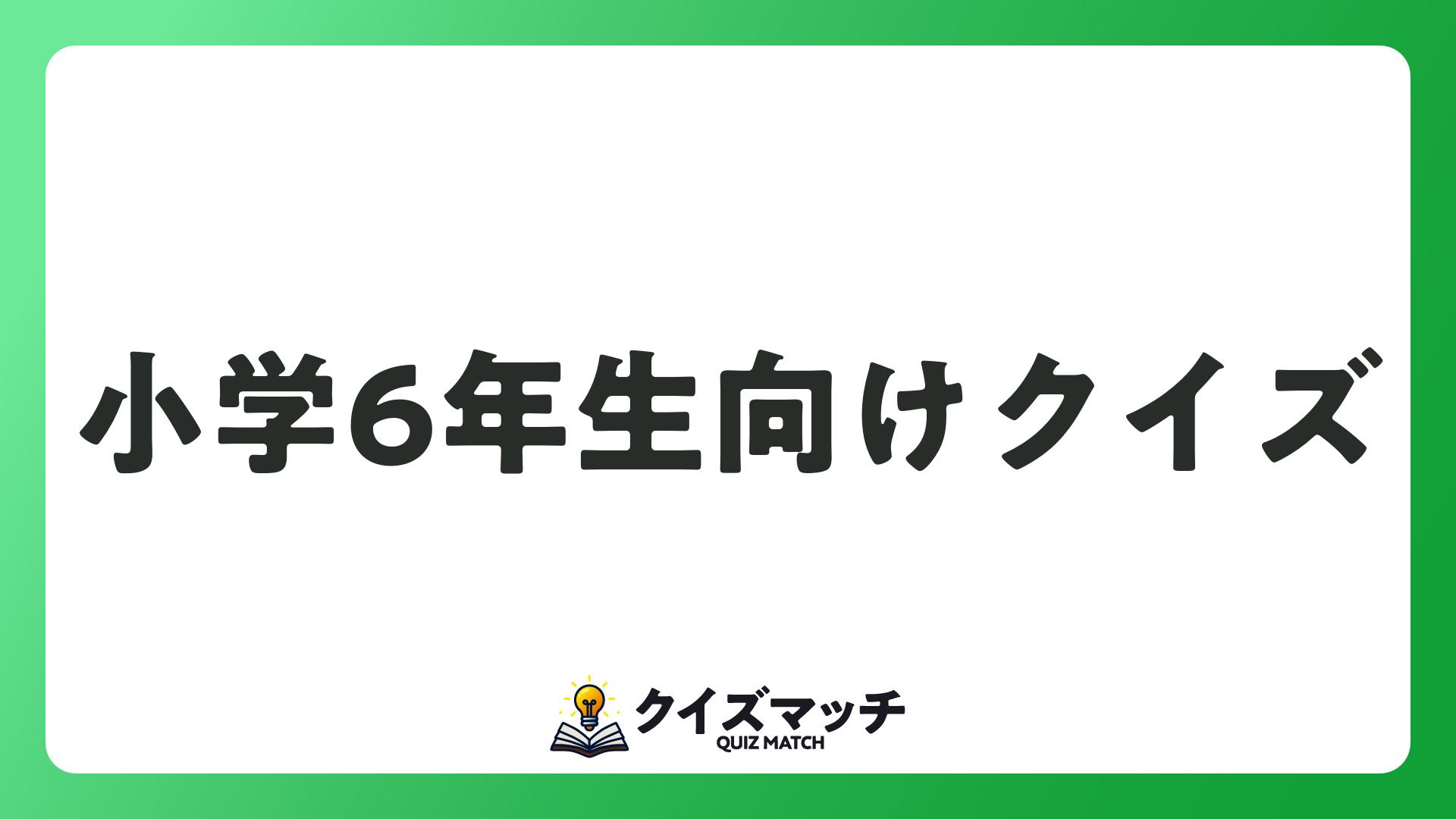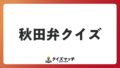小学校6年生の皆さん、今日は地球や宇宙、日本の歴史など、様々な分野のクイズにチャレンジしてみましょう。知識を深めながら、楽しく学習できるはずです。全部で10問のクイズを用意しました。子ども向けのわかりやすい問題ばかりなので、みんなも一緒に楽しめると思います。問題に集中して、正解率を上げていきましょう。
Q1 : 日本の元号のうち、令和の前は何だったでしょう?
令和の前の元号は「平成」です。平成は1989年から2019年まで続きました。その前は昭和、大正、明治の順番です。日本では天皇の在位に合わせて元号が変わります。令和は2019年から現在まで使われている元号です。
Q2 : 磁石のN極とS極を近づけたとき、どのようになるでしょう?
磁石にはN極(北極)とS極(南極)があります。N極とS極を近づけると、必ず引き合います。逆にN極同士やS極同士を近づけると反発し合い、離れようとします。これは磁石の性質で、小学生の理科でも学ぶ内容です。
Q3 : 日本の国会は何院制でしょう?
日本の国会は「二院制」となっています。つまり「衆議院」と「参議院」の2つの議院からなっています。二院制は法律を慎重に審議するために設けられています。一院制は議院が1つだけの場合です。三院制や四院制は日本にはありません。
Q4 : 地球から一番近い恒星は太陽ですが、その次に近い恒星は何でしょう?
太陽系を除くと、地球から一番近い恒星は「プロキシマ・ケンタウリ」です。その距離は約4.24光年です。プロキシマ・ケンタウリはケンタウルス座にある赤色矮星です。他の選択肢であるアルデバランやシリウス、ベテルギウスはもっと遠くにあります。
Q5 : 戦国時代に「桶狭間の戦い」で今川義元を討った武将は誰でしょう?
桶狭間の戦いで今川義元を討ったのは「織田信長」です。この戦いは1560年に起こり、織田信長が少人数の軍勢で今川義元の大軍を打ち負かした有名な戦いです。この戦で信長は全国に名を広め、戦国時代の流れを大きく変えるきっかけとなりました。
Q6 : 俳句の総文字数(基本形)はいくつでしょう?
俳句は日本の代表的な短詩で、主に「5・7・5」の音で構成されています。全部で「17音」ですが、これが俳句の基本的な形です。5文字や7文字は俳句の一部分だけの音数です。31文字は短歌の音数となります。
Q7 : 酸素は空気中のおよそ何パーセントくらい含まれているでしょう?
大気中には酸素が約21%、二酸化炭素が0.04%、窒素が約78%含まれています。酸素は私たちが呼吸するときに必要な気体であり、生物の生命活動には欠かせません。大気の多くは窒素が占めていますが、生き物が利用できるのは主に酸素です。
Q8 : 太陽系の惑星で、最も大きい惑星は何ですか?
太陽系で最も大きい惑星は「木星」です。木星は地球の約11倍の直径と、約318倍の質量を持っています。ガス状の惑星で、表面には「大赤斑」と呼ばれる巨大な嵐が有名です。水星は太陽に最も近く、小さな惑星です。地球と金星も木星よりずっと小さい惑星です。
Q9 : 日本で一番高い山はどれでしょう?
日本で一番高い山は「富士山」です。高さは標高3776メートルで、日本の象徴的な山でもあります。その他の白山(2702m)、槍ヶ岳(3180m)、大山(1709m)も有名な山ですが、それぞれ富士山より標高が低いです。富士山は山梨県と静岡県にまたがっています。
Q10 : 地球の一番外側の層を何というでしょう?
地球の構造は、内側から核、マントル、地殻の順に層が重なっています。一番外側の層は「地殻」と呼ばれ、私たちはこの地殻の上で生活しています。地殻は岩石でできていて、その厚さは陸の部分で約30〜50km、海底の部分では約5〜10kmとされています。マントルは地殻の下にあり、さらに深いところには「核」が存在します。
まとめ
いかがでしたか? 今回は小学6年生向けクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は小学6年生向けクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。