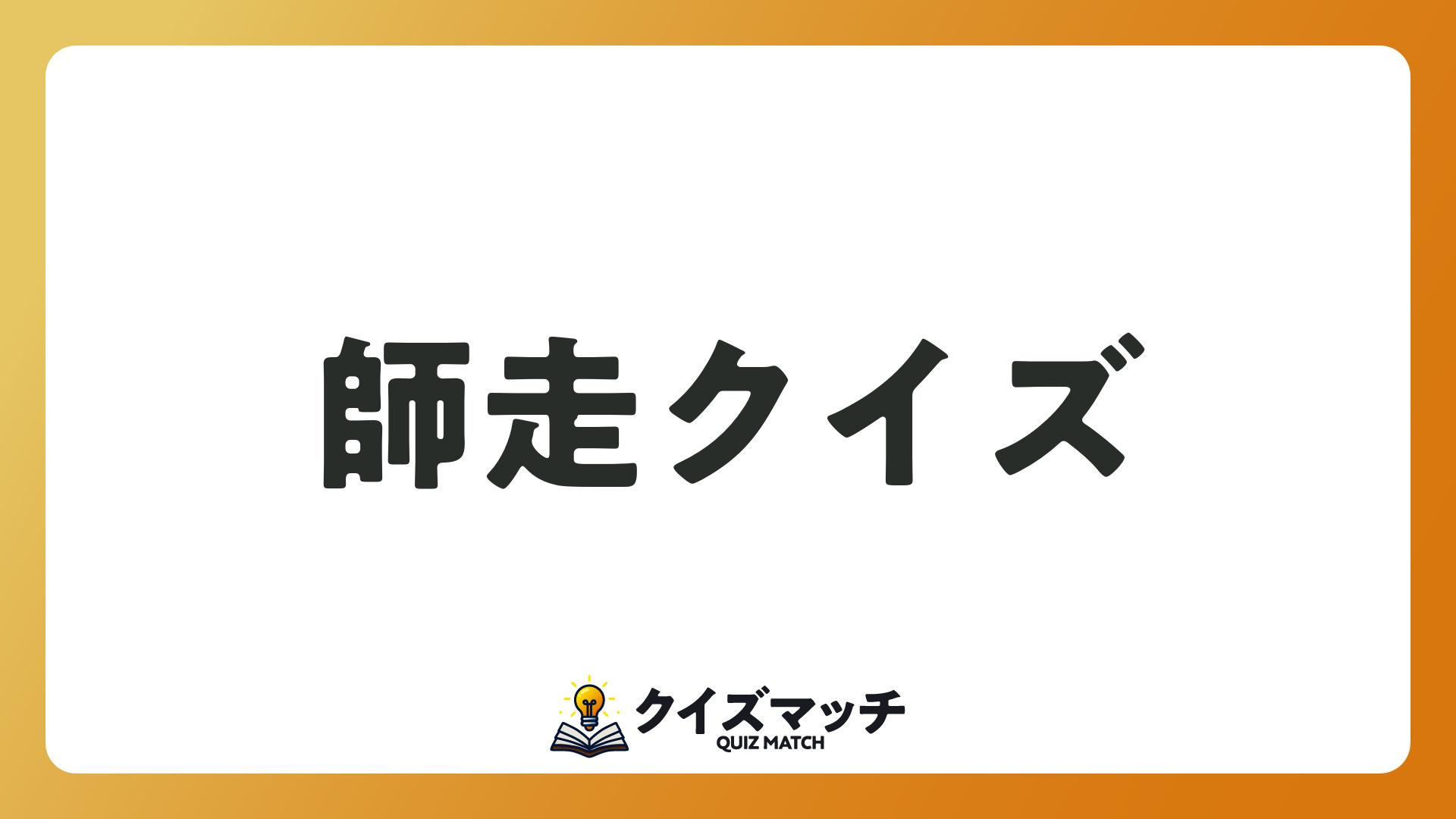日本の暦で「師走」と呼ばれる月は何月でしょうか。師走にまつわる様々な行事や風習について、クイズ形式で探っていきます。年末の慌ただしい時期を彩る伝統的な習慣や、新年を迎えるための意味合いなど、「師走」ならではの文化を10問ご紹介します。忘年会や大掃除、年越しそばなど、今年の師走を振り返る良い機会となれば幸いです。
Q1 : 師走の代表的な風物詩として、夜に各地で行われるイベントは何でしょう?
師走(12月)の風物詩の一つは、各地で行われる「イルミネーション」です。年末の夜を彩るイルミネーションイベントは日本各地の商業施設や公園、観光地などで実施され、クリスマスや年末を象徴する風景として定着しています。この時期には多くの人が家族や友人と出かけて楽しみます。
Q2 : 師走に行われる神事や祭りで有名な「大祓(おおはらえ)は何を目的とした行事でしょうか?」
「大祓(おおはらえ)」は師走の晦日(12月31日)や年2回(6月と12月末)に主に神社で行われる神事で、自分自身や社会に溜まった罪や穢れ(けがれ)を祓い清めることを目的としています。この行事を終えることで、清浄な心で新年を迎えるとされています。
Q3 : 師走に欠かせない年中行事として、家族や親族が集まり、一年を振り返り語らうことを何と呼ぶでしょう?
「年忘れ」は師走の恒例行事で、一年の苦労を忘れ、新しい年への希望を語り合う宴や集まりを指します。現在では忘年会という形で行われることも多く、職場や友人同士で行うイベントにもなっています。家族や親戚で集まる場合もこの習慣の一環です。
Q4 : 師走に新しいものを使うと良いとされるのはどれ?
箸は日本の文化において神聖なものとされています。師走の年末には、新年を清新な気持ちで迎えるために新しい箸を用意するご家庭も多く、「新しい箸で新年の神様を迎えるべし」という言い伝えもあります。他の選択肢は特に師走特有の風習とはされていません。
Q5 : 師走に関係する「煤払い」はもともとどこで始まったと言われている行事でしょう?
「煤払い」はもともと神社仏閣で行われていた行事です。一年のホコリや汚れを払い清め、新年に神様を迎え入れる準備をするために行われていました。江戸時代には一般家庭にも広まり、現在の「大掃除」として根付いています。
Q6 : 師走に一般的に食べられる、日本の伝統的な麺料理は何でしょう?
師走の最終日、大晦日に食べる「年越しそば」は日本の伝統行事の一つです。年越しそばは、細く長く生きることへの願いや、そばが切れやすいことから一年の厄を断ち切る意味をこめています。多くの家庭で大晦日に年越しそばを食べて新年を迎えます。
Q7 : 12月に贈る、感謝の気持ちとしての贈り物を何といいますか?
師走、特に12月に感謝の気持ちとして親戚やお世話になった人に贈る品物のことを「お歳暮」と呼びます。お歳暮は年の暮れに無事であったことへの感謝や、これからもよろしくという意味を込めて贈られる日本独自の習慣です。ビジネス社会でも取引先などに贈ることがあります。
Q8 : 師走に行われる伝統行事で、家をきれいにすることを何と呼ぶでしょう?
師走には年末に大掃除を行う習慣があります。これは新年を迎えるにあたり、家の中を清め、厄を払い福を呼び込むためのものです。江戸時代には「煤払い」とも呼ばれ、神社仏閣などでも行われていました。現代でも12月の終わりが近づくと、多くの家庭で大掃除が行われています。
Q9 : 「師走」の語源の有力な説の一つは何でしょうか?
「師走」の語源は、一般的に「師(僧侶)が仏事で忙しく家々を走り回るから」と言われています。他にも諸説ありますが、この「師が走る」の解釈が最も有名です。昔は大晦日や年末に僧侶を招いて読経などをしてもらう風習があり、そのために師(僧侶)が多忙になることからこの名がついたとされています。
Q10 : 日本の暦で「師走」とはどの月を指す言葉でしょうか?
「師走」とは、旧暦(太陰太陽暦)で12月を指す和風月名です。現在の新暦でも12月の別名として用いられ、年末の忙しい時期の象徴でもあります。語源には諸説あり、「師が走るほど忙しい」などの意味が込められているとされ、お坊さん(師)が年末の仏事で各家を走り回る様子から来ているとも言われています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は師走クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は師走クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。