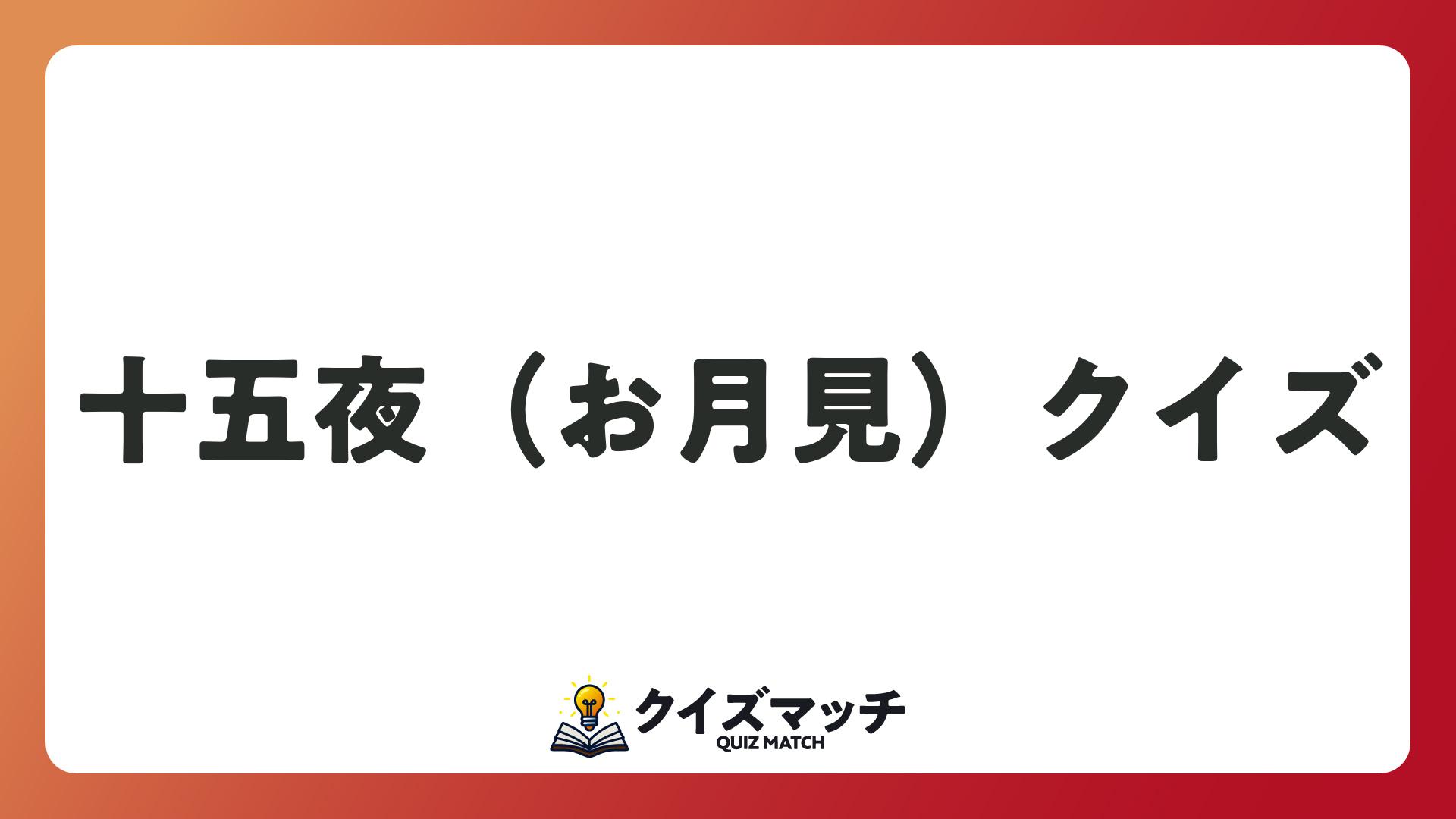秋の夜長に美しく浮かぶ十五夜の月をめぐるクイズに挑戦しましょう。旧暦8月15日に祝われるこの伝統行事は、古くから日本人に親しまれてきました。月の満ち欠けや秋の収穫物を大切にし、家族の健康と豊作を願う意味が込められた風習は、今も変わらず愛されています。日本ならではの季節感と歴史を感じられる十五夜のこと、さまざまな角度からクイズを通して学びましょう。
Q1 : 十五夜に晴天で月がよく見えることを何と呼ぶ?
十五夜の満月が美しく見える日は“名月”と呼ばれます。「名月を取ってくれろと泣く子かな」(小林一茶)など歌にも詠まれ、月がよく見えることは、縁起が良いとされています。名月に対し、曇って月が見えない場合は「無月」、雨の場合は「雨月」と呼ぶこともあります。
Q2 : 十五夜にまつわる秋の味覚で、秋の七草にも含まれるものはどれ?
十五夜に飾る植物のひとつである「はぎ」は、秋の七草にも数えられる秋の代表的な植物です。はぎは、その赤紫色の小さな花が美しく、秋の到来を象徴します。十五夜では、すすきとともに供えたり、秋の味覚や鑑賞として楽しまれることもあります。
Q3 : 日本の伝説で、月に住むといわれる動物はどれでしょう?
日本の伝説では、満月の模様が餅をつく「うさぎ」の姿に見えるとされ、月にはうさぎが住んでいると広く信じられてきました。この話は仏教説話に由来し、ウサギが餅をついている姿は絵本や童話、和菓子などでもよく登場します。各国で月の模様の見立ては異なります。
Q4 : お月見の際、月に見立てて供える団子の一般的な数は?
十五夜のお供え団子の一般的な個数は15個です。この数は“十五夜”にちなんだものです。ピラミッド状に並べるのが伝統的ですが、地方によってはその年の満月の数(12個)、十三夜にちなんで13個など、異なる数で供えることもありますが全国的には15個が最も一般的とされています。
Q5 : 十五夜とともに、もうひとつのお月見の夜として知られる日はどれ?
十五夜に次いで、十三夜も日本独特のお月見行事です。十五夜の後約1ヶ月後、旧暦9月13日にあたり、この日も美しい月が見られるとして月見をします。古来より「片見月(かたみづき)は縁起が悪い」として、十五夜と十三夜の両方で月見するのが善しとされています。
Q6 : お月見の由来とされる文化はどこから伝わったといわれているか?
お月見文化は元々中国由来と言われています。中国の「中秋節」という行事が奈良時代から平安時代にかけて伝わり、日本独自の風習として定着しました。中国でも十五夜には月を愛でながら月餅を食べるなどの風習があり、月を観賞する文化が東アジア全体に根づいています。
Q7 : 十五夜の別名は次のうちどれ?
十五夜は“中秋の名月”とも呼ばれます。これは、旧暦8月15日の月が一年で最も美しく見えることから、そのように称されるようになりました。“小正月”や“彼岸”などは異なる行事、“春の七草”も別の季節行事です。『中秋の名月』という言葉は俳句や和歌などでも古くから使われています。
Q8 : 十五夜のお供えに使われる植物で、稲穂に似ていて魔除けになるとされるものはどれ?
十五夜のお供えによく用いられる植物は“すすき”です。すすきは見た目が稲穂に似ていることから、豊作祈願の意味合いを持ち、また、鋭い葉が魔除けになると信じられてきました。ススキを束ねて飾ることで、その年の家族の健康や安全を祈願する、日本の伝統的なしきたりです。
Q9 : 十五夜でお供えする主な食べ物はなんでしょう?
十五夜のお月見で最も代表的なお供え物は「月見団子」です。まん丸の形は満月を表し、豊作や家族の健康を願う意味も込められています。ほかにも里芋やススキなど、その年の収穫物を供える場合もありますが、団子が最も一般的で、日本各地で形や数の風習が異なるのも特徴です。
Q10 : 十五夜は旧暦で何月にあたる行事でしょう?
日本の十五夜(中秋の名月)は、旧暦8月15日に祝われますが、現代の暦(新暦)では主に9月中旬から下旬にあたります。十五夜は秋の中ごろという意味で、“中秋”とも呼ばれ、この時期の月が一年でもっとも美しいとされています。季節の移り変わりと月の満ち欠けを古くから意識し、大切にしてきた日本ならではの伝統行事です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は十五夜(お月見)クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は十五夜(お月見)クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。