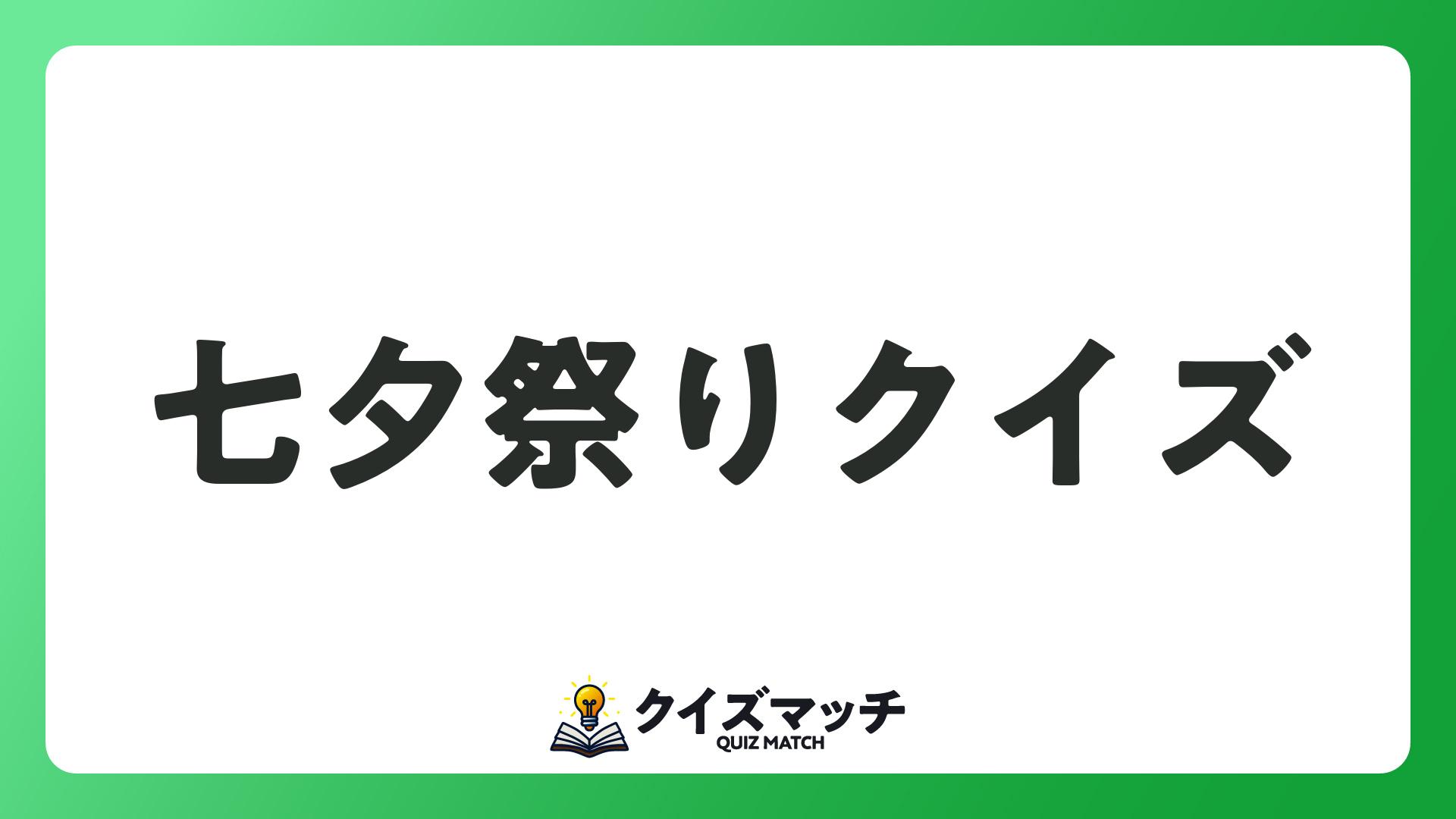七夕の星物語に隠された秘密を解き明かす!七夕祭りクイズ
日本の代表的な夏祭りの1つ、七夕祭り。織姫と彦星の伝説に端を発するこの祭りには、意外な起源や由来が隠されています。古来より受け継がれてきた七夕の習慣や、地域ごとの個性あふれる伝統を、本クイズで学んでみませんか。織姫と彦星の物語の「元」は一体どこにあるのか、笹の意味や仙台の有名な飾りなど、七夕ならではの豆知識がてんこ盛り。七夕ファンも初心者も、クイズに答えながら七夕の魅力を発見していきましょう。
Q1 : 七夕伝説で、織姫がなぜ天帝によって彦星と引き離されたのでしょうか?
七夕伝説では、織姫と彦星は結婚した後、お互いに夢中になりすぎて仕事を怠けるようになったため、天帝(織姫の父)が怒って2人を天の川の両岸に引き離しました。1年に一度だけ再会を許されることになったのが今日の七夕の由来です。天帝が嫉妬したや、雨や星の光ではありません。
Q2 : 日本三大七夕祭りに数えられるのは、仙台、平塚とどこの七夕祭り?
日本三大七夕祭りは、宮城県の仙台七夕まつり、神奈川県の平塚七夕まつり、そして愛知県の一宮七夕まつりです。これらは規模の大きさや、歴史の長さ、来客数で知られています。特に仙台と一宮は古くからの伝統を持っています。大阪、函館、京都も有名ですが三大七夕祭りには該当しません。
Q3 : 七夕祭りでは一般的にどの植物が使われますか?
七夕祭りでは願い事を書いた短冊や飾りを「笹」の枝につるします。笹は生命力が強く、邪気を払うと信じられてきたため、七夕の飾りにふさわしい植物とされてきました。松や楓、桜などは七夕にはあまり使われません。
Q4 : 七夕の物語で、織姫と彦星が天の川を渡って会うのを助けるとされる鳥は何ですか?
七夕伝説では、織姫と彦星が年に一度だけ再会できる際、増水した天の川を渡れない場合にカササギ(鵲)の群れが翼で橋を作り、2人を渡してくれるとされています。これは中国の伝承に由来するエピソードです。ツバメや他の鳥は七夕の物語には関係ありません。
Q5 : 七夕の起源に由来し、女性が技芸の上達を願う風習は何と呼ばれていますか?
七夕の起源とされている技芸上達を願う風習は「乞巧奠(きこうでん)」と呼ばれています。中国で始まったこの行事では、女性が針仕事や詩歌などの技芸の上達を星に願いました。日本に伝わって織姫の話と合わさり、しだいに短冊に願い事を書く現在の七夕になりました。他の選択肢は別の年中行事です。
Q6 : 仙台七夕まつりの飾りで有名な、色とりどりの紙で作る大きな球状の飾りを何と呼びますか?
仙台七夕まつりで有名なのが「くす玉」です。紙で作られた色鮮やかな球は笹飾りの上部に飾られ、その下には長い吹き流しがついています。くす玉は五穀豊穣と幸福を願うシンボルとされています。かざぐるまや吹き流しも笹飾りに用いられますが、大きな球状の飾りは「くす玉」です。
Q7 : 七夕の飾りの1つ「網飾り」は何を表していますか?
七夕の飾りの一つである「網飾り(あみかざり)」は、魚を捕るための網に似せて折り紙で作られています。これは豊漁や食料に困らないようにという祈願が込められています。網飾りは生活の豊かさや幸せへの願いを象徴する飾りです。星の川や着物ではなく、漁に関する意味が強い飾りです。
Q8 : 七夕の笹に飾る短冊は、主にどのような願いを書きますか?
七夕で笹につるす短冊には、もともとは裁縫や織物の上達、技芸の向上を願う言葉が書かれていました。これは織姫が機織りの名手だったことに由来します。時代が進むにつれて願い事の内容も多様化し、勉強の成績向上や運動の上達などになりましたが、基本は「勉強や手芸の上達」を願うのが七夕の伝統です。
Q9 : 七夕の日付は通常何月何日ですか?
日本の七夕祭りは、旧暦では現在の8月中旬ごろにあたりますが、現代では多くの地域で新暦の7月7日に祝われています。由来は中国暦の七月七日の「乞巧奠」という行事からきています。一部の地域では旧暦や月遅れの8月7日に行う場合もありますが、全国的には「7月7日」が一般的とされています。
Q10 : 七夕で有名な織姫と彦星の物語の「元」となった国はどこですか?
七夕の物語である織姫と彦星の伝説は、もともと中国に起源を持っています。中国の「乞巧奠(きこうでん)」という風習が日本に伝わり、日本独自の祭りや伝説と融合して現在の七夕となりました。この星伝説が日本に伝えられ、日本でアレンジされたものが七夕の物語となっています。韓国やベトナムにも類似の行事はありますが、オリジナルは中国です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は七夕祭りクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は七夕祭りクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。